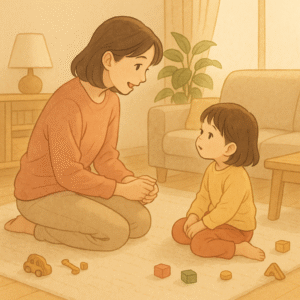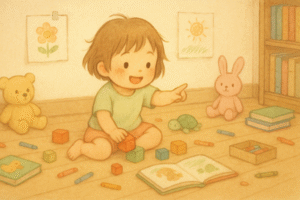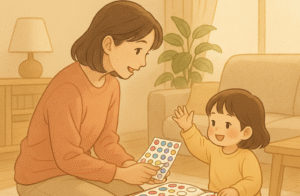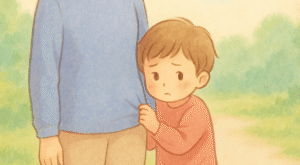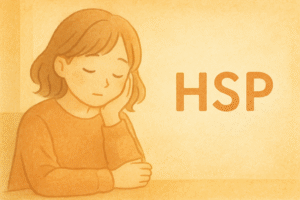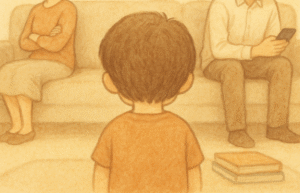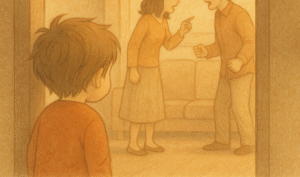はじめに
こんにちは、Dr.流星です。
近年、自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠如・多動症(ADHD)の両方の診断を受けるケースが増えています。実際に入院加療を必要とするケースでも併存が珍しくなくなっている印象です。
これは、かつては別々の障害と考えられ併存が想定されていなかったものの、2013年の米国精神医学会の診断基準改訂(DSM-5)以降はASDとADHDの併存診断が公式に認められるようになったことが背景にあります。その結果、ASDとADHDを両方もつ子どもがより適切に診断されるようになり、臨床研究も世界的に活発化しました。
本記事では精神科医の視点から、このASDとADHDの併存について、最新の信頼できる情報源にもとづき分かりやすく解説します。
1. ASDとADHDの併存率と疫学的傾向
DSM-5の改訂以降、ASDとADHDの両方を持つ子どもの有病率は年々上昇傾向にあると指摘されています。研究ごとにばらつきはあるものの、例えば、海外の研究では、ASDのある人の30~80%にADHDの症状がみられ、逆にADHDのある人の20~50%にASDの特徴がみられると報告されています。日本のある疫学調査ではASD児童の30~75%にADHD症状が併存し、ADHD児童の20~60%にASD症状が併存するとの結果も示されています。こうした数字から、ASDやADHDは単独よりもしばしば複数の特性が混在することがわかります。
DSM-5以前は「両方の症状を満たす場合はASD(当時は広汎性発達障害)の診断を優先しADHDは付けない」という除外規定がありましたが、現在では併存診断が可能となり、それが発達障害の理解を深める大きな転換点となりました。
2. 診断の難しさと単独診断との違い
ASDとADHDが併存する場合の診断は、単独のASDや単独のADHD以上に慎重な評価が求められます。両者の症状には重なりや紛らわしい点が多いためです。例えば、落ち着きのなさや衝動性はADHDの特徴ですが、ASDの子どもでも環境変化への不安からそわそわしたり、感覚過敏で衝動的に行動したりすることがあります。また不注意(集中力の欠如)も、ADHDでは注意散漫さとして現れ、ASDでは興味の限定から指示を聞き逃すなど一見似た振る舞いが起こります。
こうした症状のオーバーラップ(重複)により、専門家でもどちらの特性による行動か判別が難しい場合があるのです。
元々、ASDでは対人コミュニケーションの障害が中心で、ADHDでは多動・衝動や注意力の問題が中心という診断基準上の違いがあります。しかし実際には、一人ひとりの発達特性は千差万別であり、ASDかADHDかを明確に切り分けること自体が難しいケースも少なくありません。そのため診断にあたっては、発達障害の専門医(児童精神科医等)が詳細な発達歴の聴取や行動観察、場合によっては知能検査・発達検査などを組み合わせて総合的に評価します。
特にASDとADHDが併存している子どもでは、症状が一方の障害だけでは説明できないため、多角的な視点からのアセスメントが重要です。診断名にこだわるよりも、その子が何に困難を抱えているか、どのような支援が必要かを把握することが大切だというのが精神科医の共通した考えです。
コラム:DSM-5での変更
DSM-5によりASDとADHDの併存が認められるようになったことは前述しましたが、これは診断漏れを防ぐための大きな改善でした。それ以前はASDの診断がつくとADHDとは診断されず、結果としてASDでの注意問題が見過ごされる(ADHDの特性はないとの思い込み)ことが懸念されていたのです。現在では併存が前提に診断できるため、本人の困りごとを正確に反映した診断が可能になりました。例えば、ASD特性とともに顕著な多動・不注意があればASD+ADHDと診断し、それぞれに応じた支援策を検討できます。これは単独診断では得られない視点であり、臨床現場でも有用だと感じます。
3. ASDとADHDを併せ持つ子どもの生活上の困難
ASDとADHDの両方の特性を持つ子どもは、家庭や園・学校、さらには社会生活で日常的に様々な困難に直面しやすくなります。研究でも、ASD+ADHDの子どもはASDのみ、ADHDのみの場合に比べて日常生活上でより多くの困難を抱えると報告されています。ここでは具体的な場面ごとに、どのような困難が生じやすいか見てみましょう。
家庭
家庭では、生活のルーティンに関する問題が現れます。ASDの子どもは日課や手順が変わることに強い不安を覚えるため、突然の予定変更でパニックになることがあります。同時にADHDの特性である注意散漫や忘れ物の多さから、時間通りに準備ができない、指示を何度も伝えなければ動けない、といったことが起こりがちです。つまり、ADHDの特性が原因で日課や手順が変わってしまい、ASDの特性からパニックになったり、親に当たったりすることになります。その結果、親子ともにストレスが溜まり、親が叱責を繰り返し、子がまた癇癪を起こしてしまうという、お互いに自己肯定感を下げる悪循環にもなりかねません。家庭内ではこうした養育上の悩みが積み重なりやすいため、親御さんへのサポート(ペアレントトレーニング等)も重要になります。
幼稚園・保育園
集団生活のはじまりである幼稚園や保育園では、周囲の大人から集団行動への適応を求められます。ASDの特性がある子は新しい環境や人間関係に慣れるのに時間がかかり、他児とのトラブル(おもちゃの貸し借りができない、ルールを理解できない等)も起こりやすいです。そこにADHDの落ち着きのなさや順番を待てないといった行動が加わると、集団生活で問題行動が目立つ子として扱われてしまうことがあります。例えば、お片付けの時間に一人だけ走り回っていたり、先生の指示を無視して勝手な行動をしたうえにこだわりの強さから訂正できなかったりすると、周囲から「わがまま」「しつけがなっていない」と誤解されることもあります。実際にはその子自身もどうしてよいかわからず混乱しているのですが、適切な理解やサポートがないと園生活で孤立したり、保育者も対応に苦慮したりするケースがあります。
学校
小学校以降になると、学習面と対人関係面で困難が顕在化します。ADHDの不注意傾向から授業中に集中できない、宿題や持ち物管理が苦手で忘れ物・提出物のミスが多発するといった学習上のつまずきが生じやすいです。一方ASDの社会性の難しさから、友人とのコミュニケーションがうまくいかないこともしばしばです。例えば、会話の文脈を読み取れず一方的に喋り続けたり(ASDの特徴)、思ったことをすぐ口にしてしまって友達を怒らせたり(ADHDの衝動性)という具合に、人間関係で誤解や衝突が起こりやすいのです。その結果、学校ではいじめの対象になってしまったり、自尊心の低下から不登校傾向になる子どもも見られます。また教師側も、本人の特性への理解がないと「怠けている」「わざと反抗的に振舞っている」と判断してさらに叱責するなど、事態が悪化する恐れがあります。
社会生活(青年期以降)
思春期・青年期になると、ASD+ADHDの当事者は自分の特性と社会の要求とのギャップに悩みやすくなります。高校・大学や就労の場面では、組織の規則や暗黙の了解を理解すること、時間管理や段取り力、対人スキルなどが求められます。ASDの特性で空気を読むことが苦手だったり抽象的な表現(例え話など)が理解できなかったりする、ADHDの特性で締め切りを守れなかったり資料の準備や連絡を忘れてしまったりといったことが重なると、周囲からの評価が下がりやすく、結果として社会に適応できず、引きこもりや不安・抑うつ状態になるリスクも高まります。実際、日本の調査でもASDやADHDの人は不安障害やうつ病を高頻度で併存しやすいことが分かっています。これは二次障害と呼ばれ、発達障害の特性による生きづらさが長年積み重なることで起こる心理的問題です。周囲の適切な理解と支えがないと、青年期以降に社会生活で生きづらさを強く感じてしまうことから、生涯にわたる支援の必要性が議論されています。
以上のように、ASDとADHDが併存することで生活上の困りごとは多方面にわたります。研究でも、併存群の子どもは適応能力や生活の質(QOL)が単一のASD児より低いという報告があり、臨床的にも支援の難易度が上がる傾向があります。しかし、適切な理解と対応があれば子どもの能力を伸ばし困難を軽減することは可能です。次章では、その支援体制について述べます。
4. 支援体制の複雑さと課題(教育・医療・福祉の連携)
ASD+ADHDの子どもを支えるための支援体制は、一つの分野だけでは完結せず、教育・医療・福祉など多領域にまたがる連携が必要です。しかし、この連携を実現するには様々な課題があります。精神科医の立場から、現状の支援体制の複雑さと今後の課題を整理してみます。
教育
まず教育現場では、ASD+ADHDの子どもは特別支援教育の対象となる場合があります。日本の文部科学省も、ADHDの子どもには学習障害(LD)や自閉症スペクトラム等の併存が多く見られることを踏まえ、一人ひとりの特性に合わせた教育の必要性を提言しています。具体的には、通常学級内でも特別支援教育コーディネーターや通級指導などを活用し、その子の苦手さに応じた配慮(席を集中しやすい場所にする、掲示物を減らす、視覚的な手順を示す等)を行うことが推奨されています。
しかし、現状では学校側の専門性や人員にばらつきがあり、支援の質に地域差があるのが実情です。また、教師への発達障害研修やクラスメートへの人権教育(いじめ防止教育)を通じて、学校全体で理解を深める取り組みも重要です。これらを恒常的に行うには、教育現場の負担も大きく、人材育成と配置という課題があります。
教育現場の理解があれば、発達障害の児童も勉学に励むことができたり、その子の得意な分野を伸ばしてあげることができたりするのですが、全ての教育機関にそれを求めることは現状難しいと親も理解しておく必要があります。
医療
次に医療面では、児童精神科や小児科での診断・治療が中心となりますが、それだけでなく保健所や発達障害者支援センターとの連携も欠かせません。早期発見のためには、乳幼児健診や就学前のスクリーニングでリスクを察知し、医療につなげる地域体制が求められます。日本では発達障害者支援法のもと、各都道府県に発達障害者支援センターが設置され、療育(発達支援)や親相談などを行っています。医療と福祉の橋渡し役として、こうした機関が地域の保育所・学校・病院と情報共有しながら支援することが理想です。
現実には、情報連携の不足や支援者リソースの不足により、「診断は受けたがその後の支援先が見つからない」「関係機関連携がうまくいかず支援が途切れる」といった例もあります。この点について、厚生労働省と文部科学省は協力して発達障害ナビポータルを立ち上げ、教育・医療・福祉・労働といった各分野の支援者がお互いの取り組みを理解し連携を強化する必要性を訴えています。支援を受けにくい地域などでは是非活用していきたいシステムです。
福祉
福祉の面では、ASD+ADHDの子どもと家族は行政サービスの利用も視野に入ります。例えば、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の取得、障害者福祉サービス(居宅介護、放課後等デイサービス等)の利用などです。ただ、ASDやADHDは知的障害を伴わない場合制度の狭間に置かれやすく、「手帳の取得基準に該当しないため支援を受けにくい」といったケースもあります。
また、就労支援の場面でも、一般雇用か福祉的就労か判断が難しいグレーゾーンの若者が少なくありません。支援制度を利用するには親の情報収集と手続きの努力が必要で、精神科医として診療していても「制度が複雑でどこに相談すればいいかわからなかった」との声をよく耳にします。
ご家族は行政の窓口に繰り返し行ったり、書類を準備したりと大変な点もありますが、相談先を1つでも多く設けておくことはその後の支援の幅にも繋がるため、家庭内で抱え込まず、是非福祉の支援もご検討ください。
以上のように、教育・医療・福祉の縦割りの壁や情報共有の難しさ、人材や資源の不足など、ASD+ADHDの支援体制には課題が山積しています。改善の方向性としては、地域の関係機関がチームとなってケース会議等で協働する仕組みや、親支援(ペアレントメンター制度など)の充実、発達障害に関する社会一般の啓発などが考えられます。幸い、国レベルでも「家庭・教育・福祉の三位一体の支援」(トライアングルプロジェクト)を推進しており、今後徐々にではありますが支援体制の強化が期待されています。
5. 治療(薬物・非薬物)における対応と難しさ
ASDとADHDの併存に対する治療アプローチは、薬物療法と非薬物療法(心理社会的支援)の両面から検討されます。ただし、それぞれエビデンス(科学的根拠)に基づいた工夫が必要であり、単独のASDやADHDの場合とは異なる難しさもあります。精神科医の視点で、主な治療・支援法とその対応について説明します。あくまで参考程度のものであり、本人の特性に合わせた調整となり、効果にも個人差があることはご理解ください。
非薬物療法(環境調整・行動面の支援)
ASD+ADHDの治療では、まず環境調整や行動療法など非薬物的アプローチが優先されます。具体的には、先述の教育的支援とも重なりますが、生活環境を整える工夫(例:静かな学習スペースの確保、視覚的スケジュール提示)や、ソーシャルスキルトレーニング(SST)による対人関係スキルの向上、認知行動療法(CBT)による不安や衝動コントロールの練習などが挙げられます。
中でも、ペアレント・トレーニング(親訓練)は海外・国内ともに強く推奨される手法です。ペアレント・トレーニングでは保護者が子どもの行動理解と適切な対応法を学びますが、多くの研究が親の育児スキル向上やストレス軽減、子どもの問題行動軽減に効果があることを示しており、ASDやADHDがある子どもたちへのエビデンスのある支援策として国際的に認知されています。実際、日本の診療ガイドラインでもADHDの心理社会的治療の一つに位置付けられ、発達障害者支援法に基づく家族支援施策でも普及が図られています。併存児の場合、親は二重の課題(ASDの特性対応とADHDの行動対応)を抱えるため、専門家の指導の下で系統的に対処法を学ぶことは非常に有益です。例えば、「指示は短く具体的に」「良い行動をしたら即座に褒める」「問題行動には一貫した対応をする」といった基本スキルが身につくと、家庭での混乱がかなり防げるようになります。
さらに、ASD+ADHDの子どもでは二次障害の予防も治療目標となります。不適切な対応を避け、成功体験を積ませることで自己肯定感を高め、将来的なうつ病や不安症の発症リスクを下げることが期待できます。その意味でも、薬に頼る前に周囲の環境を整え、子どもの行動面をサポートすることが重要なのです。
薬物療法
非薬物療法を行ってもなお日常生活の改善が不十分な場合、必要に応じて薬物療法が検討されます。しかし、ASD+ADHDの薬物療法にはいくつか特徴や注意点があります。
まず、ADHD症状に対しては、中枢神経刺激薬(メチルフェニデート系)やノンステimulant(アトモキセチン、グアンファシンなど)が用いられます。海外ではアンフェタミン系薬も使われますが、日本では2025年現在、メチルフェニデート徐放剤(商品名:コンサータ)やリスデキサンフェタミン(商品名:ビバン®)、アトモキセチン(ストラテラ®)、グアンファシン(インチュニブ®)の4種類が小児ADHD治療薬として承認されています。
ASDを併存する子どもにも、これらADHD治療薬が有効な場合が多いことが臨床研究で示されており、実際に注意・集中力の改善や多動・衝動の軽減が見られるケースがあります。ただし一方で、薬の効き方や副作用の出方に個人差が大きく、注意が必要です。特にASDを持つ子どもは薬剤への反応が過敏なこともあり、刺激薬でイライラや不眠が強く出るといった副作用報告もあります。そのため少量から開始して慎重に増量し、親御さんと副作用について十分情報共有しながら進めます。もし薬が合わず不安定になった場合は速やかに中止し、担当医にフィードバックすることが大切です。
薬物療法はあくまで生活を送りやすくするための補助的役割であり、効果とデメリットを天秤にかけつつ、子どもと家族にとってプラスになる範囲で用いるという姿勢が求められます。
ASDそのものの中核症状(社会性やこだわり)に直接効く薬は存在しません。しかし、ASDに伴う易刺激性や興奮、強いこだわりによるパニックなどに対しては、非定型抗精神病薬(リスペリドンやアリピプラゾールなど)が補助的に使われることがあります(承認あり)。これらは主に攻撃的行動や自傷行為のある重症例に限定されますが、適切に使えば癇癪や攻撃性を和らげ、環境調整や療育を行いやすくする助けになります。しかし、根本的に「治す」というわけではないため、「コントロールする」という意識で期待しすぎないようにします。
その他、睡眠障害がひどい場合はメラトニン製剤や漢方薬、てんかんを併発していればてんかんに伴う精神症状をきたすことがあるため抗てんかん薬など、症状に応じた薬を組み合わせることもあります。
いずれにせよ、ASD+ADHDでは症状が混在しているため、どの症状に優先的に薬物介入すべきか主治医が全体像を見て判断します。そして薬を使う際は、家族にも効果や副作用、注意点を十分説明し、医療者と養育者がチームとなって子どもの様子を見守ることが理想です。例えば「この薬で多動は改善するが食欲が落ちるかもしれないので食事時間を工夫しましょう」「夕方に薬が切れてくると宿題で集中しづらいかもしれません」といった情報共有を行い、薬剤の特徴や副作用が生活に与える影響も一緒に考えていきます。
薬物療法単体ではなく総合的な支援計画の中の一要素として位置づけることが、併存児の治療では特に重要なのです。
コラム:エビデンスに基づく支援の実例【成功体験を積ませる】
ASD+ADHDの子どもに対する有効な支援の一つに、「成功体験を意図的に積ませる」ことがあります。例えば学校場面で、ADHD傾向の子はミスが多く叱られがちですが、支援員が付き添ってその子の得意な場面で活躍できる役割(黒板消し係や機器の操作など)を与えるといった工夫です。これは単に気分を良くするだけでなく、適切な行動を増やす行動療法のテクニックでもあります。実際に褒められる体験が増えると自己肯定感が上がり、学校への適応度も改善したという報告があります(このような介入は教師の理解と協力が不可欠ですが)。エビデンスの視点から言えば、親や教師が望ましい行動に注目して強化することはABA(応用行動分析)の基本であり、PTやSSTでも重視されています。併存児の場合、一見すると問題行動ばかり目につきますが、その中にも「小さな良い行動の芽」が必ず存在するので、それを見逃さず褒め伸ばすことが、長期的な発達支援につながります。
おわりに
ASDとADHDの併存について、最新の知見を交えながら解説しました。ASDとADHDが一緒に存在するケースは決して珍しくなく、むしろ発達障害の子どもにとっては「自分だけ他と違う特性を複数抱えている」という現実と向き合っていることになります。そのため、本人の困難さは周囲が想像する以上に複雑です。
しかし、正しい診断と多面的な支援アプローチがあれば、本人の可能性を最大限に引き出し、生活のしづらさを緩和することができます。大切なのは、診断名にとらわれすぎず、その子の特性やニーズに応じたオーダーメイドの対応をすることです。
決して家庭内で抱え込まず、専門家や支援機関に相談してほしいと思います。幸い、近年は発達障害支援の仕組みも増えつつあり、エビデンスに裏付けられたプログラムも利用できるようになっています。専門的な知識を一般の皆さんにも共有することで、このテーマへの理解が深まり、当事者とご家族への温かい支援の輪が広がることを願っています。
参考文献・情報源
- 山室和彦ほか「自閉スペクトラム症の併存による注意欠如・多動症の血液動態反応への影響」『児童青年精神医学とその近接領域』59巻2号, 2018
- 大阪メンタルクリニック コラム「ADHDとASDの合併」前田雅春監修, 2024
- 小野和哉「ADHDに関する最近の話題 ―成人期への連続性と自閉スペクトラム症との関係―」東京精神医学会シンポジウム資料, 2019
- 厚生労働省科研費報告書「発達障害の診断・疫学に関する研究」2018
- 日本小児心身医学会 一般向け解説「注意欠如・多動症」深井善光執筆, 2020
- 文部科学省 中央教育審議会資料「注意欠陥・多動性障害に関する学校における配慮事項(案)」2016
- 国立障害者リハビリテーションセンター他「発達障害ナビポータル」2018-2023
- 岡田俊「自閉スペクトラム症とADHDを含む小児神経発達症の薬物療法」ファーマスタイル, 2021
- 井上雅彦ほか「発達障害に対するペアレント・トレーニングの地域実装と課題」『発達障害研究』45巻3号, 2023
- IRCN東京大プレスリリース「Autism+ADHD co-occurrence ≠ Autism + ADHD(自閉症とADHDの併存状態の神経学的特性)」2023
- 科研費「ASD・ADHDにおける認知特性の性差と発達過程の研究」概要, 2017
- その他、厚労省・文科省ガイドライン、公的研究論文 等