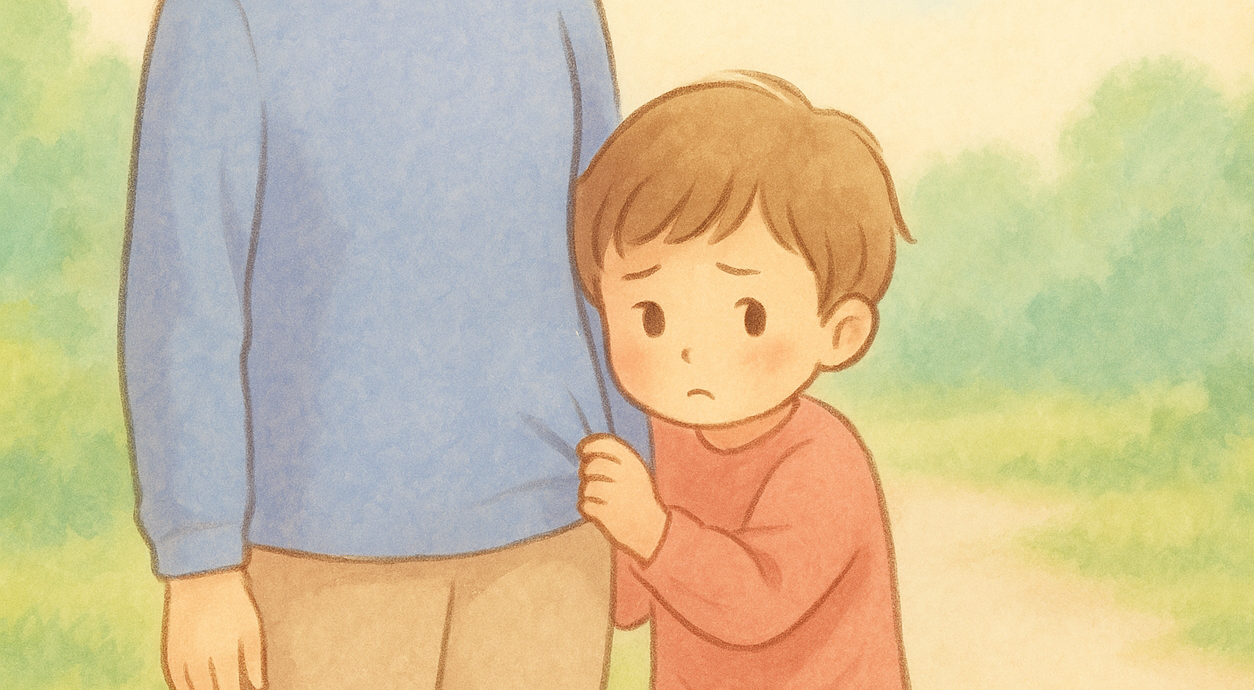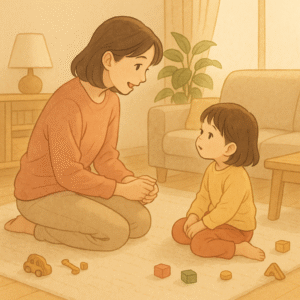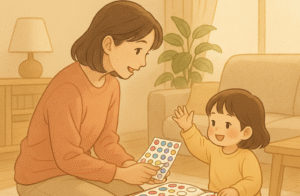こんにちは、Dr.流星です。
「うちの子、人見知りがすごくて……」「緊張すると固まってしまうみたいで……」というパパママの声をよく聞きます。慣れない人や環境に全然緊張しない子もいれば、特に初めての状況で本来の自分を出せなくなってしまう子どももいます。
そんな「人見知り」に今回は焦点を当てて、年齢別にまとめていきたいと思います。
早速みていきましょう!
乳児期(0〜1歳): 人見知りの始まりは成長のサイン
脳が成長している証拠
生後6〜12か月頃になると、多くの赤ちゃんに「人見知り」が見られ始めます。見知らぬ顔を認識すると不安を感じ、慣れた養育者から離されると泣き出すことも珍しくありません。しかし、これは脳の発達により「知っている人」と「知らない人」を区別できるようになった証拠であり、健全な成長過程の一部です。人見知りの現れ方や継続期間には個人差がありますが、一般的には生後8〜9か月頃に始まり、遅くとも2歳頃までには落ち着いていきます。「脳が成長してるんだな、嬉しい!」くらいの気持ちで見守りましょう。
コラム:「親が人見知り」は遺伝する?
赤ちゃんの人見知りが激しいのは、決して親御さんの育て方のせいではありません。科学的な知見によれば、人見知りの起こりやすさは生まれつきの気質や本能的な脳の働きによるところが大きいとされています。たとえば「小さい頃にあまり外出しなかったから」「親が内向的だから」などの外的要因は本質的な原因ではないことが分かっています。むしろ、人見知りは赤ちゃんの大切な自己防衛反応であり、この時期に見られるのは成長のサインと言えるでしょう。
精神医学的な視点からの注意点
多くの赤ちゃんは人見知りをしますが、もし全く人見知りをしない場合には留意が必要です。発達障害(自閉スペクトラム症など)をもつお子さんでは、知らない人に対して警戒や不安を示さないことがあり、親と他人の区別がついていない場合があります。もちろん個人の性格によって人見知りしない赤ちゃんもいますが、発達の一指標として「ある程度の警戒心」が見られるのが通常です。一方で、人見知りの程度が極端に強かったり長引いたりする場合は、より広汎な不安傾向の可能性も考えられます。このようなケースでは念のため小児科医や児童精神科医に相談し、家庭環境や発達の様子を評価してもらうことが望ましいでしょう。
赤ちゃんの不安に寄り添う
人見知りをして泣いているときは、「びっくりしたんだね。大丈夫、大丈夫、ママがいるよ~」などと声をかけながら優しくあやし、赤ちゃんが安心できるようにします。過度に「なんで泣くのー?」と大騒ぎしたり「泣いちゃダメでしょ!」と叱ったりせず、穏やかに見守ることが大切です。無理に他人に抱かせようとはせず、泣いてしまったときは親が安心感を与え、赤ちゃんのペースに合わせて慣れさせていきましょう。
慣れた環境で徐々に慣らす
どうしても新しい人に預ける必要がある場合は、いきなり離れるのではなく事前に顔合わせの時間を設けると効果的です。例えば新しいベビーシッターさんが来る際には、事前に親も交えて何度か一緒に遊んでもらい、赤ちゃんがその人に慣れてから本格的に預け始めます。親が留守にする間に祖父母にみてもらう場合も、可能なら1〜2日前から、難しければ数時間前から一緒に過ごしてもらうなど、いきなりパパママがいなくなることは避けることが望ましいです。
安心のタネを持たせる
人見知りのある赤ちゃんを他の人に預けるときは、お気に入りの毛布やぬいぐるみ(いわゆる「安心毛布」)を持たせたり、親が必ず笑顔で「行ってきます、後で迎えに来るね」と声をかけてから離れるようにします。「親」という安全基地がなくなるだけでも不安ですから、知らない間にパパママがいなくなっていることに気づくと赤ちゃんは一気に不安が増すため、こっそりいなくなることは避けましょう。親の「また必ず戻ってくる」という態度が赤ちゃんに安心感を与え、人見知りの不安を和らげます。
幼児期前半(1〜3歳): 慣れと自我の芽生えによる人見知り
「慣れる」のに時間がかかるようになる
1〜3歳の幼児期になると、基本的な人見知りのピークは過ぎますが、それでも慎重な性格のお子さんは初対面の人や初めての場所に警戒心を示します。歩けるようになり行動範囲が広がる一方で、見知らぬ環境では親の後ろに隠れたり、しばらく様子をうかがってから遊び始めたりする子も多いです。例えば、図書館の読み聞かせ会に行っても、馴染むまでお母さんの膝から降りない、初めての公園では見知らぬ遊具に近寄るまで時間がかかる、といった具合です。これはこの時期の子どもによく見られる反応であり、特に内気な気質(いわゆる”slow to warm up”タイプ)の子どもでは顕著です。
「自我」が芽生え、「個性」が出てくる
この頃になると子ども自身の「自我」や「こだわり」も出てくるため、人見知りの表れ方にも「個性」が出ます。たとえば、2歳前後ではお気に入りの特定の友達や保育士さんにばかり懐き、他の大人には人見知りするケースもあります。また、新しい保育園に通い始めたばかりの頃は毎朝泣いて別れを惜しむ子もいるでしょう。しかし多くの場合、保育園や幼稚園で遊んでいるうちに不安が薄れ、時間とともに泣かずにバイバイできるようになります。登園後しばらくして落ち着くようであれば、心配しすぎず見守って良いサインです。周りの子と比べてしまい、「うちの子は人見知りが激しい…」「親から全然離れてくれない…」とパパママの悩みが出てくるのもこの時期かもしれません。
見逃したくない「不安の強さ」
人見知りをする中で、幼児期の人見知りが極端に強く集団に入れない場合は注意が必要です。例えば、3歳近くになっても親から離れることに強い恐怖を示して集団生活に全く適応できない場合、それは単なる人見知りではなく「分離不安症」などに発展している可能性があります。また、特定の場所(例えば、園や人混み)にいる時だけ全く話さない、動かない(表情が変わらない、固まってしまう)という場合は「場面緘黙 (ばめんかんもく)」(選択性緘黙とも言う)の可能性も考えられます。場面緘黙の子どもは家庭では普通に話せても、園や学校など特定の社交場面で全く話せなくなりがちで、多くは社交不安障害(人前で極度に緊張する症状)を併せ持つことが知られています。もしお子さんが園で全く話せず友達や先生と関われないようであれば、早めに専門家に相談し、必要なら心理的支援を受けることが大切です。
温かい見守りと励まし
初めての場所や人に緊張しているときは、無理に集団に押し出すのではなく、しばらく親がそばに寄り添って安心感を与えるようにします。抱っこが安心するなら抱っこを続けて、ちょっと距離をとることが安心につながるならお友達や苦手なものから離れた場所でパパママと遊ぶなど安全安心な状況をつくってあげましょう。そうすると、抱っこされた状態や遠くからみている状況から徐々にその場に慣れて、もしかしたら「向こうに行きたい」「あれで遊びたい」と言ってくれるかもしれません。そうして、お子さんが一歩踏み出せたら大いに褒めて励まし、自信につなげます。「○○ちゃん、自分からあいさつできたね!偉い偉い!」「○○くん、自分から遊ぼうって言えて、すごいね!」といった行動に焦点を当てた具体的な声かけが効果的です。
馴染みやすい環境づくり
人見知りの強い幼児には、慣れた場所や少人数から社交の練習を始めると良いでしょう。「初めての場所+初めての人+初めての人がたくさん」だと初めて尽くしで不安が強くなります。例えば、お友達を初めて家に招くときは、自宅という安心できる環境で新しいお友達と2人という状況から遊ばせ始め、慣れてきたら徐々に人数を増やします。公園デビューの際も、まずはパパママと一緒に遊具を見て回り、本人が「遊んでみようかな」という気持ちになるのを待ちます。親が「あの滑り台面白そうじゃない?」「この赤いブランコかわいいね」など興味を持てるような声掛けをすることも有効です。そうやって周囲の子や環境に興味が出てきたら「一緒に滑り台滑ってみる?」「お友達におもちゃどうぞしてあげよっか」など声をかけ、子どものペースで遊びの輪に入れてあげることが大切です。それでも怖がってしまう場合は「じゃあ、今日はパパと遊ぼうか。今度はお友達に遊ぼうって言えたら嬉しいね」などと無理をしなくてもいいことを教えてあげます。
気質を理解して周囲へ伝える
お子さんが人見知りしやすいタイプであることを、周囲の大人(保育士や祖父母、お友達のママさんなど)にも伝えておきましょう。「この子は初めての場所では緊張して固まって時間はかかってしまうけれど、慣れると元気に遊びます」「このおもちゃや遊びが好きで、その時は安心できるみたいです」といった情報を共有することで、周囲の大人も適切にサポートしやすくなります。これは子どもの安心感につながり、周囲の大人がペースを合わせることで人見知り克服の助けになります。
幼児期後半(3〜6歳): 友達関係と社会性の発達
「個性」として社会性に違いが出てくる
幼児期後半、いわゆる就学前の時期になると、多くの子どもは友達と遊ぶ楽しさを知り、社会性がぐんと発達します。しかし、この頃でも引っ込み思案な子どもは大勢の中では恥ずかしがって本来の自分を出せないことがあります。幼稚園や保育園でみんなが元気に遊んでいる中、一人の子が隅でモジモジしている…という光景は珍しくありません。この年齢では、人見知りは徐々に「恥ずかしがり屋」「内気」といった性格・個性として表現で語られることが多くなります。保護者から見ると「うちの子は自己主張が苦手で、園でも大人しいみたいで…」と心配になるかもしれません。しかし、専門家の視点では、友達の数はそれほど重要ではなく、1人でも気の合う友達がいて楽しく遊べているなら心配いらないとされています。むしろ無理に活発な子集団に入れようとすると嫌な出来事や強い緊張を経験してい以前より状況が悪化する可能性もあります。その子なりのペースで交友関係を築けるよう支えることが大切です。
まずは「理解」して受け入れる
まずはその子の「個性」として理解し、受け入れることが重要です。例えば、5歳の女の子で、新しい園ではなかなか自分から友達に話しかけられずポツンとしがちでも、家では親や兄弟・姉妹と元気におしゃべりできる場合、「外では緊張しやすい子なのだな」と理解してあげてください。その上で、周囲の大人とも連携し「きっかけ作り」をそっとサポートすると良いでしょう。親が活発で人付き合いが得意なタイプだと、「うちの子に限って内気なわけがない」「きっかけさえあればすぐに治る」とその子の個性を受け入れないまま人見知り改善を焦ることがあるかもしれません。しかし、それはその子の気質によるものなので荒療治や強制ではなかなか改善しないどころか、より人見知りを悪化させてしまう結果になってしまいます。不安が強い子どもにとってそういった体験は本当に辛いものであり、後々親に対して負の感情を抱くこともあります。なので、「これがこの子の個性なんだな」としっかりと理解して、受け入れることから始めてみてください。
神経発達症(発達障害)の特性として目立つことも
また、この時期に顕著な人見知りや内気さの裏に、発達障害が潜んでいるケースもあります。自閉スペクトラム症(ASD)の特性を持つ子どもの中には、同年代の子とうまく遊べず一人ぼっちになったり、大人の指示が通りにくく「集団行動が苦手な恥ずかしがり屋」と誤解されたりする例があります。しかしASDの場合、恥ずかしさというより社会的なやりとりの難しさが根底にあります。例えば、ごっこ遊び(ヒーローごっこ、おままごとなど)に入っていけなかったり、順番待ちができなかったりといった形で現れるため、単なる人見知りとは対応法が異なります。もし言葉の発達の遅れや極端なこだわり行動などが併せて見られる場合は、小児精神科で発達相談を受け、早期から専門的支援を受けるようにすると良いでしょう。
得意分野で自信づけ
恥ずかしがり屋のお子さんには、その子の得意なことを伸ばして自信につなげる支援も有効です。例えば、絵が好きな子には家でも存分に描かせて作品を誉め、作品を友達や知り合いに見せる機会を作ると「すごいね!」と注目される体験が得られます。それが自己肯定感につながり、人前でも積極性を発揮する一歩になります。
小さな目標を積み重ねる
いきなり大勢の前で発表させるより、まずはママ、次に家族の前で、と達成可能な小さな目標を設定し成功体験を積ませましょう。例えば、「今日は先生に自分からあいさつする」「明日は友達に話しかけてみる」といった目標を一緒に立て、できたら大いに褒めます。人前での緊張は、場数を踏むことで和らいでいきます。苦手な状況を避け続けるより、小さな「できた」でもいいので「経験」を積み重ねることが大切です。易しい課題から挑戦し、段々ハードルを上げていく方法がおすすめです。緊張する場面に繰り返し臨むうちに、「嫌だけどできる」「少し緊張するけど大丈夫」と感じられる範囲が広がっていきます。
努力や過程を認める
人前で発言・発表したときの結果(上手にできたか、みんなの反応が良かったか)よりも、挑戦したこと自体を評価してあげてください。仮に発表で言葉に詰まってしまっても、「手を挙げて発表しようとした勇気がすごいよ!」といった声かけをすることで、子どもは「恥ずかしかったけど頑張った自分」に気づき、次への意欲が湧きます。また、「ママ・パパが喜んでくれるなら頑張ってみよう」という意欲が改善につながるきっかけになることもあります。
子どものペースを尊重
内気な子は心の準備に時間がかかります。集団遊びに参加するときも、「早くみんなのところに行きなさい」と急かすのは逆効果です。子どもなりのタイミングで輪に入れるよう、「あ、みんなで滑り台するみたいだよ!行ってみようか」と見守りつつチャンスを作ってあげましょう。タイミングを逃してうまく入れなかった場合も「次またお友達が遊んでたらママも一緒に声かけてみるね」とフォローし、決して責めないことが大切です。
学童期(6〜12歳): 学校での人見知りと対人スキルの習得
学校生活の中で人見知りが目立つようになる
小学校に上がると、子どもたちはさらに広い社会の中で生活を始めます。この時期、人見知り傾向のある子どもは教室で自分から発言できなかったり、新しい友達になかなか話しかけられなかったりすることがあります。学校という集団生活では、シャイな子は目立たず静かに過ごしているため、一見大きな問題がないように見えるかもしれません。しかし、心理的には、内気な子どもは教室を「潜在的に緊張を強いられる場所」だと感じていることがあります。この場合、常にストレスのかかった生活が続き、その後の精神状態に影響したり、精神疾患の発症に寄与したりします。研究によれば、小学校期に人見知りが強い子どもは交友関係や情緒面で様々な困難を抱えやすいことが示されています。例えば、消極的な性格のために遊びの仲間に入れてもらえず孤立したり、いじめの対象になる要因となったりする場合があります。また、自尊心が低くなりがちで、不安や抑うつ傾向といった内向きの問題(internalizing problems)を抱えやすいとも指摘されています。学業面でも、発表や質問ができないために授業への参加度が低くなり、理解が遅れたり成績が伸び悩んだりすることがあります。こうした困難が重なると、本人はますます自信を失い、学校が憂うつな場所になっていきます。
気持ちを言葉で表現できるようになってくる
では、親として学童期の人見知りの子にどう向き合えばよいのでしょうか。この年代では、子ども自身が「恥ずかしい」「みんなにどう思われるか不安だ」といった自己意識(思い)を言葉で表現できるようになってきます。まずはお子さんの気持ちにしっかりと耳を傾け、「そういうときに緊張しちゃうんだね。でも大丈夫、一緒に少しずつ慣れていこうね」と受け止めてあげてください。否定せず受容された安心感が前向きな意識へ繋がり、克服への第一歩となります。
学校との連携も重要
次に、学校ともしっかり連携しましょう。担任の先生にはお子さんの性格傾向を伝え、クラス内での様子を定期的に共有してもらいます。先生が理解してくれれば、例えば、発表の機会があっても急に指名するのではなく事前に準備させてあげる、発表の補助をしてもらうことができます。また、グループ活動では相性の良い友達と組ませる、仲間外れにならないよう日々子どもたちに声掛け(もちろん本人が人見知りであることを周知するのではなく、道徳心として呼びかける)といった配慮が期待できます。親も授業参観や面談でお子さんの努力している点を先生から聞き出し、家庭でたくさん褒めてあげてください。それにより子どもは「自分もちゃんと見てもらえている、評価されている」と感じ、自信につながります。
自己表現の練習
家庭内で、自分の意見を言う練習をさせましょう。夕食時に「今日あったこと」を話してもらいながら、最終的には「いいこと」「悪いこと」それぞれを話す(表現する)機会を増やしていきます。一家で順番にスピーチごっこをするなど、遊び感覚で人前で話すトレーニングをします。慣れてくると言葉に自信がつき、教室でも発言しやすくなります。
興味のある活動に参加してみる
お子さんの興味・関心に合った習い事やクラブ活動、集まり等に参加させるのも有効です。好きなことならば自分から話せるきっかけが生まれ、似た趣味の友達とも交流しやすくなります。例えば、絵が好きなら絵画教室、科学好きなら科学クラブ、ゲームやアニメが好きなら好きなアニメの展示会やファンイベントなど、「好き」を通じて社交性を伸ばしましょう。
本人のペースを尊重しつつ、親がサポート
社交的な両親や兄弟姉妹と比べて「この子はどうしてできないの」と思うかもしれませんが、決して比較せず、その子なりのペースを尊重してください。発表が苦手なら事前に家でのリハーサルに付き合い、小さな成功体験を積ませます。無理強いせず見守る姿勢が、子どもの安心感につながることを忘れないでください。友人関係では「無理にみんなと仲良くなる必要はない」「気の合う友達が一人いれば素晴らしいこと」と伝えましょう。実際、内気な子は少人数の深い関係を好む傾向があり、それは健全な付き合い方です。親は放課後に仲の良い友達を家に招いて遊ぶ機会を作ったり、流行に合わせたオモチャや文房具を与えてクラスメイトと交流する機会を提供したりするとよいでしょう。
必要に応じ専門家へ相談も
この時期でも極度の人見知りが見られる場合には、専門家への相談も検討しましょう。特に「学校に行きたくない」「お腹が痛いから学校に行かない」と言って登校を渋るといった状況が続く場合、子どもの不安が限界に達しているサインかもしれません。スクールカウンセラーや小児精神科では、認知行動療法という技法を使って子どもの不安に対処する練習を行ったり、必要に応じてお薬の助けを借りたりすることもできます。社交不安障害(社会不安症)は思春期前後に発症することが多く、早めに適切なサポートを受けることで学校生活への適応がぐっと楽になります。
思春期(12〜18歳): 思春期の社交不安とその対策
思春期特有の「人と関わらない」なのか「人見知り」なのか
思春期になると、子どもは急激な身体的変化や自己意識の芽生えによって、人からどう見られているかを強く意識し始めます。そのため、それまで人見知りでなかった子でも中学生くらいから急に無口になったり、新しい人間関係を避けようとすることがあります。これは思春期特有の自己防衛であり、ある程度は誰にでも見られる変化で温かく見守れば問題はありません。しかし、中には人間関係を避ける原因が強い緊張や不安であり、「人前に出るのが怖い」「友達でも自分から誘うことができない」といった状態に陥る場合があります。この場合は「人見知り」として人との関りを避けようとしているため本人が困っていれば改善を図ってあげることが大切です。
思春期では「不安障害」として診断されることも
思春期の強い人見知りは、しばしば社交不安障害(社交不安症、かつては対人恐怖とも)と呼ばれる不安障害の範疇になります。社交不安障害では「人から批判的に見られるのでは」「相手から良く思われないんじゃないか」という強い恐怖から、初対面の人と話すことや学校で発表することを極度に避けてしまいます。症状は女性に多く、思春期から青年期にかけて発症することが多い疾患です。放置すると学校生活や対人関係に支障をきたし、将来的にも交友や就職に困難を抱える恐れがあります。幸いにもこの社交不安障害は適切な治療で改善が可能です。認知行動療法(CBT)などの心理療法や、場合によっては抗不安薬・抗うつ薬の助けを借りながら、不安に対処するスキルを身につけることで時間はかかっても克服できる場合が多いため、心配なときには治療をしてみてください。親御さんとしては、思春期の子どもが「人前が苦手」「友達ができない」と悩んでいるとき、まずは否定せずに受け止めてあげてください。「何恥ずかしがってるの!」と叱っても逆効果です。代わりに、「そういう悩みは誰にでもあるものだよ。ゆっくり慣れていけば大丈夫。何か対策をしてみる?」と声をかけ、必要ならカウンセラーや精神科医など専門家の力を借りることも選択肢だと伝えましょう。子ども自身が「自分だけがおかしいんじゃない」と知り、支援を受けることを恥ずかしいと思わなくなることが大切です。
子どもの自己理解を助け、対処法を考える
思春期の子は、自分の性格に悩みがちで、この時期に「考え方の癖」も付きがちです。「自分はダメだ」「何もできない」と繰り返し思い込まないよう、「人見知りな部分も含めてあなたの個性だよ」と自己理解を促します。長所と結びつけて、「人間関係に慎重だからこそ相手を思いやれる思慮深さや優しさがあるんじゃないかな」といったポジティブな捉え方を教えましょう。思春期の子にはリラクゼーションや呼吸法を教えるのもよいでしょう。緊張した場面で腹式呼吸をする、リラックスできる好きな音楽を聴いて心を落ち着かせる、といったスキルは不安対処に有効です。対処方法を知っているだけで「心の余裕」が生まれます。
専門家や第三者の力を借りる
親には話せない悩みも、カウンセラーや信頼できる教師・友人になら話せることがあります。学校のスクールカウンセラー利用や、必要に応じ精神科の受診も前向きに検討しましょう。専門家は客観的な視点で助言してくれたり、認知行動療法など科学的根拠に基づく手法で不安の克服を手伝ってくれます。「話すことで状況の整理ができてすっきりする」ということは思春期の子にも当てはまります。実際、精神科に通院している思春期の患者さんも「話すだけ」の診察で処方などはなくても「話せてよかったです」とすっきりして帰っていきます。
成功体験を積ませる
社交不安の強い子でも、興味のある分野では大胆になれることがあります。例えば、趣味の合うオンラインコミュニティは発言できる、好きな分野の発表なら饒舌に話せるなど、得意分野で成功体験を積ませる工夫をします。最初は心臓がドキドキして冷や汗をかいていた、逃げ出してしまったとしても、何度か繰り返すうちに「案外なんとかなるかも」という感覚が芽生えてきます。その成功を他の場面にも一般化できるよう、「できたね~!自信を持っていいんじゃないかな」と「できている」ことを繰り返し伝えます。
将来的な視点を共有する
中高生には、「今の時期に人前で緊張するのは普通のこと。今経験を積んでおけば将来必ず役に立つ」と優しく伝えることも必要です。大学生活や社会に出てから、人と関わる練習をしておくことの大切さを話し、本人のモチベーションを引き出します。ただし、決して「このまま人前で話せなくても知らないからね」といった脅す口調や「将来発表できなかったら恥ずかしいよ?」などのマイナスな点を伝えるのではなく、「夢を叶えるためにも、一緒に少しずつ練習しよう」「大学生活や仕事が楽しくなるように今から練習してみない?」という励ましの姿勢で伝えましょう。また、目標となる人物や仕事があると具体的なモデルになります。好きなアイドルや俳優でも構いません。堂々とした姿勢や態度の人でもいいですし、デビューしたての頃にはオドオドしていたけれどもどんどん場慣れしていった人はより目標にしやすいでしょう。さらに、親自身がお手本になることも効果的です。例えば、人前で挨拶する場や発表の場に子どもを同席させ、「お父さんも緊張したけど、やってみると意外と平気だったよ」と伝えることで、ロールモデルとなります。
おわりに: 個性を尊重しながら社会性を伸ばす
子どもの「人見知り」は、成長の中で誰もが通る道です。精神科医の視点から見ると、それは一概に悪いものではなく、子どもが自分のペースで世界に適応しようとするプロセスと捉えられます。このプロセスに時間がかかる子もいれば、途中で大きな「壁」にぶつかって足踏みしてしまう子もいます。大切なのは、親がそのプロセスに寄り添い、必要な助け舟を出しつつ、子どもの個性を尊重してあげることです。
人見知りしやすい子も、安心できる環境と適切なサポートがあれば、少しずつ集団生活に慣れ、友人関係を築き、自分の能力や個性を発揮できるようになります。その過程で時には専門家の力を借りることも恥ずかしいことではありません。最新の研究やガイドラインも、子どもの不安には早めの対応と周囲の理解が有効だと示しています。
最後に、親御さん自身もあまり心配しすぎず、お子さんのペースを信じてあげてください。内気だと思っていた子がある日、友達と笑い合っていたり、立派に発表をしていたりする姿を見るのは、親にとって何より嬉しい瞬間と言えます。その日を迎えるまで、程よいサポートで暖かく見守っていきましょう。
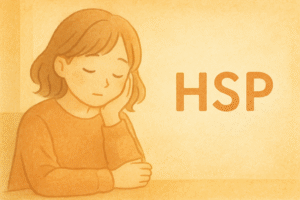
参考文献・情報源
日本小児精神神経学会「子どもの人見知りと社会性の発達」
厚生労働省「子どもの発達と社会性に関するガイドライン」
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Anxiety Disorders.
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)
National Institute of Mental Health. Social Anxiety Disorder: More Than Just Shyness.
日本発達心理学会編『発達心理学ハンドブック』
橋本和明ほか編『小児精神医学の基礎と臨床』
齊藤万比古編『子どものこころの診療ハンドブック』
日本小児科学会「発達障害の子どもの行動と対処」
東京大学学生相談所「対人不安ワークショップ資料」
児童青年精神医学とその近接領域(学術雑誌 各号)
World Health Organization. International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11).
佐々木正美『子どもの心の育て方』
公益社団法人日本小児保健協会「子どもの社会性と育ち」
文部科学省「児童生徒のメンタルヘルスと学校教育」
厚生労働省「子どもの心の診療ネットワーク」
日本臨床発達心理士会「保護者のための子ども相談」
大阪大学大学院人間科学研究科「子どもの社会不安に関する研究」