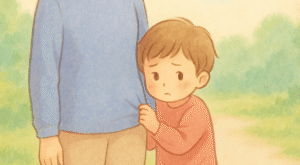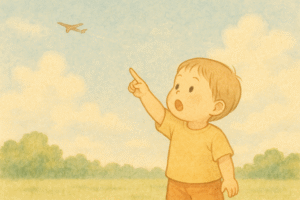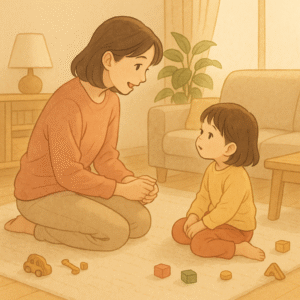はじめに
こんにちは、Dr.流星です。今回は少しフランクな内容です。気軽に読んでくださいね。
小学生から高校生まで、男の子が好きな女の子に意地悪をしたり、からかったり、ついちょっかいを出してしまう姿は多くのご家庭や学校で見られます。
「なんで相手が嫌がることをするの?」――これは多くの保護者や教師が一度は疑問に感じる“子どもの不思議”のひとつでしょう。
本記事では、精神科医の立場から、発達心理学や神経科学の知見をもとに、その理由と発達段階ごとの特徴、そして大人がどう見守り・サポートすればよいのかを整理して解説します。
「好きなのに意地悪」の根本メカニズム
1. 反動形成――「好き」の裏返し
最初に知っておきたいのは、「本当は好きなのに、あえて逆の行動に出てしまう」という“反動形成”と呼ばれる心理現象で、防衛機制の一つです。子どもは自分の「好き」という気持ちをどう扱っていいかわからないとき、またはそれを他人に知られたくないとき、あえてその気持ちとは逆の行動――たとえば相手に対して冷たくしたり、からかったり――をしてしまうことがあります。これはフロイトが提唱した発達心理学で古くから知られているメカニズムであり、特に思春期以降、プライドや恥じらいの感情が強くなることでより顕著になります。要するに「好きなのに素直に表現できない」不器用さが、時に“ちょっかい”や“意地悪”として現れるのです。
2. 注目を集めたい・関わりたいという承認欲求
加えて、「注目されたい」「自分の存在を知ってほしい」という子ども特有の強い承認欲求も、この行動の根底にあります。ポジティブな形で注目される術をまだ十分に持たない子どもは、「無視されるくらいなら怒られてでも構ってもらいたい」と感じ、あえて相手の反応を引き出す行動に出ます。これは親にも友達に対しても認められる行動であり、子どもにとって、たとえ相手が怒ったり嫌がったりしても、それが「自分の存在に気づいてくれた」という安心や満足につながることも少なくありません。こうした未熟なコミュニケーションが、「好きな子を困らせる」「からかう」といった形で現れやすいのです。
3. 衝動性と共感性の未熟さ
さらに、脳の発達段階に着目すると、子どもの衝動性や共感性の未熟さも関係します。衝動のコントロールや、他者の立場で考える力(共感性)は、脳の前頭前野という部分が担当していますが、この部位の成熟は20歳後半ごろまで続くといわれています。特に男の子は女の子よりも衝動性が高い傾向があり、「やりたい」と感じたことを即座に行動に移してしまう傾向が強く、また「自分が楽しい=相手も楽しい」と誤って考えがちです。そのため、「自分のからかいが相手にとって本当にどう受け止められているか」まで想像できず、結果として故意ではなくとも相手を困らせたり傷つけたりしてしまうケースが多いのです。
4. からかいといじめ――その境界
「からかい」は、子ども同士のコミュニケーションの一形態であり、関係性を深めたり、親しみを伝えたりする場合もありますが、相手が明らかに嫌がっている・傷ついている時点で、それは“いじめ”となります。本人が“冗談”や“遊び”のつもりでも、相手がそう受け取れなければ、それは単なる加害です。この「からかい」と「いじめ」の線引きを理解できないことも、発達段階における未熟さの現れと言えるでしょう。そういった場合にはしっかりと大人が介入して解決する必要がありますが、大人も「子どもがやったことだから……」と軽視してしまう場合も少なくありません。被害者側の心のケアも含めてしっかり対応しましょう。
大人にできるサポートと介入
1. 気持ちの背景を読み取る
「なんでそんなことするの?」「ダメでしょう!」と頭ごなしに叱るのではなく、「本当はどうしたかったの?」「○○ちゃんと仲良くしたかったんだよね?」「どんな気持ちでいじわるしちゃったのかな?」と問いかけてみることで、子ども自身も自分の気持ちに気づけるように促します。子どもが「本当は一緒に遊びたくて意地悪しちゃった」「○○ちゃんが好きだから……」と言えた場合には、「そう思うこと自体は悪いことじゃないよ。でも、お友達はいじわるされてどう思ったと思う?嫌だったんじゃないかな」と、感情を認めつつ、相手の立場に立つ視点を養えるよう働きかけましょう。
2. 間違いははっきりと正す
好意の存在自体は尊重しつつも、「いじわるやちょっかいは基本的に相手を悲しませる行動である」「からかいやいじめは人を傷つけること」としっかり伝え、「どうしたら気持ちも伝えられて、相手も嬉しい気持ちになるかな?」と建設的な行動に導くことが重要です。もちろん、相手の子も楽しんでいたり、ちょっかいをかけられて嬉しそうな場合は例外ですが、多くのケースでは一方的にいじわるをしてしまっているため、同じような言動が続くと嫌われてしまうことも少なくありません。そうなると子ども自身も傷つく経験となり、場合によってはコミュニケーションに苦手意識をもってしまうこともあります。
3. 具体的な“伝え方”や“仲良くなる方法”を教える
「禁止」と言われただけでは子どもはどうしていいのか分からず、結局同じことを繰り返してしまうでしょう。そこで、大人が具体的な言い方を提示してあげることが大切です。これは子どもがいじわるをしてしまった場合だけでなく、日常の会話の中で示し続けることが理想です。例えば、「一緒に遊ぼうって誘ってみようか」「お友達のいいところを見つけて伝えてみよう。例えば、この絵すごく色がきれいだよね」「今度会ったときに元気に挨拶してみよう」「この前いじわるしちゃってごめんねって自分で伝えてみようか」など、ポジティブな関わり方のモデルや代替行動を具体的に提案します。
4. 「からかい」と「いじめ」の境界を明確に教える
「お友達が嫌がってたり、泣いちゃったりした時は、それは冗談じゃなくなるんだよ」「困った顔をしていたら、すぐにやめて謝るようにしてね」というシンプルなルールを日頃から伝え、相手の表情や反応を観察する力を育てていきましょう。実際にそういったトラブルが起きてしまったときには厳として、よりはっきりと叱ることが肝要です。特に加害者側の親が「子どもがしたことだから……」と曖昧な対応をしていると、今度は加害者である子どもが無視されるようになってしまうなど子ども自身の不利益につながる可能性もあります。
5. 必要な時は毅然と介入する
もし、しつこいちょっかいが続き、相手が明らかに苦痛を感じている場面に遭遇した際には、大人が毅然とした態度で介入し、両者を守る姿勢が必要です。「好きなら仕方ない」「子どもがしたこと」と見過ごすことなく、本人にも被害を受けている側にも寄り添う対応が大切です。被害者側には優しくフォローをして、加害者側には毅然とした態度で注意をします。
6. 良いロールモデルを示す
難しいことではありますが、大人自身が家庭や学校で互いを尊重し、思いやりのあるコミュニケーションをしている様子を子どもたちに「見せておく」ことが一番重要です。やはり子どもたちは大人の言動をよく見ています。いい行動も悪い行動も「見て学ぶ」のです。それが親ならなおさら影響力は強いと言えるでしょう。大人が日常的に良いロールモデル(お手本)となることで、子どもたちは自然と「好きな人には優しくする」ことを学びます。良い関わりを見せることが、最も大きな教育効果を持つと言えるでしょう。
おわりに
男の子が好きな女の子にちょっかいを出してしまうのは、発達段階上ある程度自然な現象であり、そこには未熟な感情表現・自己主張・社会的スキルの学習過程が含まれています。
とはいえ、「好きならいじわるも仕方ない」と放任するのではなく、大人が気持ちの背景を理解しつつ、適切な表現や関わり方を根気よく教えることが極めて重要です。
子どもは失敗と指導を繰り返しながら「好きな人にはどう接するのがよいのか」を学びます。保護者や教師がその“成長の伴走者”となり、お手本となり、正しい社会性を育てるサポートを続けていくことが、健全な人間関係の基礎づくりにつながります。
愛情表現も、社会性も、一朝一夕には身につきません。さらに、日頃から”完璧なお手本”を示すことはまず無理な話です。ですが、「どうしたら相手も自分も嬉しくなれるか」を大人も子どもも日々考えて行動し続けることこそが、子どもたちの豊かな心の成長を支える最大の力となるのです。
参考文献・情報源
米国小児科学会(AAP) HealthyChildren.org「Your Child’s First Crush」
日本小児精神神経学会 発達・行動に関するガイドライン
Journal of Adolescent Health(青年期の発達と対人関係に関するレビュー論文)
Psychological Bulletin(発達心理学・防衛機制に関する総説論文)
米国心理学会(APA)公式サイト・監修記事
Canadian Psychological Association(カナダ公認心理士協会)「Childhood Peer Relationships」
Verywell Mind(心理学専門家監修コラム)
Journal of Child Psychology and Psychiatry(児童期・思春期の共感性や社会的行動に関する論文)
学校臨床心理学・教育心理学分野の学術書・ガイドライン
その他、国際的な心理学・発達科学ジャーナルの最新研究レビュー