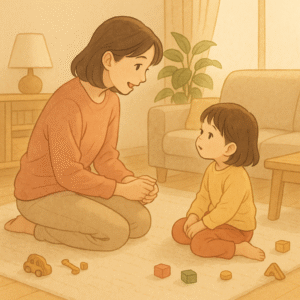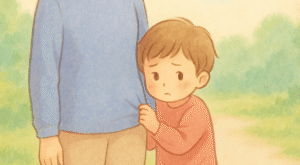こんにちは、Dr.流星です。
幼児期(0〜6歳)は、子どもが言葉以外の仕草や非言語的なコミュニケーションを通じて多くのことを伝える大切な時期です。まだ言葉が十分に発達していないこの時期の子どもたちは、視線、ジェスチャー、身体の動き、表情などで気持ちや欲求を表現しています。これらのサインには、発達の進み具合や心理状態が如実に反映されており、時に発達障害(医学的には神経発達症と言いますが、記事内では「発達障害」としています)や愛着形成の状態を示す重要な手がかりとなります。
本記事では、幼児期の子どもが見せる非言語的なサインを「一般的な発達」「発達障害の早期兆候」「愛着形成」「言語発達」といった観点から解説し、親子の健やかなコミュニケーションに役立つ情報をお伝えします。
一般的な発達:幼児期の非言語コミュニケーションの段階
まず、乳幼児が年齢とともに見せる典型的な非言語コミュニケーションの発達を押さえておきましょう。子どもは成長に伴い、徐々に複雑なジェスチャーや視線の使い方を身につけていきます。以下に年齢ごとの主な仕草の例を示します。
0〜1歳(乳児期)
生後1〜2か月頃には人の顔をじっと見つめ、声をかけられると笑顔を見せ始めます。生後6か月頃までに「あやされると笑う」「大人の表情をまねて喜ぶ」など簡単なやりとりが可能になり、笑い声を立てたり喜怒哀楽の表情を示したりするようになります。7〜9か月頃になると「いないいないばあ」や「ちょうだい・どうぞ」の遊びを通じて手を叩いたり顔を隠したりといった模倣的な身振りを楽しみます。また、バイバイと手を振る動作も徐々に見られ、生後12か月頃までには大人に対して手を振って別れのあいさつができる子が多いでしょう。この時期には簡単な指差しも始まり、欲しい物があると指差しや手を伸ばして要求を伝えます。
1〜3歳(幼児期前半)
歩行が安定する1歳半頃になると、子どもの探索意欲が高まり、周囲の物や出来事への関心を大人と共有しようとする行動が現れます。例えば、興味のあるものを指差して「見て!」と大人に知らせる(指差しによる共有)ことが増えてきます。実際、1歳6か月頃までに自分の興味を大人に伝える指差し(発達学では「叙述の指差し」や「共感の指差し」と呼ばれます)が見られるようになることは、健常な社会性発達の重要な指標です。同じ頃、子どもは自分で少し離れて遊んでは振り返り、保護者が近くにいるか確認するようになります。これは愛着対象である親を「安全基地」として、安心を確かめながら探索を広げている行動です(後述する「愛着形成」の項で詳述)。2歳頃になると指差しのバリエーションも増え、絵本の絵を指して大人に物や生き物の名前を尋ねたり、指差しで簡単な意思表示をしたりします。また、「バイバイ」以外のジェスチャー(例:投げキッスやうなずき)も使うようになり、状況に応じて首を横に振って「嫌」を示す、両手を広げて「だっこ」をせがむ等、多彩な身振りで気持ちを表現します。さらに、この頃の子どもは周囲の大人の表情にも敏感になり、新しい場面では保護者の顔色をうかがって良いことかどうか判断する(社会的参照)行動も見られます。例えば、知らない人に会ったときに母親の表情を見て安心していい人物か確かめる、といった仕草です。
3〜6歳(幼児期後半)
3歳になる頃には、子どもは他の子どもにも関心を持ち、友達の遊びに加わったり一緒に遊ぼうと誘ったりするようになります。この時期はごっこ遊びが盛んになり、3〜4歳では「お医者さんごっこ」「お店屋さんごっこ」など、見立て遊び・ごっこ遊びの中で役になりきることで、言葉だけでなく身振りや表情を駆使して想像の世界を表現します。例えば、「先生役」になった子どもが腕組みをしてうなずきながら「次の方どうぞ」と言う、といった具合に大人のしぐさを真似ることもあります。また、4〜5歳になると他者への思いやりがさらに発達し、友達が泣いていると心配そうな表情をしたり肩に手を置いたりする姿も増えてきます。「〇〇ちゃんが転んで痛がっているから、優しくトントンした」といったエピソードも珍しくありません。5歳頃までには、人前で歌ったり踊ったりといった自己表現も積極的になり、保護者に「見てて!」と言ってダンスやお芝居を披露する子も多いでしょう。これは創造力と自信の表れであり、同時に他者に喜んでもらいたいという社会性の発達も示しています。
生後9か月の赤ちゃんが「いないいないばあ」で大笑いするのは、人の動作や表情を手がかりに「見えないものがまた現れる」ことを理解しつつ(認知発達の表れ)、大好きな大人とのやりとりを楽しんでいるからです。また、1歳半の子どもが遠くの犬を指差し、「わんわん!」と大人の方を見る場合、それは「見て、犬がいるよ!」と共有したい気持ちの現れです。大人がそれに気づき「本当だ、わんわんがいるね!」と応じれば、子どもは満足げに笑顔を見せます。この一連のやりとりには、子どもの好奇心(探索行動)と大人と喜びを共有したい思い(共同注意)が表れており、健全な社会的コミュニケーションの発達段階にあることがわかります。一方で、人見知りをしながらも保護者にしがみついて安心し、落ち着くと再び遊びに戻る姿には、愛着形成による情緒の安定がうかがえます。
発達障害の早期兆候:非言語コミュニケーションの異常
次に、仕草や非言語的サインの観察から早期に読み取れる発達障害(とくに自閉スペクトラム症〈ASD〉など)の兆候について解説します。乳幼児期のASDでは対人コミュニケーションの質的な偏りがしばしば見られ、年齢相応であれば見られるはずのジェスチャーや視線の応答が欠如または異常であることがあります。米国疾病予防管理センター(CDC)は、以下のような行動が見られない場合には自閉スペクトラム症を含む発達上の問題を疑うサインになり得ると示しています。該当する月齢になっても当てはまる行動が見られない場合は専門家に相談するとよいでしょう。あくまで一例なので、同じようなサインには注意を払いましょう。
生後9か月まで
人の目を見つめない、またはアイコンタクトを避ける。名前を呼ばえても反応しない。喜怒哀楽の表情をあまり示さない(例えば、笑いかけても笑い返さない)。
生後12か月まで
「いないいないばあ」など簡単なやりとり遊びをしない。指差しやバイバイといった基本的なジェスチャーをほとんど使わない。
生後15か月まで
興味のあるものを指差して大人に見せたり共有しようとしない(例えばお気に入りのおもちゃを持ってきて見せる等がない)。
生後18か月まで
何か面白いものを見つけても指差して他者に知らせない(共感の指差しが見られない)。
2歳まで
他人が悲しんだり痛がったりしていてもほとんど気づかない(共感的な反応の欠如)。
3歳まで
周囲の子どもに関心を示さず、いっしょに遊ぼうとしない。
4歳まで
ごっこ遊びで見立てや役になりきる遊びをしない(例:おもちゃの電話で話すふりをする、ヒーローになりきる、などが見られない)。
5歳まで
歌ったり踊ったり「見て見て!」と人前で何かを披露するような仕草が全くない。
上記のようなサインのいくつかが組み合わさって見られる場合、専門機関での評価を検討しましょう。例えば、「1歳を過ぎても指差しやバイバイが出ない」「2歳近くになっても他人への関心が希薄で共遊びしない」といった場合、自閉スペクトラム症(ASD)の初期兆候の可能性があります。実際、生後1歳半健診で指差しの有無を確認することは、自閉スペクトラム症の早期発見において重要視されています。指差しで答えられなかったり指示が通らなかったりする場合、専門家は聴覚障害や知的発達の遅れ、コミュニケーション発達の遅れ、さらには養育環境上の問題など様々な要因を考慮に入れて評価します。特に、応答的な指差し(大人から「〇〇はどこ?」と聞かれて指差しで答える能力)が18か月(1歳半)を過ぎても全く見られない場合には注意が必要です。もちろん、これらの兆候は素人判断が難しい場合もありますし、全てが揃わないと診断されないというものでもありません。気になる点があれば早めに小児科医や専門の相談機関に相談し、必要に応じて発達検査や支援につなげることが大切です。
1歳の誕生日を迎えたばかりのAくんは、まだ人差し指で物を指すことをしません。欲しいものがあっても大人の手を自分の手で引っ張るだけで、指差して伝えることがありません。また、家族が手を振って「バイバイ」と言っても、Aくんは手を振り返さず無表情なままです。このような場合、単に恥ずかしがり屋という可能性もありますが、同年齢の多くの子が身につけている非言語コミュニケーションが見られない点で気がかりです。発達専門クリニックではまず聴力検査等で耳が聞こえているかを確認し、それに問題がなければ発達の遅れや偏りを注意深く評価します。実際に自閉スペクトラム症(ASD)などであった場合、その後の言語や社会性の発達を伸ばす支援に繋がるため、早期から適切な療育を開始することが重要になります。
愛着形成:仕草に表れる親子の絆
愛着(アタッチメント)とは、乳幼児が特定の養育者とのあいだに形成する情緒的な絆のことです。幼児期の仕草や非言語的コミュニケーションには、この愛着の状態が反映されることがあります。愛着が安定している子どもは養育者に対して安心感と信頼感を抱いており、そのことは行動の端々(視線の送り方や身体接触の求め方)によく表れます。一方、愛着が不安定な場合や形成に問題がある場合、子どもの示すサインにも特徴的なズレが生じることがあります。
安定した愛着(安全基地行動)
乳児は生後半年を過ぎる頃から人見知りを始め、自分と他人をはっきり区別し始めます。この頃から、特定の養育者(多くは母親など主要な保護者)に対して強い情緒的な結びつきを示すようになります。例えば、知らない人に抱かれると泣いてしまうが、親に抱っこされると泣き止むという反応は愛着の形成が進んでいる証拠です。また、ハイハイやあんよができるようになると、子どもは探索範囲を広げますが、途中で振り返って親が自分を見守っているか確認したり、不安になると親の元に戻ってきて安心を得たりします。この一連の行動は発達心理学で「安全基地行動」と呼ばれ、親を安全基地として信頼しつつ、自立した行動(探索)との両立を図っている状態です。十分に安心感を与えられた子どもは、しばしば転んだ時や怖い思いをした時に両手を広げて保護者に助けを求め、抱き上げられるとすぐに落ち着いて再び遊びに戻るといった行動を示します。このように親の存在を「拠り所」にする健全な愛着が育まれている場合、子どもの非言語コミュニケーションには以下のような特徴が現れます。
視線
不安な時や新しい環境で親の顔をよく見て確認します。一方で安心して遊んでいる時には時折振り返って親と笑顔を交わし、「ちゃんと見守ってくれているかな?」と視線で対話します。
身体接触
疲れた時や怖い時には自分から抱っこを求め、しがみついたり頭を胸にうずめたりします。十分に甘えて心が落ち着くと、自分からまた遊びに離れていくことができます。
表情・しぐさ
親が部屋に戻ってくるとパッと笑顔になったり、手をバタバタさせて喜びを表現します。逆に親と離れると悲しそうな顔をしたり泣いたりするのは、愛着があるからこその自然な反応です。
このような安定した愛着を背景にした子どもの仕草は、子どもの情緒面の健全さを示す重要なサインです。ボウルビィの愛着理論によれば、乳児期に養育者から十分な安心感と応答を得られることで、子どもは「自分は愛されていて大丈夫なんだ」という基本的信頼感を獲得するとされています。「愛」を言葉ではなく、行動で示してあげることがこの時期には重要なのです。実際、生後1年頃までの乳児は抱っこやスキンシップが大好きで、「かまってほしい」「安心させてほしい」という欲求を全身で示しますが、これに応えてもらえることで情緒が安定し、他者への信頼感が育まれていきます。
2歳のBちゃんは、公園で遊んでいて転んで膝をすりむいてしまいました。Bちゃんは驚いて一瞬泣き顔になりましたが、すぐに立ち上がって「ママ!」と泣きながら駆け寄り、両腕を広げて抱っこを求めました。お母さんが「痛かったね」と抱きしめてあげると、Bちゃんはしばらく涙を流しましたが、次第に落ち着きを取り戻しました。そして膝に絆創膏を貼ってもらうと、自分からまた遊具の方へと歩き出しました。このBちゃんの行動には、痛いときにママに助けを求めれば安心できるという信頼が表れています。抱きしめられて心が落ち着いたことで、遊びに向かう意欲が回復したのです。Bちゃんのように不安時に保護者へサインを送り、適切な慰めで回復するパターンは、愛着がしっかり形成された子どもに典型的な姿と言えるでしょう。
不安定な愛着とそのサイン
一方で、様々な理由から愛着が不安定になっている場合、子どもの非言語的な反応にもいくつかの特徴が見られます。不安定型愛着にはいくつかタイプがありますが、例えば、回避型愛着の子どもは親との分離にあまり泣いたりせず平然として見える反面、内心ではストレスホルモンが上昇しているという研究報告があります。しかし、見た目には親が戻ってきても目を合わせず、甘える素振りも少ないなど、あたかも「興味がない」かのような仕草をとることがあります。これは、繰り返しの経験から「泣いてもどうせあまり反応してもらえない」と学習してしまった可能性も指摘されています。逆にアンビバレント(抵抗)型愛着の子どもは、分離不安が強く親と離れる時に激しく泣きますが、再会時にも怒ったように叩いたり抱っこを拒んだりして、なかなか落ち着かないという矛盾した行動を示すことがあります。これは日頃の養育者の応答が一貫していないため、子どもが不安と甘えたい気持ちの間で葛藤している表れと理解されます。また、稀ですが無秩序(混乱)型愛着では、養育者に向かって行こうとした途中でフリーズして固まる、一瞬近づいたのにまた急に離れる、といった分裂した奇異な行動が見られることもあります。これは主に虐待や極度のネグレクト(養育放棄)など、子どもにとって本来安心できるはずの養育者が恐怖の対象にもなっている状況で起こりやすいとされます。
極端な養育環境の問題によって適切な愛着が形成されない場合、医学的には愛着障害と診断されることがあります。愛着障害には大きく分けて、養育者に対してほとんど情緒的な応答を示さず他人にも関心を向けない「反応性愛着障害」と、見境なく誰にでも愛想よく振る舞い他人にすぐついて行こうとする「脱抑制型対人交流障害」とがあり、いずれも幼少期の深刻な養育環境不良が原因と考えられます。愛着障害は、幼児期に施設で育った子どもや、虐待を受けた子どもに見られることがあり、DSM-5(精神疾患の診断基準)にも正式に記載されています。このような場合、子どもの非言語コミュニケーションは年齢相応とは大きく異なり、表情が乏しい、抱き上げても身体の緊張が強かったり逆にぐったりしたりする、他人でも誰にでもしがみつく、といった特徴がみられることがあります。専門家による早期介入とケアが重要ですが、これは特殊なケースがほとんどであり、大部分のご家庭では日々の関わりの中で十分な愛情と安心感が育まれていることでしょう。
3歳のCくんは保育園で転んで膝を擦りむきました。しかし、Cくんは泣かずに立ち上がり、保育士の方を見ることもなく一人で遊び続けようとしました。保育士が近づいて「大丈夫?痛かったね」と声をかけても、Cくんは視線をそらして「大丈夫」と小さな声で答えるだけで、涙も見せません。この様子を聞いたお母さんは「家でもあまり甘えてこない子で…」と心配そうです。Cくんの場合、痛みや不安を感じても大人に助けを求めるというサインを出していない点が気がかりです。家庭環境を詳しく伺うと、両親とも多忙で関わる時間が少なく、泣いたときに十分あやしてもらえない経験が重なったのかもしれません。このケースでは専門家のアドバイスのもと、お母さんに意識的にスキンシップや共感的な声かけを増やしてもらう対応をしました。すると数か月後、Cくんは転んだとき以前よりも「痛い」と訴えて泣くようになり、抱きしめると落ち着くようになりました。これは大人から見ると手がかかる、煩わしさに繋がっているように思えますが、適切に甘えられる健全な愛着が形成されつつある兆しと捉えられます。
言語発達との関連性:ジェスチャーと言葉の相乗効果
最後に、幼児のジェスチャーや非言語コミュニケーションと言語発達との深い関係について説明します。言葉を話し始める前の子どもにとって、ジェスチャーは重要なコミュニケーション手段です。実際、言葉の発達は非言語コミュニケーションの土台の上に築かれると考えられており、赤ちゃんはまず身振りや声の抑揚で意思を伝え、それが徐々に意味のある言葉へとつながっていきます。
ジェスチャーは「話し言葉の先駆け」
研究によれば、生後9〜16か月頃までのジェスチャーの発達は、その後2歳代の言語能力を予測する重要な指標であることがわかっています。例えば、ある追跡研究では1歳半頃までに多彩なジェスチャーを使っていた子どもは、そうでない子どもに比べて、3歳半(42か月)時点で語彙が豊富で文の構造も発達している傾向が確認されました。このようにジェスチャーの習得と音声言語の発達には密接な相関があり、ある専門家は「16か月までに最低16種類のジェスチャーを身につけていることが望ましい」とも提唱しています。ジェスチャーが順調に増えていくことは、コミュニケーション能力が年齢相応に発達しているサインであり、後の語彙獲得や文章表現力の伸長に良い影響を与えることを理解しておきましょう。
具体的に、子どもはジェスチャーと言葉を組み合わせて使うことで、より複雑な意味を伝える準備をします。例えば、指差しながら「ワンワン!」と言った場合、「そこに犬がいるよ!」という主語+述語のような二語文に相当する意味を表現しています。このようなジェスチャー+単語の組み合わせが頻繁に見られる子は、その後まもなく「ワンワン来た!」のような二語文を口にするようになることが知られています。また、親が子どもの指差しに応じて「〇〇だね」と言語化してあげることで、子どもは言葉と対象物との結びつきを学んでいきます。例えば、子どもが飛行機を指差したとき、親が「飛行機だね。ブーンだね」と応じれば、子どもはその指差しの体験と言葉を関連付け、語彙を習得していきます。この大人と子どもの共同注意(ジョイント・アテンション)の中でジェスチャーが果たす役割は極めて大きく、言語習得の基盤になるものです。
さらに、子ども自身が言葉を話し始めた後も、身振りや表情は言語を補完し、会話の質を高める役割を果たします。例えば、2歳児は「ママ、あっち!」と言いながら欲しい物のある方角を指差すことで、自分の言いたいことを明確に伝えられます。また、大人にとっても子どもの指差しや仕草を手がかりにすることで、言葉だけでは汲み取りにくい要求や感情を理解しやすくなります。実際、「コミュニケーション発達の良好な子どもほど言葉だけでなく身振りも豊かに使う」ことが報告されており、これは子どもが周囲との相互作用から多くを学び取っている証とも言えます。
ジェスチャーの遅れと言語発達
反対に、ジェスチャーの発達が遅れている場合、後の言語発達の遅れにつながる可能性があります。例えば、生後1歳を過ぎても指差しが全く出ず、意思表示が泣くことと大人の手を引っ張る動作だけに限られる子は、言語の獲得も遅れる傾向があります。これは、子どもが周囲とのコミュニケーション経験を十分に積めないことで、言葉を習得する機会が減ってしまうためと考えられます。また、自閉スペクトラム症(ASD)の場合にはジェスチャーや視線によるやりとりに乏しいため、当然ながら言語発達にも遅れが生じることが少なくありません。そのため乳幼児健診では言葉の遅れだけでなく指差し等の非言語コミュニケーションの有無がチェックポイントとなっているのです。
ただし、ジェスチャーの出現がややゆっくりでも、その後の環境次第で言語発達が追いつくケースも多くあります。大切なのは、子どもの出すサインを大人が見逃さず受け止め、言葉を添えてあげることです。例えば、子どもがコップを持って大人に差し出したら、「お茶ちょうだい、かな?」「おかわり、だね?」と代弁してあげます。子どもが指差しで示したものには、すかさず名前を教え、「○○があるね!よく見つけたね!」と共感したりすることも効果的です。このように日常生活の中で大人が適切にジェスチャーに応答して言語入力を与えることで、子どもの言語発達は大いに促されます。「話しかけてもまだわからないだろう」と思わず、たとえ言葉を話せない赤ちゃん相手でも、ジェスチャーや表情に応じてたくさん語りかけてあげてください。それが言語と非言語の架け橋となり、豊かなコミュニケーション能力へとつながっていきます。
1歳3か月のDくんはまだ意味のある言葉を話しませんが、空を指差して「うー!」と声をあげました。「何かあるのかなー?」と指差す方向を見ると、飛行機が飛んでいました。お父さんがそれに気づき「飛行機が飛んでいるね!」と反応すると、Dくんはお父さんが自分の意図を汲み取ってくれたことでにっこり笑い、さらに「ブーン!」と飛行機の音真似をしました。お父さんも「ブーンだね、飛行機だね!」と笑顔で応じます。このやり取りによって、Dくんは「指差しで自分の興味を伝え、お父さんと共有できた」という喜びを感じると同時に、「飛行機」「ブーン」という言葉も学習しています。まさにジェスチャーと言葉が連動したコミュニケーションが成立した瞬間と言えるでしょう。このように子どものジェスチャーに大人が反応し言葉を返す積み重ねが、言語発達を力強くサポートします。
おわりに
0〜6歳の幼児期における子どもの仕草や非言語コミュニケーションには、発達の節目や個々の心理状態が如実に反映されています。一般的な発達に沿ったサインを理解していれば、我が子の成長を安心して見守ることができますし、逆に「何かおかしいな」という兆候にいち早く気づくこともできます。特に指差しやアイコンタクトなどのコミュニケーション行動は発達障害の早期発見の重要な鍵となり得ます。また、子どもの甘え方や人との関わり方からは、愛着関係の深まり具合や情緒の安定度が読み取れ、適切な関わり方のヒントになります。さらに、ジェスチャーといった非言語の表現を大切に育んでいくことが、言葉の発達を促す土壌にもなるのです。
周囲の大人には、ぜひ子どもの小さなサインにも耳を傾け、それに応えてあげる姿勢を持ってほしいと思います。それは決して特別なことではなく、子どもが指を差せばその目線を追い「○○がいるね!」と反応し、泣いていれば抱きしめて「怖かったね」「ママ(パパ)がいるよ。大丈夫だよ」と声をかける、といった日常の関わりです。そうした積み重ねが健やかな発達と心の安定、そして豊かなコミュニケーション能力につながっていきます。もし発達に不安を感じることがあれば、早めに専門家に相談し、必要なサポートを受けるようにしましょう。子どもの仕草は多くのことを語っています。私たち大人がそれを読み取り、適切に応じることで、子どもの可能性を最大限に引き出してあげたいものです。
参考文献・情報源
参考文献・情報源
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
- “Developmental Milestones”
- URL: CDC Developmental Milestones
American Psychiatric Association (APA)
- “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)”
- 出版社: American Psychiatric Publishing, 2013
- ISBN: 978-0890425558
World Health Organization (WHO)
- “International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11)”
- URL: WHO ICD-11
National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)
- “Child Development and Early Learning”
- URL: NICHD Early Learning
国立成育医療研究センター
- 「子どもの発達と育ちに関するガイドライン」
- URL: 国立成育医療研究センター
厚生労働省
- 「発達障害の理解と支援」
- URL: 厚生労働省 発達障害