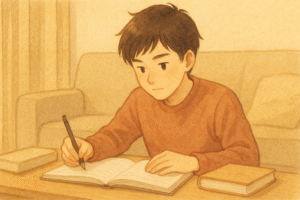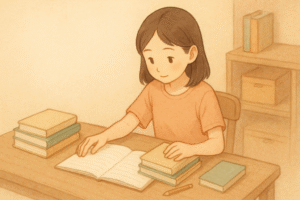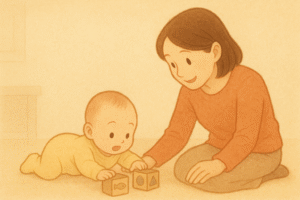こんにちは、Dr.流星です。
4歳から6歳の幼児期は、心も体も大きく成長する大切な時期。この時期にどのような習い事や体験を積ませるかは、子どもの認知能力や社会性、感情の安定に大きな影響を与えます。運動や音楽、言語活動、そして自然体験など、多彩な経験が幼児の脳を刺激し、将来の学びや人間関係の土台を作ります。
この記事では、科学的根拠に基づいて、4~6歳の子どもに適した習い事や日常で体験させておきたいこと、さらに家庭や祖父母が心がけるべきポイントについて詳しく解説します。お子さんの成長をサポートするためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
習い事と発達への影響
幼児期は「遊び」を通じて心身のバランスのとれた発達の基礎が培われる時期です。この年齢に適した習い事には、運動・音楽・言語・創造的活動などがあります。それぞれが幼児の発達に特有の効果を持つことが科学的に示唆されています。
運動系(スポーツ・体操など)
体を動かす活動は筋力や巧緻性を育てるだけでなく、認知機能の発達にも寄与します。例えば、幼児期に日常的に十分な身体活動を行っている子どもは、実行機能(ワーキングメモリや抑制力など)や言語能力の向上が見られたとの報告があります。運動能力、特に手先・指先を使う巧緻性が高い子どもほど、言語や数概念の習得、注意力など学習面で成功しやすい関連も指摘されています。つまり、遊びやスポーツを通じて体を動かすことが、脳の発達や学習準備にプラスの影響を与えると考えられます。
音楽系(楽器演奏・歌唱など)
音楽活動は情緒面の発達に良いだけでなく、認知的な能力を育む効果があります。メタ分析によれば、幼児期から楽器演奏などの音楽訓練を受けた子どもは注意力や衝動抑制(抑制制御)能力が有意に向上し、集中して課題に取り組む力が強化されることが示されています。実際、リズム遊びや音楽と動きを組み合わせたプログラムによって、幼児の自己調整力(自分の気持ちや行動をコントロールする力)や実行機能が向上し、就学準備能力が高まったとのRCT研究もあります。このように音楽に親しむことは、幼児の脳の発達を多面的に刺激し、認知・情動・運動機能のバランスの取れた向上につながります。
言語系(読み聞かせ・語学体験など)
幼児期は言葉の爆発的発達期であり、豊かな言語環境が重要です。母語については、親による絵本の読み聞かせが語彙力や記憶力の向上に直結します。週に数回以上の頻度で読み聞かせを行う家庭の子どもは、5歳までに聞く語彙数が絵本なしの場合と比べて圧倒的に多く、いわゆる「100万語のギャップ」を生むことが報告されています。実際、家庭で読み聞かせ頻度が高い子どもほど視空間的ワーキングメモリや言語的短期記憶、語彙力が有意に高いという研究もあります。一方、外国語に触れる機会も認知発達に良い影響があります。バイリンガル環境で育つ子どもは、注意力や課題の切り替え(マルチタスク)能力が単一言語の子よりも優れていることが示されており、幼児期から異なる言語の音や表現に触れることは脳の認知柔軟性を育むと考えられます。ただし、こちらも無理に早期英才教育を押し付けるのではなく、歌や遊びを通じて楽しく言語に親しむ形が望ましいでしょう。
創造的活動(お絵描き・工作・ごっこ遊びなど)
自由な創作や空想遊びは、幼児の創造力や問題解決力の基盤を育てます。ごっこ遊び(見立て遊び・空想遊び)に熱中する幼児は、感情のコントロールや社会的スキル(協同や自己主張)の発達が進み、他者の気持ちを理解する心の理論の発達も促されます。おままごとやヒーローごっこなどの創造的な遊びは発散的思考を鍛え、子どもの思考の柔軟さを高める効果があります。実際、空想遊びを積極的に行った子どもは認知的柔軟性(状況に応じて考えを切り替える力)が向上し、創造的思考力が育つことが研究で示唆されています。さらに、自由な空想遊びやドラマ遊びを取り入れたプログラムは幼児の自己抑制力や記憶、タスクへの粘り強さを伸ばす効果も報告されています。加えて、絵画やブロック、折り紙など手先を使う制作遊びは巧緻性を高め、後の学習(書字や工作の習熟)を支えるだけでなく、集中力や計画性といった非認知的能力の発達にもつながります。創造的活動全般を通じて「自分で考えて表現する力」を育むことが、幼児期の脳と人格の発達に有益と言えるでしょう。
幼児期に適した習い事
- 運動系(スポーツ、体操)
- 筋力や巧緻性の発達
- 認知機能(記憶、注意、抑制力)の向上
- 社会性や自己調整力の育成
- 音楽系(楽器演奏、歌唱)
- 言語能力や集中力の強化
- 感情表現や情緒の安定
- 記憶力や空間認識能力の向上
- 言語系(読み聞かせ、語学)
- 語彙力や読解力の発達
- 言語的短期記憶と視空間的ワーキングメモリの向上
- 認知柔軟性とマルチタスク能力の強化
- 創造的活動(お絵描き、工作、ごっこ遊び)
- 問題解決力や発散的思考の育成
- 心の理論(他者の感情理解)の発達
- 自己抑制力や記憶力の強化
体験させておきたいこととその効果
習い事に限らず、日常生活で様々な体験を積むことが幼児の全人的な発達につながります。特に重要なのは 自然体験、社会的な関わり、そして手先や体を使った多様な活動です。
自然体験
戸外での遊びや自然との触れ合いは、幼児期にぜひ経験させたいものです。緑(自然)の多い環境で遊ぶと子どもは想像力豊かな遊びを展開しやすく、協同的に遊ぶ傾向が高まることが観察されています。自然の中での遊びは創造力や問題解決能力、知的発達を育むうえで特に重要であると報告されています。また、日常的に自然に触れる環境がある子どもは注意力が高まり、認知能力が向上するという研究結果もあります。実際、定期的に屋外で自由に遊ぶ機会を持つ子どもは、他者との協調性が育ち、より健康で幸福になりやすいことが示唆されています。五感を使って自然を感じる体験は情緒の安定やストレスの軽減にもつながり、都市部の子どもでも公園の緑を見るだけで自己コントロールや落ち着きが増すという報告があります。このように「外遊び」や自然体験は幼児の心身の発達に多面的な恩恵をもたらすため、積極的に取り入れたい体験です。
社会性を養う関わり(集団遊びや友達づくり)
同年代の子ども同士で遊ぶ経験も幼児期には欠かせません。親や大人との関わりとは異なり、友達との遊びは子どもの社会的・情緒的スキルを伸ばす格好の機会となります。ルールのある遊びや協力が必要なごっこ遊びを通じて、順番を待つ、自分の欲求を調整する、相手の気持ちを推し量る…といった社会性が育まれます。実際、幼児期によく仲間と遊んだ子どもは他者の心情理解(Theory of Mind)が発達しやすく、協調性や主張性といった社会スキルも高まることが報告されています。また、友達とのごっこ遊びを豊かに経験した子は、就学後の対人関係や問題解決でも柔軟に対処できるとされます。一方で、同年代と関わる機会が少なく大人に常に依存していると、いざ集団生活に入った際に友達関係の構築に苦労する場合もあります。4~6歳は幼稚園・保育園など集団生活での学びが始まる時期ですので、可能な範囲で友達と遊ぶ場を設け、社会性やコミュニケーション能力を養うことが大切です。
手先を使う活動や生活体験
幼児は遊びを通じて生活に必要な様々な技能を身につけていきます。ブロック遊びや折り紙、簡単な料理のお手伝い、衣服の着脱練習など、手先や指先を使う活動は脳の発達にとって重要です。巧緻性(ファインモーター技能)の高まりは、後の学習準備能力(鉛筆の操作、書字、工作理解など)と関連し、幼児期の巧緻性が高いほど小学校以降の学業成績が良好である傾向も報告されています。また、パズルや積み木で遊ぶことは空間認識や問題解決力の発達に寄与し、数や形への興味を育てます。さらに、家庭の中で簡単な家事(食卓の準備や片付けなど)を経験させることも有益です。大人の真似をして役割を担う体験は責任感や自立心の芽生えにつながり、「できた!」という成功体験が自己肯定感を育みます。これら日常的な生活体験の積み重ねが、幼児の実践的な知恵と自信を養い、学習意欲にもつながっていきます。
体験させておきたいこと
- 自然体験
- 想像力と問題解決能力の向上
- 身体的・感覚的な発達
- ストレスの軽減と情緒の安定
- 社会性を養う関わり(友達との遊び)
- 協調性や自己主張力の発達
- 他者の心情理解(Theory of Mind)の向上
- 社会的スキルと共感力の強化
- 手先を使う活動や日常生活
- 巧緻性の向上(書字、工作、日常動作)
- 空間認識と問題解決力の発達
- 自立心や自己肯定感の育成
両親が日頃心がけるべきこと
幼児の発達を最大限サポートするには、両親の日頃の関わり方や家庭環境が極めて重要です。科学的エビデンスに基づき、以下のような点に留意することが望ましいとされています。全てを守る必要はありませんが、気づく点などがあれば実践してみてください。
愛情深く応答的なコミュニケーション
親からの十分な愛情と安心感は、幼児の健全な発達の土台です。敏感で反応の良い養育(Responsive Parenting)は子どもの認知的成熟に不可欠であり、乳幼児期には特に「泣いたらあやす」「発した言葉に応じて会話する」といったサーブ・アンド・リターン(やりとり)の積み重ねが脳の配線を最適化します。親が子どもの要求や感情に共感し、タイミングよく応答することで、子どもは安心して探索し学ぶことができます。また、一緒に遊ぶ時には子どものペースに合わせ、指示ばかりするのでなく自由な発想を受け止める姿勢が大切です。例えば、おままごとの役になりきって参加する、子どもの無理がある指示にも工夫して対応するなど、親がポジティブな反応を続けます。逆に「今は忙しいから無理。一人で遊んでいなさい」「そんなことできるわけないでしょう」と子ども発想に対してネガティブな反応をすることは避けます。こうした温かなコミュニケーションによって形成される安全基地(愛着関係)は、子どもの社会情緒的スキルやストレス対処能力の基盤にもなります。
読み聞かせと言葉のシャワー
前述の通り、絵本の読み聞かせは言語発達に非常に有益です。毎日決まった時間に親子で絵本を読む習慣は、子どもの語彙力を飛躍的に伸ばし、読解力や学習意欲の土台を築きます。ストーリーを共有することで親子のきずなも深まり、子どもの情緒は安定しやすくなるとの研究もあります。一般的には1~3回/日の読み聞かせを継続できれば十分であり、同じ絵本を何回読んでも構いません。理想を言えば、1日に5回以上絵本の読み聞かせをすれば、言語能力の向上や情動の安定化が図れるとの報告もありますが、子どもが嫌がってるのに「ここに座って!」と押さえつけてまで読む必要はありません。あくまで「この絵本が読みたい」と本人が思える絵本選びや読み方の工夫が重要です。絵本のレベルは今の言語レベルよりやや上(子どもにとって分からない言葉が少しある)程度が理想で、内容は絵本の文章そのままを読みます。難しい言葉は親がわかりやすく言い換えてあげたくもなりますが、分からない言葉も子どもなりに絵本の場面やお話の流れから理解していくものです。もちろん、幼い内容の絵本でも本人が気に入っているのであれば楽しく読んであげます。そして、読み聞かせ以外でも、日常会話でできるだけ豊かな語彙を使い、子どもの発言を広げるような対話を心がけましょう。「今日はどんなことをしたの?」「これは何色かな?きれいな色だね」など問いかけ、子どもが言葉で表現する機会を作ることが大切です。幼児期に浴びた言葉のシャワーが、将来のコミュニケーション能力や学力に直結することは多くの研究が支持しています。
遊びと学びのバランス
幼児期には遊びそのものが学びです。親としては早期に知的能力を伸ばそうと学習教材やドリルに頼りたくなるかもしれませんが、詰め込みよりも自発的な遊びを尊重することが重要です。ブロック遊びからお店屋さんごっこまで、遊びの中で数概念や社会ルール、創造力が育っていきます。親は必要以上に手出しせず、環境(おもちゃや素材、安全な遊び場)を整えて自由な遊びを見守りましょう。本ブログでもおすすめの知育玩具などについても別の記事でまとめられたらなと思っています。一方で、子どもが何かに熱中して「もっと知りたい」という姿勢を見せた時には、それを広げるサポートをします。例えば、昆虫に興味を持てば図鑑を一緒に読む、文字に関心を持てば絵本の指さし読みをする、歌で「あいうえお」や「ABC」を覚えていく、といったタイミングを捉えた働きかけが効果的です。これにより子どもの探究心はさらに育ち、自ら学ぶ力の芽が伸びていきます。過度な早期教育の押し付けではなく、遊びと好奇心に導かれた学びを応援する姿勢が、幼児の主体性や創造性を育てる鍵です。
規則正しい生活習慣
幼児の脳と身体の発達には、十分な睡眠・適切な栄養・安定した生活リズムが欠かせません。特に睡眠は記憶の定着や脳の発達に直結します。5~12歳の子どもを対象にしたメタ分析では、睡眠時間の長さと認知パフォーマンス(知能や注意力)には正の関連があると報告されています。幼児期でも、毎日十分な睡眠をとる子は日中の注意集中や学習意欲が高く、情緒面でも安定します。また、栄養バランスのとれた食事は脳の発達を支え、朝食をきちんと食べる子は認知テストの成績が良い傾向が知られています。逆に、朝食抜きの生活習慣は注意力低下につながるとの国内研究もあります。生活リズムを整え、決まった時間に起き寝する習慣や食事・歯磨きなどの自己管理を促すことは、幼児の自律心と健康な発達の双方に役立ちます。親自身も安定した生活リズムを示すことで、子どもに良い手本を示すことができます。子どもに生活習慣を正せと言う場合には、まず親の生活習慣を見直すことが肝要です。
メディア利用のコントロール
テレビやタブレット、スマートフォンなどスクリーンメディアとの付き合い方にも注意が必要です。幼児期の過剰なスクリーン時間は、言語発達や認知発達にマイナスの影響を及ぼす可能性が指摘されています。特に受動的になりやすいテレビ視聴は語彙やコミュニケーション発達を阻害しがちで、長時間の視聴は注意力の低下や社会的なやりとりの機会減少につながります。米国小児科学会なども5歳以下の長時間のスクリーン利用を控えるよう勧告しています。ガイドラインでは2~5歳は1日1時間未満の良質なコンテンツ視聴に留めることが推奨されています。親はテレビやデジタルゲームの視聴時間・内容を管理し、可能な限り親子の対話や体を使った遊びに時間を充てましょう。どうしても見せる場合でも一緒に見て会話する「共同視聴」を行い、受け身にさせない工夫が大切です。本ブログでも良質なコンテンツについてまとめた別の記事を掲載できたらなとは考えています。健全なメディア利用の習慣づけは、子どもの注意力・言語能力の発達を守るだけでなく、将来のデジタルとの付き合い方にも影響を与えます。
両親が心がけるべきこと
- 愛情深く応答的なコミュニケーション
- 安全基地の形成
- 語彙力とコミュニケーション能力の向上
- 読み聞かせと言葉のシャワー
- 語彙力と理解力の強化
- 親子の絆と情緒の安定
- 遊びと学びのバランス
- 創造力と好奇心の育成
- 自発的な学びと探究心の強化
- 規則正しい生活習慣
- 睡眠、食事、活動のバランス
- 自律心と集中力の育成
- メディア利用のコントロール
- 言語発達や認知能力への悪影響を防ぐ
- 親子での共同視聴と適切なコンテンツ選び
祖父母が孫と関わる際に心がけるべきこと
祖父母の存在は、孫にとって多くの愛情と学びを与えてくれる貴重なものです。一方で、祖父母の関わり方によっては幼児の発達にプラスにもマイナスにも作用し得るため、以下の点に留意すると良いでしょう。
両親を支えるサポーターであること
祖父母が育児に参加することは、両親(特に母親)の負担を軽減し、心理的なゆとりをもたらすというメリットがあります。実際、祖父母の育児関与時間が多いほど母親の主観的QOL(生活の質)が高い傾向が日中双方の調査で示されています。親のストレスが減り精神的に安定することで、子どもにもより良い関わりができるようになるため、祖父母のサポートは間接的に孫の健やかな発達に良い影響を及ぼします。したがって、まずは両親を助けるサポート役という意識を持ち、必要に応じて育児や家事を手伝うことで、家庭全体の安定に貢献すると良いでしょう。
豊かな会話と遊びで言語・社会性を促す
祖父母は豊富な人生経験と語彙を持っており、それを孫との対話に活かすことで言語発達を支援できます。祖父母と同居する子どもはコミュニケーション力や言語発達に良い効果があるというエビデンスもあります。昔話や遊び歌を聞かせたり、一緒に絵本を読んだりすることで、孫の語彙や知識は自然と広がっていきます。また、祖父母とのゆったりした対話は孫の情緒を安定させ、安心感を与えます。時間に余裕のある祖父母だからこそ、せかせかせずに孫のペースに合わせて話を聞いてあげたり、伝承遊び(お手玉や折り紙、おはじき等)を教えてあげたりすることができます。これらの関わりは、親とはまた異なる角度で孫の社会性や創造力を育む手助けとなるでしょう。
甘やかしすぎない・自立を促す
孫が可愛いあまり、つい甘やかして何でも手助けしてしまう――その気持ちは理解できますが、やりすぎは禁物です。中国の調査では、祖父母が乳幼児に必要以上に食事介助をしたり欲求を即座に満たしたりする過保護な養育が、子どもの主体性や自立心の発達を損なう可能性が指摘されています。祖父母の関与が多い子ほど、自分の思い通りにならないときに強い癇癪を起こすなど自己コントロールが弱まる傾向も報告されています。日本のケースでも「祖父母に育てられた子は三文安い(甘やかされて教育が行き届かない)」ということわざがありますが、科学的エビデンスも過度な甘やかしへの注意を促しています。孫の身の回りのことを何でも先回りしてやってあげるのではなく、見守りつつ自分でやらせてみる姿勢が大切です。困った時に手を貸すのは良いですが、基本は孫の「できた!」を増やせるようサポート役に徹しましょう。適度な挑戦と失敗の経験が、孫の自立心と問題解決力を育てます。
親の方針を尊重し一貫性を保つ
祖父母はつい自分たちの子育て経験に基づいてアドバイスしたくなるものですが、現代の育児方針や両親の考えを尊重することも重要です。祖父母と親のやり方が食い違うと、子どもが混乱したり、親子間で葛藤が生じてしまうことがあります。例えば、お菓子の食べていいと言われる量や就寝時間などで両者のルールが異なると、子どもは戸惑い、場合によっては親よりも祖父母に頼れば何でも許されると誤解してしまうかもしれません。研究でも、祖父母との同居家庭では養育方針の衝突から母親のストレスが上がりやすい傾向が指摘されています。そうした摩擦を避けるためにも、親と祖父母でルールや一貫性を共有することが大切です。何か提案や心配がある場合は、陰で勝手に子どもへ口出しするのではなく親御さんと率直に話し合いましょう。両親と祖父母との軋轢が大きくなると「もう祖父母には会わせない」などの大きなトラブルに発展する可能性さえあります。共通の理解に基づいて協力することで、孫にとっても安心できる養育環境が生まれます。
祖父母が心がけるべきこと
- 両親を支えるサポーターであること
- 育児負担の軽減と家庭の安定
- 親子のストレス軽減とQOL向上
- 豊かな会話と遊びで言語・社会性を促す
- 語彙力と情緒の安定
- 創造力と共感力の育成
- 甘やかしすぎず自立を促す
- 自立心と問題解決力の育成
- 過保護による依存を避ける
- 親の方針を尊重し一貫性を保つ
- 一貫した養育スタイルで安心感を提供
- 親子間の葛藤を減らし安定した育児環境を支援
幼児の発達・学習能力への影響まとめ
4~6歳の幼児期は、人間の基礎的な能力が飛躍的に伸びる大切な時期です。この時期にどんな経験を積み、どんな大人の関わりを受けるかが、脳の発達や非認知能力(意欲・協調性・自己制御など)に長期的な影響を与えます。運動や音楽、言語、創造的遊びといった習い事はそれぞれに発達を促す効果があり、多様な活動を通じて身体能力・認知能力・社会情動的スキルがバランス良く育まれます。また、自然体験や仲間との遊び、日常生活の練習などは教室での勉強には代えがたい実体験として、子どもの好奇心や探究心を刺激します。両親は愛情ある適切な関わりと環境整備によって子どものポテンシャルを最大限引き出すことができ、祖父母も良きサポーターとして関与することで三世代にわたる協力体制が子どもの成長を支えます。これらのエビデンスに基づく取り組みは、幼児の脳の発達を助け、将来の学習能力や人格形成に良い土壌を提供するでしょう。幼児期に培われた「心と体と知」の力こそが、生涯にわたる学びと健やかな成長の原動力になるのです。
要点まとめ
幼児期に適した習い事
- 運動系(スポーツ、体操)
- 筋力や巧緻性の発達
- 認知機能(記憶、注意、抑制力)の向上
- 社会性や自己調整力の育成
- 音楽系(楽器演奏、歌唱)
- 言語能力や集中力の強化
- 感情表現や情緒の安定
- 記憶力や空間認識能力の向上
- 言語系(読み聞かせ、語学)
- 語彙力や読解力の発達
- 言語的短期記憶と視空間的ワーキングメモリの向上
- 認知柔軟性とマルチタスク能力の強化
- 創造的活動(お絵描き、工作、ごっこ遊び)
- 問題解決力や発散的思考の育成
- 心の理論(他者の感情理解)の発達
- 自己抑制力や記憶力の強化
体験させておきたいこと
- 自然体験
- 想像力と問題解決能力の向上
- 身体的・感覚的な発達
- ストレスの軽減と情緒の安定
- 社会性を養う関わり(友達との遊び)
- 協調性や自己主張力の発達
- 他者の心情理解(Theory of Mind)の向上
- 社会的スキルと共感力の強化
- 手先を使う活動や日常生活
- 巧緻性の向上(書字、工作、日常動作)
- 空間認識と問題解決力の発達
- 自立心や自己肯定感の育成
両親が心がけるべきこと
- 愛情深く応答的なコミュニケーション
- 安全基地の形成
- 語彙力とコミュニケーション能力の向上
- 読み聞かせと言葉のシャワー
- 語彙力と理解力の強化
- 親子の絆と情緒の安定
- 遊びと学びのバランス
- 創造力と好奇心の育成
- 自発的な学びと探究心の強化
- 規則正しい生活習慣
- 睡眠、食事、活動のバランス
- 自律心と集中力の育成
- メディア利用のコントロール
- 言語発達や認知能力への悪影響を防ぐ
- 親子での共同視聴と適切なコンテンツ選び
祖父母が心がけるべきこと
- 両親を支えるサポーターであること
- 育児負担の軽減と家庭の安定
- 親子のストレス軽減とQOL向上
- 豊かな会話と遊びで言語・社会性を促す
- 語彙力と情緒の安定
- 創造力と共感力の育成
- 甘やかしすぎず自立を促す
- 自立心と問題解決力の育成
- 過保護による依存を避ける
- 親の方針を尊重し一貫性を保つ
- 一貫した養育スタイルで安心感を提供
- 親子間の葛藤を減らし安定した育児環境を支援
参考文献・情報源
参考文献・情報源
- 運動と認知発達の関連
- Diamond, A. (2000). Close interrelation of motor development and cognitive development and of the cerebellum and prefrontal cortex. Child Development, 71(1), 44-56.
- Tomporowski, P. D., Davis, C. L., Miller, P. H., & Naglieri, J. A. (2008). Exercise and children’s intelligence, cognition, and academic achievement. Educational Psychology Review, 20(2), 111-131.
- 音楽教育と認知能力
- Hannon, E. E., & Trainor, L. J. (2007). Music acquisition: Effects of enculturation and formal training on development. Trends in Cognitive Sciences, 11(11), 466-472.
- Schellenberg, E. G. (2004). Music lessons enhance IQ. Psychological Science, 15(8), 511-514.
- 言語発達と読み聞かせ
- Montag, J. L., Jones, M. N., & Smith, L. B. (2015). The words children hear: Picture books and the statistics for language learning. Psychological Science, 26(9), 1489-1496.
- Gilkerson, J., Richards, J. A., Warren, S. F., Oller, D. K., Russo, R., & Vohr, B. (2017). Language experience in the second year of life and language outcomes in late childhood. Pediatrics, 140(4), e20163657.
- Hart, B., & Risley, T. R. (1995). Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children. Brookes Publishing.
- 自然体験と発達への影響
- Kellert, S. R. (2005). Building for life: Designing and understanding the human-nature connection. Island Press.
- Louv, R. (2008). Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder. Algonquin Books.
- 社会性と心の理論
- Hughes, C., & Dunn, J. (1998). Understanding mind and emotion: Longitudinal associations with mental-state talk between young friends. Developmental Psychology, 34(5), 1026-1037.
- Lillard, A. S., & Witherington, D. C. (2004). Mothers’ socialization of preschoolers’ pretend play and social competence. Developmental Psychology, 40(6), 1012-1022.
- 家庭環境と育児スタイル
- Landry, S. H., Smith, K. E., & Swank, P. R. (2006). Responsive parenting: Establishing early foundations for social, communication, and independent problem-solving skills. Developmental Psychology, 42(4), 627-642.
- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (2015). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Psychology Press.
- 祖父母の関与と子どもの発達
- Silverstein, M., & Marenco, A. (2001). How Americans enact the grandparent role across the family life course. Journal of Family Issues, 22(4), 493-522.
- Buchanan, A., & Rotkirch, A. (2016). Grandfathers in cultural context. Springer.
- メディア利用と子どもの発達
- American Academy of Pediatrics (2016). Media and Young Minds. Pediatrics, 138(5), e20162591.
- Christakis, D. A., & Zimmerman, F. J. (2009). Violent television viewing during preschool is associated with antisocial behavior during school age. Pediatrics, 124(5), 993-999.