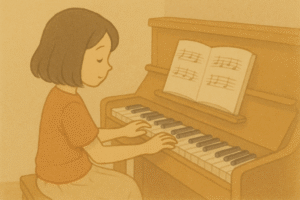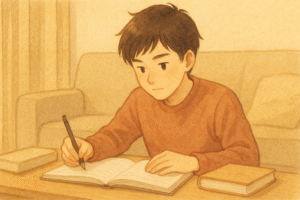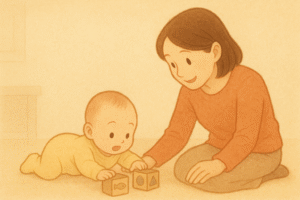こんにちは、Dr.流星です。
小学校高学年になると、子どもの脳はますます複雑な情報処理が可能になり、抽象的な思考力や論理的な理解力が育ち始めます。この時期は、これまで培ってきた基礎的な学力をさらに高めるとともに、自分で考え計画する力を伸ばす絶好のチャンスです。
今回は、高学年の子どもが自主的に学び続けるための脳の発達特性、動機づけのポイント、親のサポート方法、そして学習環境の工夫について詳しく解説します。お子さんがさらに学びに前向きになれるよう、一緒に工夫してみましょう。
小学校高学年(9~12歳)
脳の発達と認知の成長
高学年になると、子どもの認知能力は大きくレベルアップします。論理的思考や抽象的な概念の理解が徐々に可能になり、目に見えないルールや数量関係も扱えるようになります(ピアジェの形式的操作期の入り口に近づく頃です)。脳の構造的には、この時期からシナプスの刈り込み(不要な回路の整理)が本格化し、効率的な脳ネットワークが形作られる段階です。頻繁に使うスキルの神経回路は太く強固になり、使わないものは減弱していきます。したがって、学習したことを繰り返し使って定着させることがますます重要になります。例えば、4年生で習う分数の概念なども、一度テストが終わったら終わりではなく、買い物で割引を計算する時に使ってみる、料理で2/3カップを計る時に一緒に考えるなど、生活の中で何度も登場させると、脳内に長期記憶として回路化されやすくなります。逆に言えば、この時期に基礎をおろそかにすると中学生以降で苦労するので、学校で習ったことは確実に押さえられるように親も積極的に関与しましょう。また、高学年は記憶力が飛躍的に伸びる時期でもあります。語彙数や知識量が増え、学んだ情報同士を関連付けて覚えることができるようになります。社会や理科の暗記物も、この時期にコツを掴んで覚える習慣がつくと、中高の勉強が楽になります。加えて、メタ認知(自分の考え方を客観視する能力)も芽生えてくるため、「どうすれば効率よく覚えられるかな?」と親子で学習方法を話し合うのも良いでしょう。例えば、「音読すると覚えやすいかな」「図に描いて整理してみようか」「インターネットで画像や動画を見てみようか」といった戦略を一緒に試して、自分に合った学習法を発見できれば、子どもは主体的に勉強を工夫する力を身につけます。この頃の脳発達の大きな特徴として、思春期前後のホルモン変化が脳にも影響し、情緒や行動に揺らぎが出やすい点があります。小学校高学年から思春期にかけて感情を司る扁桃体や報酬系の活動が高まり、理性を司る前頭前野とのバランスが一時的に崩れがちになるため、ムラっ気や反抗心が見られることもあります。これは脳の成長過程で自然なことであり、親はあまり厳しく押さえつけず見守る姿勢も必要です。総じて、高学年の脳は「大人の脳へのリモデリング期」に入ります。基礎学力をさらに固めつつ、抽象的な思考力の芽を育て、勉強面でも自ら考え計画する力を徐々に身につけさせることが、この時期の目標となります。
モチベーション:内発的動機の伸長と外発的動機の調整
高学年になると、学習へのモチベーションにも変化が出てきます。テストの点数やクラスでの順位など「評価」を意識し始めるため、純粋な好奇心だけでなく競争心や達成欲求が動機づけに加わります。これは外発的モチベーションが強まることでもありますが、この時期に内発的モチベーションも失わずに育てることが、将来的な「勉強好き」につながる重要なポイントです。親や教師は、子ども自身の興味関心を深める働きかけを意識しましょう。例えば、算数が好きな子には難しめのパズルや図形遊びを与えて更に興味を伸ばす、歴史が好きな子には関連する漫画を与え、歴史博物館に連れて行く、といった具体的なアクションです。本人が夢中になれる分野を広げてあげることで、「学ぶ楽しさ」を実感し続けることができます。一方、どの教科にもあまり興味が持てない子には、学ぶ内容を現実や将来と結びつけて意義づけしてあげるのも方法です。「英語を覚えると海外のゲームもできるね」「科学を知ると料理も上手になるよ」「ピッチャーには物理も必要なんだ」など、知識が生活を面白くする例を示すと勉強への前向きさが出ます。報酬の活用法も見直します。低学年まではシールやお小遣いといった報酬が効果的でしたが、高学年になると幼すぎるご褒美はかえってプライドを傷つけることもあります。ご褒美を与えるなら本人の希望やプライバシーを尊重した形にします。例えば、「計画通りテスト勉強できたら欲しがっていた漫画を買ってもいいよ」など、子ども自身が密かにモチベーションにできるものが良いでしょう。とはいえ、報酬が主目的にならないよう注意も必要です。報酬なしでも学習を続けられるよう、徐々に報酬は減らし内発的動機づけへ移行していきます。具体的には、できるだけ達成そのものを喜ぶ雰囲気を作ることです。テストで目標点を取れたら「努力してたもんね。お母さん(お父さん)も嬉しい!」と本人の喜びに寄り添い、仮に失敗しても「今回はうまくいかなかったけど、この問題が解けるようになってるね。確実に力がついているよ」と成長を実感させる声かけをします。また、高学年の子どもは責任感や自尊心が芽生えているので、「あなたならできると信じてるよ」「任せたよ」といった言葉も効果的です。心理学の研究でも、大人からの信頼や期待は子どもの自己効力感を高め、動機づけにつながることが示されています(いわゆるピグマリオン効果)。ただし、期待がプレッシャーになりすぎないよう声かけは温かく控えめにします。例えば、「絶対100点取ってね。頑張ったんだからしっかりね」ではなく「毎日頑張ってたから、きっとうまくいくよ」と励ます程度に留めましょう。高学年は思春期の入り口で多感な時期なので、叱咤より激励、そして自主性を尊重することがモチベーション維持の鍵です。また、この頃になると友達との関係も学習意欲に影響します。友達同士で刺激し合って勉強したり、逆にサボる仲間に流されたりということも。できれば良いライバル関係を築けるよう、友達と一緒に勉強する機会を作ったり、親しい友人の保護者と協力して情報交換したりすると良いでしょう。まとめれば、高学年では「興味関心の深化」「学ぶ意義の実感」「達成感の共有」を意識し、内発的モチベーションを高めつつ、外発的報酬は補助的に使うというバランスが重要です。
親の関わり方
小学校高学年になると、子どもはかなり自立心が出てきます。親の言うことに反発したり、「自分でやるから放っておいて」と言ったりする場面も増えるでしょう。しかし、親のサポートが不要になるわけではありません。親の関わり方を「管理」から「伴走・相談役」に切り替えるタイミングだと考えてください。まず、日々の勉強については基本的に本人に計画させるよう促します。例えば、「夏休みの自由研究、どんなテーマにしようか?どういう計画で進める予定かな?」と尋ね、子どもが自分でスケジュールを立てるのをサポートします。必要に応じてカレンダーに一緒に書き込んだり、中間チェックの日を決めたりして、計画力と実行力を養います。親はあれこれ指示を出す代わりに、「何か手伝えることある?」「困ったらいつでも聞いてね」というスタンスで、子どもが助けを求めたらサポートする姿勢を示しましょう。一方で、まだ子ども任せにするには不安な部分(例えばテスト前の総復習など)は、一緒に計画を立てても構いません。重要なのは子ども自身が主体的に考える余地を必ず作ることです。家庭学習でも、高学年になったら親が付きっきりになる必要はありません。宿題も自室や自分の勉強机でできるようになります。ただ、完全に放任するとスマホや他の遊びに流れる可能性もあるので、「終わったら見せてね」と声をかけ、適度にチェックは続けましょう。この時、答え合わせや間違い直しもなるべく子どもにさせ、自律性を高めます。親のサポート不足が災いして、あとから「なんで宿題してないの!」「自分が悪いんだからね!」と言わないようにしたいですね。親は間違えた問題の解き直し方を教える程度に留めるだけで十分です。例えば、「どうして間違えたか一緒に考えてみようか」など声をかけ、復習の大切さを少しずつ理解させます。また、親子の会話も勉強の話だけでなく、ニュースや時事ネタについて意見を聞いたり、親の仕事の話をしたりと広げていきます。子どもは大人扱いされたようで嬉しく思い、積極的に考えを述べたり質問したりするでしょう。確かにちょっと背伸びではありますが、そうした対等なコミュニケーションの中で、実は社会や科学の知識が身についたり、論理的思考の訓練になったりもします。「なぜ選挙があるの?」「ウイルスと細菌の違いって?」などと聞かれたら、面倒がらず調べて一緒に考えると、家庭が知的対話の場になり、学ぶ意欲を刺激できます。さらに、親の生き方や価値観が子どもの学習観に影響を与えることも意識しましょう。文科省の提言では、子どもの学習意欲を高めるには将来の職業や生活と学びを結びつけて、その意味や価値を実感させる教育が有効とされています。家庭でも、「お父さんは子どもの頃はこの勉強が役立つって思えなかったけど、今では…」など、勉強と人生の関連について話してみるのもよいでしょう。ただし、押しつけにならないよう、「あなたもこうしなさい」「親の言う通りにしてたらいい」という説教ではなく、あくまで一例として語る程度にします。高学年は親の価値観を批判的に見る面も出てきますので、対話の姿勢を大事にしてください。最後に、心理的サポートも引き続き重要です。思春期に差しかかり、友人関係のトラブルや思い通りにいかない悩みが学業に影響することもあります。親は勉強のことばかり責めるのではなく、子どもの心の声にも耳を傾けましょう。例えば、成績が落ちたときも、まず「最近何かあった?」と寄り添い、原因を一緒に探る姿勢を取ります。何も問題がなく単に怠けていた場合でも、頭ごなしに怒るより「どうしたらやる気出るかな?」と問いかけ、一緒に対策を考えます。親子の信頼関係が保たれていれば、子どもは素直に本音を話し、アドバイスも受け入れやすくなります。つまり、高学年期の親は、前面に立って引っ張るのではなく、「”黒子的”支援者」となり、背後から支えている存在になりましょう。適度な距離感を保ちつつ、子どもが助けを求めればすぐ応じ、褒める時はしっかり褒め、失敗した時は励まし、子ども自身が自分の力で進んでいけるよう見守ることが、結果的に勉強への前向きな姿勢を長続きさせる秘訣です。
学習環境の最適化
小学校高学年になると、子どもによって「勉強するならこの環境が落ち着く」という好みが出てきます。ある子は自室で一人静かにする方がはかどり、別の子はリビングで人の気配があった方が集中できるかもしれません。本人の好みや集中度合いを観察し、最適な環境を一緒に整えましょう。 もし自室で勉強する場合、先述したようにテレビやゲームは別室に置き、スマホはリビングに預けるなどデジタルデトックス環境を用意します。ただ、タブレットで調べ物をすることも増える時期なので、一概に電子機器を排除できません。そこで、ルーターの設定で夜○時以降は学習サイト以外閲覧不可にする、アプリの使用時間を制限する、といった技術的なサポートも検討してください。本人にも、「〇時までは通知オフにしようね」など自己管理の方法を教えていくと良いでしょう。机と椅子は体格に合ったものを用意し、長時間座っても疲れにくい姿勢を保てるようにします。場合によっては高さ調節クッションや足台を使ってもいいでしょう。照明も高学年になっても引き続き重要です。特に夜に勉強することが増えるので、演色性の高いスタンドライトで手元を十分に照らし、目の負担を軽減します。部屋全体の明るさも確保し、陰影が強すぎないようにしましょう。環境心理学の研究では、明るさ・空気質・温度の3つで学習環境の半分近くの効果が決まるとも言われています。温度については、勉強時は適度に緊張感がある方が良いため冬でも厚着させすぎず、少し涼しいくらいが集中力が高まるという意見もあります(個人差があるので子どもの様子を見て調節してください)。音環境については、この時期になると多少の雑音は無視できる子もいれば、相変わらず静寂でないとダメな子もいます。前述のように騒音は学習の大敵なので基本は静かな環境がベストですが、子ども自身が「環境音アプリを流すと集中できる」など好みを掴んできたら、それも尊重しましょう。ただし、歌詞のある音楽は読解や暗記の妨げになるので、流すならクラシック音楽や自然音などがおすすめです。視覚環境では、高学年ともなると教科ごとの資料やノートが増えて机が散らかりやすくなります。整理整頓の仕方も一緒に考えてあげましょう。ファイルボックスを設置して科目別にプリントを整理したり、カレンダーやホワイトボードを活用して宿題や試験日を見える化すると、机周りが「自分の勉強基地」らしく機能します。例えば机の前の壁にホワイトボードを貼って、「今週やることリスト」を子ども自身に書かせると、自律的な学習計画の練習にもなります。さらに、集中できないときは場所を変えるのも手です。家族の出入りが気になるなら図書館に行く、気分転換にカフェで勉強してみるなど、環境を変えて集中力を引き出す方法も教えてみてください。ただし、カフェは周囲の目もあるので長時間は難しく、小学生なら図書館の自習室が安全でしょう。環境を変える際は「○時までここで頑張ってみよう」と時間を区切ると良いです。全体として、高学年の学習環境づくりは本人の意見を取り入れつつ、集中を妨げる要因を親子で特定して潰していく作業になります。親子で「どうすると一番勉強に集中できるかな?」と話し合い、照明や音、温度、片付けの仕組みなどを調整しましょう。このプロセス自体が子どもにとっては自分の学習スタイルを理解する訓練にもなります。将来自分で環境を整える力をつけるためにも、一緒に試行錯誤して最適な学習空間を創り上げてください。
小学校高学年(9~12歳)
- 脳の発達
- シナプス刈り込みが進み、”効率的に考える”神経回路が形成される。
- 抽象的思考力や論理的な理解が育ち始める。
- モチベーション
- 達成感や内発的動機を重視。
- 短期目標と長期目標の組み合わせが効果的。
- 親の関わり方
- 基本的に子どもに計画を任せつつ、必要時にサポート。
- 成長の実感を言語化してあげる。
- 学習環境
- 自分で片付ける習慣を促す。
- 机周りの視覚的整理が重要。
参考文献・情報源
参考文献・情報源
- 乳児期の脳発達
- Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (Eds.). (2000). From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. National Academy Press.
- Johnson, M. H. (2005). Developmental Cognitive Neuroscience. Wiley-Blackwell.
- 内発的動機づけと報酬系
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.
- Galván, A. (2013). The Teenage Brain: Sensitivity to Rewards. Current Directions in Psychological Science, 22(2), 88-93.
- Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627-668.
- 学習環境と家庭の影響
- Evans, G. W., & Wachs, T. D. (Eds.). (2010). Chaos and Its Influence on Children’s Development: An Ecological Perspective. American Psychological Association.
- Sanders, M. R., & Mazzucchelli, T. G. (2013). The Power of Positive Parenting: Transforming the Lives of Children, Parents, and Communities Using the Triple P System. Oxford University Press.
- 学習習慣と学力
- Dweck, C. S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. Random House.
- Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. P. (2005). Self-Discipline Outdoes IQ in Predicting Academic Performance of Adolescents. Psychological Science, 16(12), 939-944.
- Heckman, J. J., & Kautz, T. (2013). Fostering and Measuring Skills: Interventions That Improve Character and Cognition. NBER Working Paper No. 19656.
- 睡眠と学習の関係
- Walker, M. P. (2017). Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams. Scribner.
- Carskadon, M. A., & Tarokh, L. (2014). Developmental changes in circadian biology and sleep regulation. In G. G. National Research Council (Ed.), Sleep Disorders and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem. National Academies Press.
- 思春期の脳の発達
- Blakemore, S. J., & Mills, K. L. (2014). Is Adolescence a Sensitive Period for Sociocultural Processing? Annual Review of Psychology, 65, 187-207.
- Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The Adolescent Brain. Annals of the New York Academy of Sciences, 1124(1), 111-126.
- 家庭の学習支援と親の関わり
- Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1989). Parent Styles Associated with Children’s Self-Regulation and Competence in School. Journal of Educational Psychology, 81(2), 143-154.
- Pomerantz, E. M., Moorman, E. A., & Litwack, S. D. (2007). The How, Whom, and Why of Parents’ Involvement in Children’s Academic Lives: More Is Not Always Better. Review of Educational Research, 77(3), 373-410.