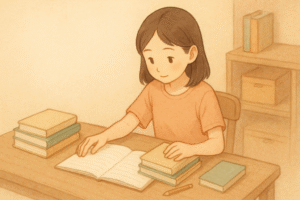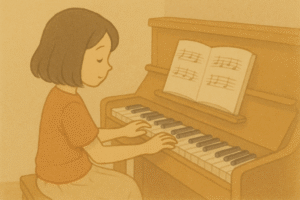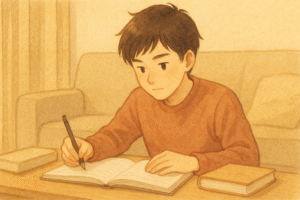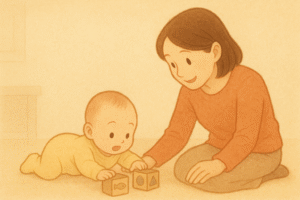こんにちは、Dr.流星です。
小学校低学年になると、子どもは具体的な思考力や記憶力が飛躍的に伸びる時期に入ります。読み書きや計算といった学業スキルが急速に発達し、学びの基礎が築かれる大切な段階です。この時期の子どもは、達成感や承認欲求が強く、親や教師からのポジティブなフィードバックが大きな動機づけになります。
今回は、低学年における脳の発達、効果的なモチベーションの与え方、親の関わり方、そして集中できる学習環境の作り方について解説します。お子さんが「勉強って楽しい!」と感じられるような工夫を取り入れてみましょう。
小学校低学年(6~8歳)
脳の発達と学習能力
小学校に入学する頃、子どもの脳は具体的な思考力と基礎的な記憶力が飛躍的に伸びる段階です。ピアジェの発達段階で言えば前操作期から具体的操作期への移行期で、まだ抽象概念は苦手ですが、身近な具体物を使った学習で理解力を発揮します。神経科学的には、この時期に読み書き計算といった学業スキル習得に応じて脳内で新たな回路が形成・強化されます。例えば、文字を読む習慣を身につけると視覚野と言語野の結びつきが強まり、読むスピードや理解力が向上していきます。また、神経可塑性が高いので正しい書き順や計算手順をこの時期にしっかり練習すると、そのパターンが効率的な脳回路として定着しやすくなります。つまり、脳の構築・再構築が繰り返し起こり、より能力を高めていくことができるのです。反面、誤ったやり方が癖になると後で修正が大変なので、基本の定着が重要な段階です。厚生労働省の発達研究でも、この頃に獲得する「読み・書き・計算」の基礎は生涯の学習能力に直結するとされています。そのため、低学年のうちは学校や家庭で反復練習を通じて基礎学力を脳に焼き付けることが望ましいでしょう。ただし、長時間集中はまだ難しく、注意持続時間は20~30分程度とも言われます。一度に詰め込むよりも、小刻みな学習と休憩を織り交ぜる方が効率的です。例えば、20分勉強したら5分くらい体を動かす、といったリズムを作ると、脳がリフレッシュして次の学習に臨めます。また、低学年では体の発達と脳機能が密接に関連しています。十分な睡眠と運動が認知機能を高めることも示唆されていますので、早寝早起きや外遊びの時間確保も学力向上の一部と考えてください。まとめると、小学校低学年の脳は「基礎回路を作り上げる工事中」の状態です。焦らず着実に基礎固めをしつつ、子どものペースに合った学習で脳に成功体験を刻んでいくことが、勉強好きになる素地を築きます。
モチベーションと報酬の扱い
低学年の子どもは、とても素直に外的な賞賛やご褒美に反応します。先生や親に「よくできました」と言われたり花丸をもらったりすると大喜びし、また頑張ろうという気持ちになります。同時に、「もっと知りたい」「もっと上手になりたい」という内発的動機も育ち始める時期です。この内発的な部分を伸ばすために、ただ結果を褒めるだけでなく過程や努力を評価するフィードバックを与え続けることが大切です。例えば、テストで100点を取った時、「満点ですごいね」だけでなく「毎日コツコツ勉強した成果だね」と努力や過程を認める言葉をかけます。逆に結果が振るわなかった時も、「今回は残念だったけど、頑張ったことは知ってるよ。また一緒にやってみようか」と伝えましょう。そうすることで、点数や順位といった外発的報酬だけに子どもの関心が向かないようにできます。実際、親の関与が高く励ましを受けている子どもほど、学校での学業への関与や意欲が高いことが、大規模な研究レビューで明らかになっています。親が関心を持っていることを日頃から伝えてあげることが肝要です。一方で、ご褒美シールやポイント制も低学年には効果的に働きます。例えば、毎日宿題をやったらカレンダーにシールを貼り、目標数貼ることができたら小さなご褒美を与える、といった簡単な報酬制度は、学習習慣を楽しく定着させる助けになります。しかし、ここでも注意したいのは、ご褒美の与えすぎで「もらえるからやる」と思わせないことです。あくまで「自分から勉強したから結果としてご褒美がもらえた」という順序を大切にし、主体性を尊重しましょう。幸いこの年代の子どもは、まだ「勉強=楽しい」という感覚を持ちやすいです。学校でも塗り絵のようなワークやゲーム仕立ての教材が用いられ、学習と遊びの境目が曖昧です。家庭でも、例えば、九九を歌で覚えたり、理科の単元に合わせて一緒に植物を育てたり、歴史の勉強で博物館に連れて行ったりと、知識を実生活や遊びに結びつける工夫をすると、興味が深まり自主的な学びにつながります。また、低学年は競争心よりも承認欲求(認められたい)が強い傾向があります。「友達は宿題してるんだからあなたもしなさい!」ではなく、「先生に提出する宿題、きれいに書けたね。先生も喜ぶね」などと声をかけ、他者からの承認と結びつけるのもモチベーション維持に効果的です。ただし、承認欲求も行き過ぎると「他人の評価のために勉強する」ようになってしまうので、あくまでバランスが大事です。子ども自身が「できるようになって嬉しい!」と感じる内なる報酬を味わえるよう、達成したことを一緒に喜び、「成長実感」を言語化してあげましょう。例えば、「前は30分かかっていたのに、今日は15分でできたね。すごい成長だね!」と言えば、子どもも「できるようになってるんだ」と自分の上達を認識し、さらなる自信と意欲が湧きます。
親の関わり方
小学校低学年の子どもにとって、親の関与は学習習慣を身につける決定的な要因となります。まず入学したら、家庭での勉強のルールやリズムを親子で作りましょう。例えば、「宿題は毎日○時からリビングのテーブルでやる」「宿題が終わったらテレビ(ゲーム)タイムにする」など、決まった流れを設定します。文部科学省も、学習意欲・習慣を高めるには家庭での学習課題や復習の時間を設け、家庭と学校が連携して学習習慣を確立する必要があると指摘しています。実際、学校から宿題が出ない日でも親がドリルや読書タイムを課す家庭の子は、学力面で優位にあるとの調査もあります。最初のうちは親が隣についてサポートすると良いでしょう。難しい問題に直面した時はヒントを出したり、一緒に考える姿勢を見せてください。ただし、答えをすぐ教えたり手を出したりしないことも大切です。ヒントは小出しにして、子どもが自力で解けた時にはしっかり褒め、「できた!」という達成感を味わわせます。自力で考える力を培うには少し時間がかかりますが、親がじっくり待つことで子どもの思考力・忍耐力が育ちます。また、子どもに自分の学びを表現させる機会も作りましょう。例えば、「今日学校で面白かったこと教えて?」と尋ね、子どもが習ったことを説明できるように促します。人に教えることで理解が深まり、また親が興味を持って聞いてくれることで学ぶ意義を感じます。研究でも、親が家庭で学業について会話したり関与したりするほど、子どもの学業成績や学習意欲が向上するとされています。子どもとの交流時間も増え、一石二鳥です。その他、習慣化のサポートも続けましょう。低学年のうちは、明日の時間割に合わせた教科書やノート、体操服などを一緒に揃えたり、宿題のチェックを親が手伝ったりして構いません。そうすることで、「勉強や準備は日々やるもの」という認識が身につきます。ただし学年が上がるにつれ、徐々に自分でできる部分は任せ、親は監督から支援者へ役割シフトしていく意識を持つと良いでしょう。また、親自身も学びに参加する姿勢を見せます。例えば、子どもが虫捕りや草花に興味を持てば、図鑑を買って親も一緒に調べてみる、子どもが算数でつまづいたら「お母さん(お父さん)も解いてみようかな」と一緒に解法を確認するなど、「一緒に学ぶ仲間」というスタンスを取ると、子どもは安心して質問できます。加えて、学校行事やPTAへの参加も有益です。教育研究によると、学校での親の関与(授業参観や学校イベント参加)は子どもの学業成績や社会性にも良い影響があるとされています。親が学校と連携し、先生とも情報交換することで、子どもへのサポート体制が強化されるでしょう。まとめると、低学年期の親は「コーチ兼チアリーダー」のような存在です。適切なルール作りとサポートで学習習慣をコーチしつつ、常に励まし前向きな言葉で子どもの努力を称え、「勉強って面白い」「もっとやりたい」と子どもが思える雰囲気を作りましょう。
家庭の学習環境
この時期、落ち着いて勉強に取り組める環境を用意することも大切です。まず、家の中で「ここで勉強する」という場所を決めます。リビングの一角でも子ども部屋でも構いませんが、集中できる静かなスペースであることが条件です。テレビの音や兄弟の遊ぶ声が聞こえると注意がそれてしまうので、勉強時間中はテレビを消す、兄弟には別の遊びを提供するなど協力を仰ぎます。また、学習環境で見落とされがちなのが騒音の影響です。欧州の調査では、交通騒音など環境騒音に日常的にさらされている子どもは、読解力の得点が低下し行動面の問題も増える傾向が確認されています。そのため、可能な範囲で静かな学習環境を整えることは学力面だけでなく行動面にもプラスと言えます。窓の防音対策やイヤーマフの利用なども場合によっては検討しましょう。次に照明です。子どもの視力を守り集中力を維持するには十分な明るさが必要です。イギリスの大規模研究(HEADプロジェクト)では、教室の物理環境が学習成果に影響し、その中でも照明(光環境)が最も大きな効果を及ぼしたと報告されています。自然光が差し込む明るい部屋で学ぶ児童は、暗い部屋の児童に比べて読解・算数などの技能が20~26%も向上したというデータもあります。家庭でも昼間はカーテンを開けて自然光を取り入れ、夕方以降はスタンドライトなどで手元をしっかり照らしましょう。LED照明なら青白い昼光色は覚醒効果が高い一方、夜遅くは眠りを妨げるので暖色系に切り替える、といった工夫もよいでしょう。学習用具や視覚環境にも配慮します。低学年の子は文房具に興味を持つので、自分のお気に入りの鉛筆やノートを選ばせると勉強への愛着が湧きます。机の周りには地図や掛け算表など役立つポスターを貼るのも良い刺激ですが、前記事で述べたように貼りすぎは禁物です。机の上も常に筆記用具と宿題に必要なものだけ出し、ゲームやおもちゃ、マンガなど誘惑になるものは視界に入らないように片付けておきます。整理整頓された環境は頭の中の整理にもつながり、学習効率を高めます。親子で一緒に「勉強する前に机をきれいにしよう」と片付ける習慣をつけるのも良いでしょう。さらに、低学年のうちはまだ親の目が届く場所で勉強させる方が安心です。リビング学習は親子のコミュニケーションも取りやすいため、多くの家庭で採用されています。ただし、集中力に個人差があるので、リビングだと気が散る子は静かな子ども部屋で、一人だと不安な子はリビングでと、子どものタイプに合わせて柔軟に環境を選ぶと良いでしょう。最後に、家庭におけるデジタル機器との付き合いもこの頃からルール化します。宿題中はタブレットゲームは禁止、インターネットで調べ物をする時は親が見守る、といった約束を決めておきます。早い段階でルールを設けておけば、中高生になっても自制しやすくなります。総じて、小学校低学年では明るく静かで整理された学習空間を提供し、親の目が届く範囲で習慣づけをサポートすることが、勉強に向かう前向きな姿勢を育てる助けとなります。
小学校低学年(6~8歳)
- 脳の発達
- 具体的な思考力と基礎的な記憶力が発達する時期。
- 繰り返し使うスキルが脳に定着しやすく、学習効率が高まっていく。
- モチベーション
- 努力や過程を評価するフィードバックが有効。承認欲求を満たす。
- 短時間の学習(20~30分)と休憩(5分程度)のリズムが集中力を高める。
- 親の関わり方
- 毎日の学習習慣をサポート。「一緒に学ぶ」姿勢を見せる。
- 自力で解決する力を育てる(ヒントを出しつつ見守る)。
- 学習環境
- 静かで集中しやすいスペースが重要。子どもに合わせた学習環境を。
- 明るい部屋での学習。整理整頓と適度な視覚環境の工夫をする。
参考文献・情報源
参考文献・情報源
- 乳児期の脳発達
- Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (Eds.). (2000). From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. National Academy Press.
- Johnson, M. H. (2005). Developmental Cognitive Neuroscience. Wiley-Blackwell.
- 内発的動機づけと報酬系
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.
- Galván, A. (2013). The Teenage Brain: Sensitivity to Rewards. Current Directions in Psychological Science, 22(2), 88-93.
- Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627-668.
- 学習環境と家庭の影響
- Evans, G. W., & Wachs, T. D. (Eds.). (2010). Chaos and Its Influence on Children’s Development: An Ecological Perspective. American Psychological Association.
- Sanders, M. R., & Mazzucchelli, T. G. (2013). The Power of Positive Parenting: Transforming the Lives of Children, Parents, and Communities Using the Triple P System. Oxford University Press.
- 学習習慣と学力
- Dweck, C. S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. Random House.
- Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. P. (2005). Self-Discipline Outdoes IQ in Predicting Academic Performance of Adolescents. Psychological Science, 16(12), 939-944.
- Heckman, J. J., & Kautz, T. (2013). Fostering and Measuring Skills: Interventions That Improve Character and Cognition. NBER Working Paper No. 19656.
- 睡眠と学習の関係
- Walker, M. P. (2017). Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams. Scribner.
- Carskadon, M. A., & Tarokh, L. (2014). Developmental changes in circadian biology and sleep regulation. In G. G. National Research Council (Ed.), Sleep Disorders and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem. National Academies Press.
- 思春期の脳の発達
- Blakemore, S. J., & Mills, K. L. (2014). Is Adolescence a Sensitive Period for Sociocultural Processing? Annual Review of Psychology, 65, 187-207.
- Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The Adolescent Brain. Annals of the New York Academy of Sciences, 1124(1), 111-126.
- 家庭の学習支援と親の関わり
- Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1989). Parent Styles Associated with Children’s Self-Regulation and Competence in School. Journal of Educational Psychology, 81(2), 143-154.
- Pomerantz, E. M., Moorman, E. A., & Litwack, S. D. (2007). The How, Whom, and Why of Parents’ Involvement in Children’s Academic Lives: More Is Not Always Better. Review of Educational Research, 77(3), 373-410.