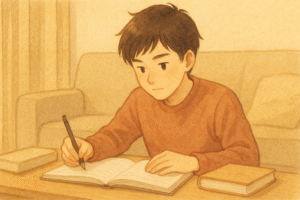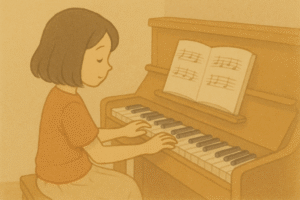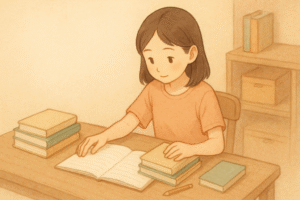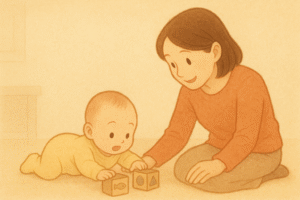こんにちは、Dr.流星です。
18歳以上となっても、まだまだ学びの機会は続きます。脳は成熟期を迎え、抽象的な思考力や問題解決能力がさらに洗練されます。自己決定が求められる場面が増え、学ぶ内容も高度で専門的になりますが、その分「学ぶ楽しさ」や「知識を深める喜び」も大きくなります。
今回は、本シリーズ最後となる18歳以上(主に大学生)が生涯学び続けるための力を育むポイントを解説していきます。脳の発達特性、内発的動機づけの重要性、親の関わり方、そして学習環境の整備について考え、学びが人生を豊かにする力であることを再確認し、成長を支えるヒントにしていただければと思います。
18歳以上(大学生以上)
脳の発達と生涯学習能力
大学生になると、脳の構造発達はほぼ完了に近づきます。一般に25歳前後で脳の発達は成熟期を迎えると言われますが、大学生(18~22歳)の脳はまさにその最終段階です。とはいえ、神経可塑性が失われるわけではなく、大人になってからも新しい知識やスキルを習得すれば脳内に新たな回路が形成されます。大学生は自分の専攻分野を深く学ぶことで、関連する脳領域(例えば工学なら論理的思考や視空間能力、語学なら言語野など)をさらに発達させることができます。また、この年代は抽象的思考力や批判的思考力が一段と洗練され、複雑な問題に対処したり、自ら問いを立てて探究したりする能力が育ちます。大学での学びは受動的なものから能動的・創造的なものへ移行するため、脳も「知識を得る脳」から「知識を運用・創造する脳」へと機能的にシフトします。
一方、脳の生物学的成熟に伴い、学生によっては「もう若くない」「新しいことを覚えにくくなった」と感じるケースもあります。しかし実際には、適切な刺激と意欲があれば脳は生涯成長可能です。大学時代はそのことを体感する良い機会です。難しい専門科目を履修し苦労しても、乗り越えれば脳内に強固な理解のネットワークが築かれます。また、20歳前後は価値観やアイデンティティの形成が進む時期でもあり、心理社会的成熟が脳の神経ネットワークにも影響を与えます。例えば、計画力や共感力といった高次の認知機能は、人との交流や自己省察によってさらに磨かれていきます。
医学的に見ても、大学生の年代は精神疾患の発症が増える時期でもあります。うつ病や不安障害がこの頃始まる人も多いです。強いストレスや生活環境の急激な変化が引き金になることも多いですが、これは脳の神経ネットワークが環境に適応しようと再編成されている時期であることも一因かもしれません。いずれにせよ、心身の健康が学習効率に直結する点はこの年代も同じです。睡眠不足や不摂生は記憶力や集中力を鈍らせますし、メンタル不調は認知機能全般を下げます。
総じて、大学生の脳は「成熟しながらも柔軟性を保った状態」です。自分の選んだ道を深めつつ、周辺領域にも広げ、社会との関わりの中でより複雑な思考を身につけていく段階と言えます。親としてはもう子どもの脳発達をどうこうする立場ではありませんが、ここまで育ててきた集大成として生涯学び続ける力を発揮できるよう、最後のサポートをする心構えでいましょう。
モチベーション:生涯にわたる学習意欲へ
大学生の学習モチベーションは、それまでと大きく性質が異なります。まず、勉強するもしないも本人の自由です。極端な話、大学をさぼっても親や教師から叱られることはなく、単位を落として痛い目を見るのも自己責任です。そのため、真に自律した内発的動機づけがないと、勉強を続けることは難しくなります。幸い多くの学生は自分の興味ある分野を専攻しているため、高い内発的興味を持っています。しかし、中には「なんとなく大学に来た」「親に言われて進学した」ために目的意識が希薄な学生もいます。そうした場合、モチベーションを見失いがちです。
親としてできることは限られますが、子どもが大学で学んでいることに関心を示すのは効果があります。例えば、「最近どんな授業が面白いの?」「この前のゼミ発表はどうだった?」と問いかけてみます。子どもが嬉々として話すなら、本当にその分野が好きなのだと安心できますし、あまり乗り気でなければ別の興味を探すよう勧めるきっかけになるかもしれません。大学は専門変更や副専攻、サークル活動など学びの幅が広いので、本人が情熱を傾けられるものを見つけることが重要です。親は直接それを見つけてあげられませんが、会話の中でヒントを出したり、いろいろな経験を提案することはできます。例えば、「パソコンが好きならパソコンに関する動画を投稿してみたら?」「アルバイトやボランティアで子どもにパソコンやプログラミングを教えてみたら?」など、本人の関心に沿った活動を薦め、新たな内発的動機の芽を発見させる手助けをします。ただし、詳しくない専門分野に口出しする場合は、あまり深く干渉しないように注意します。
また、大学生になると将来のキャリアが具体的な動機になります。就職活動が迫れば嫌でも勉強や資格取得に身が入るでしょう。ただ、ここで気をつけたいのは外発的動機づけだけに陥らないようにすることです。就活のためだけに勉強するのは短期的には役立ちますが、内発的な学ぶ喜びがないと社会に出てから成長が止まってしまう恐れがあります。そこで親は、「就職に有利だからという理由だけで興味のない資格を取る」より、「自分が本当に興味を持てることを深め、その結果として強みになるものがいい」という視点を伝えます。実際、自己決定理論でも人は内発的に意味を感じられる活動の方が長続きし成果も出るとされます。例えば、親が「〇〇の資格は将来食いっぱぐれないから取りなさい」というより、「この資格はこういうメリットがあるよ」「興味があるなら挑戦してみたら?」という応援に留めるべきでしょう。
称賛や承認のモチベーション効果も大学生には依然ありますが、求める対象が親や教師から、友人や社会へと移ります。例えば、資格を取ったり、研究で成果を出して学会発表したり、コンテストで表彰されたりすることが大きな自信と意欲につながります。親としては陰ながら応援し、その成功を家族で祝うなどして更なる励みにします。逆に失敗や挫折を経験した時は、そっと支えます。大学生ともなると親に弱音を吐かないかもしれませんが、態度や表情で不調は感じ取れるでしょう。そういう時は無条件に受け止め、「あなたが大人になろうと、お母さん(お父さん)はずっと味方だよ」という安心感を与えます。それだけで立ち直る力になることもあります。立ち直る活力が必要なときに「もう大人なんだから自分で何とかしなさい」と突き放すことは避けます。
生涯学習者となるには、大学時代に「自分で学び続けられる」という自己効力感を確立することが大事です。親はこれまでの子育てで築いた信頼関係の中で、「あなたならどんなことでも学んでいける」というメッセージを最後に伝えてあげましょう。例えば、大学卒業後に進学や起業、転職など新たなチャレンジをすると言った時、「本当にできるの?」「失敗したらどうするの」という心配より先に「あなたならできるよ」「決めたことなら応援しているよ」と背中を押してあげることです。親が子を信じる姿勢は、子どもの内発的な勇気と意欲を引き出します。
まとめれば、大学生以降のモチベーションは本人の興味・目的が中心ですが、親はそれに共感しサポートする存在であり続けます。決して直接干渉せずとも、親の期待や応援は心の支えになりますし、ふとした助言が新たな学びの方向を示すこともあります。大学生になった子どもに対しても、親が教育的パートナーである姿勢を保つことが、子どもを勉強好きな大人へと導く一助となるでしょう。
親の関わり方と環境支援
大学生への親の関わり方は、基本的に「見守り」と「経済的・精神的支援」が中心です。勉強内容に口出しすることはほぼ無くなりますが、保護者として適切な環境を提供する責任は残ります。まず経済的支援として、学費はもちろん、必要な教材や留学・研修など子どもの希望する学びの機会に可能な範囲で資金を出すことです。これは直接には環境要因ですが、子どもの学習意欲に直結します。例えば、「大学院に進みたい」と相談されたら、家庭の事情が許す限りサポートを約束しましょう。親が投資を惜しまない姿勢を見せると、子どもも「応えたい」と一層努力します。ただし、経済力には限界もありますから、無理な場合は正直に話し合い、奨学金などの情報を与えて自立を促すことも必要です。それも一つの人生経験です。
精神的支援では、親子の良好な関係の維持が何より大切です。大学生になると一人暮らしをする子も多く、親と距離ができます。定期的に連絡を取り、「ちゃんと食べてる?」「最近どう?」と気にかけるようにしましょう。子どもは鬱陶しがるかもしれませんが、内心気にしてくれることを嬉しく思っているものです(頻度は子どもの性格に合わせます)。帰省した際には話をじっくり聞いてあげます。ここまで大きな問題なく育ったように見えても、大学生は将来への漠然とした不安を抱えていることもあります。そうした気持ちに共感し、「これまでも頑張ってきたんだから、きっとできるよ」と励ましつつ、「お父さんお母さんも同じようなことで迷っていたことがあるんだ」などエピソードを共有すると、自分だけじゃないんだと安心します。親が人生の先輩として相談に乗る場面も増えるでしょう。キャリア、人間関係、社会のことなど、子どもから相談されたら親身になって答えます。答えが無くても一緒に考えるスタンスが重要です。それが結果的に子どもの学業や挑戦への意欲を保つ背景支援となります。
学習環境について、大学生は自宅外で過ごす時間も長いですが、実家にいる場合は引き続き集中できるスペースを提供します。特に卒業論文や研究で追い込み時期には、自宅で徹夜作業することもあります。その際、静かな夜の環境や夜食の差し入れなど、親ができる範囲でサポートしましょう。逆にずっと自室にこもって疲弊しているようなら、適度に声をかけ気分転換を勧めます。精神面のフォローも含め、家庭が安らげる場所であるよう努めます。一人暮らしの場合、親は直接環境を整えてあげられませんが、節目節目で部屋を訪ねて生活環境をチェックするのも良いでしょう(嫌がらない範疇で)。散らかっていたら一緒に片付けたり、足りない家具家電があれば提案したり、時には提供したりします。最近ではオンラインで親子がつながりやすいので、ビデオ電話で生活の様子を確認することもしやすくなりました。
大学生にもなると親がいなくても学習環境を自分で整えられるはずですが、親が少し手を差し伸べることで「まだ気にかけてくれている」という安心感を持たせられます。その安心感こそ、勉強や新しい挑戦へのベースになります。例えば、就活で忙しい時期、親から差し入れ食材や家事を楽にする家電などが送られてきたら、子どもはきっと助かるでしょう。そういったさりげない環境支援を続け、苦労している時期こそ気にかけます。
最後に、引き続き親も学び続ける姿勢を見せることは、子どもが勉強好きな大人になる上で意外に大きな影響があります。大学生ともなると、親の考え方や生き方を冷静に見ているものです。もし親が全く新しいことを学ぼうとはせず、知的好奇心を示さない人なら、子どもは潜在的に「大人になれば勉強はしなくなるものだ」と思っているかもしれません。逆に親が社会人大学院に通ったり、新しい趣味(ガーデニングやプログラミングなど何でもいいのです)に熱中したりしていると、「大人になっても学ぶことはあるし、何より楽しそうだ」と感じ取っているはずです。例えば、親が英会話を習って旅行で実際に現地の人と会話した話や健康のためヨガを始めて体調が良くなった話などをすれば、子どもにとっては生涯学習のロールモデルとなります。精神科医としての視点でも、親が自己成長を楽しんでいる家庭は子どもの自己肯定感が高く、知的好奇心も豊かになりやすい印象があります。ぜひこの記事を読んでくださっている親御さん自身も学びを楽しんでください。それが巡り巡って、お子さんが大学を卒業し社会に出た後も「学ぶって面白いし大事だ」と思い続ける原動力になるでしょう。
大学生(18歳以上)
- 脳の発達
- 25歳頃に脳が成熟するが、神経可塑性は継続し、新しい知識に適応する。
- 高度な批判的思考力や問題解決能力が育ち、「大人」に近づいていく。
- モチベーション
- 内発的動機が主体であり、新しいモチベーションを見つけていく必要がある。
- 自己効力感が学びの持続力に直結し、「自分で学び続ける」精神を養う。
- 親の関わり方
- 基本的に見守りつつ、精神的・経済的支援を適宜行う。
- 親自身も新しいことを学び、楽しむ姿勢を見せ続ける。
- 学習環境
- 自己管理が基本だが、必要に応じたサポートも行う。
- 忙しい時期こそ、さりげない支援で環境を整えて精神面のフォローも。
参考文献・情報源
参考文献・情報源
- 乳児期の脳発達
- Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (Eds.). (2000). From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. National Academy Press.
- Johnson, M. H. (2005). Developmental Cognitive Neuroscience. Wiley-Blackwell.
- 内発的動機づけと報酬系
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.
- Galván, A. (2013). The Teenage Brain: Sensitivity to Rewards. Current Directions in Psychological Science, 22(2), 88-93.
- Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627-668.
- 学習環境と家庭の影響
- Evans, G. W., & Wachs, T. D. (Eds.). (2010). Chaos and Its Influence on Children’s Development: An Ecological Perspective. American Psychological Association.
- Sanders, M. R., & Mazzucchelli, T. G. (2013). The Power of Positive Parenting: Transforming the Lives of Children, Parents, and Communities Using the Triple P System. Oxford University Press.
- 学習習慣と学力
- Dweck, C. S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. Random House.
- Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. P. (2005). Self-Discipline Outdoes IQ in Predicting Academic Performance of Adolescents. Psychological Science, 16(12), 939-944.
- Heckman, J. J., & Kautz, T. (2013). Fostering and Measuring Skills: Interventions That Improve Character and Cognition. NBER Working Paper No. 19656.
- 睡眠と学習の関係
- Walker, M. P. (2017). Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams. Scribner.
- Carskadon, M. A., & Tarokh, L. (2014). Developmental changes in circadian biology and sleep regulation. In G. G. National Research Council (Ed.), Sleep Disorders and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem. National Academies Press.
- 思春期の脳の発達
- Blakemore, S. J., & Mills, K. L. (2014). Is Adolescence a Sensitive Period for Sociocultural Processing? Annual Review of Psychology, 65, 187-207.
- Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The Adolescent Brain. Annals of the New York Academy of Sciences, 1124(1), 111-126.
- 家庭の学習支援と親の関わり
- Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1989). Parent Styles Associated with Children’s Self-Regulation and Competence in School. Journal of Educational Psychology, 81(2), 143-154.
- Pomerantz, E. M., Moorman, E. A., & Litwack, S. D. (2007). The How, Whom, and Why of Parents’ Involvement in Children’s Academic Lives: More Is Not Always Better. Review of Educational Research, 77(3), 373-410.