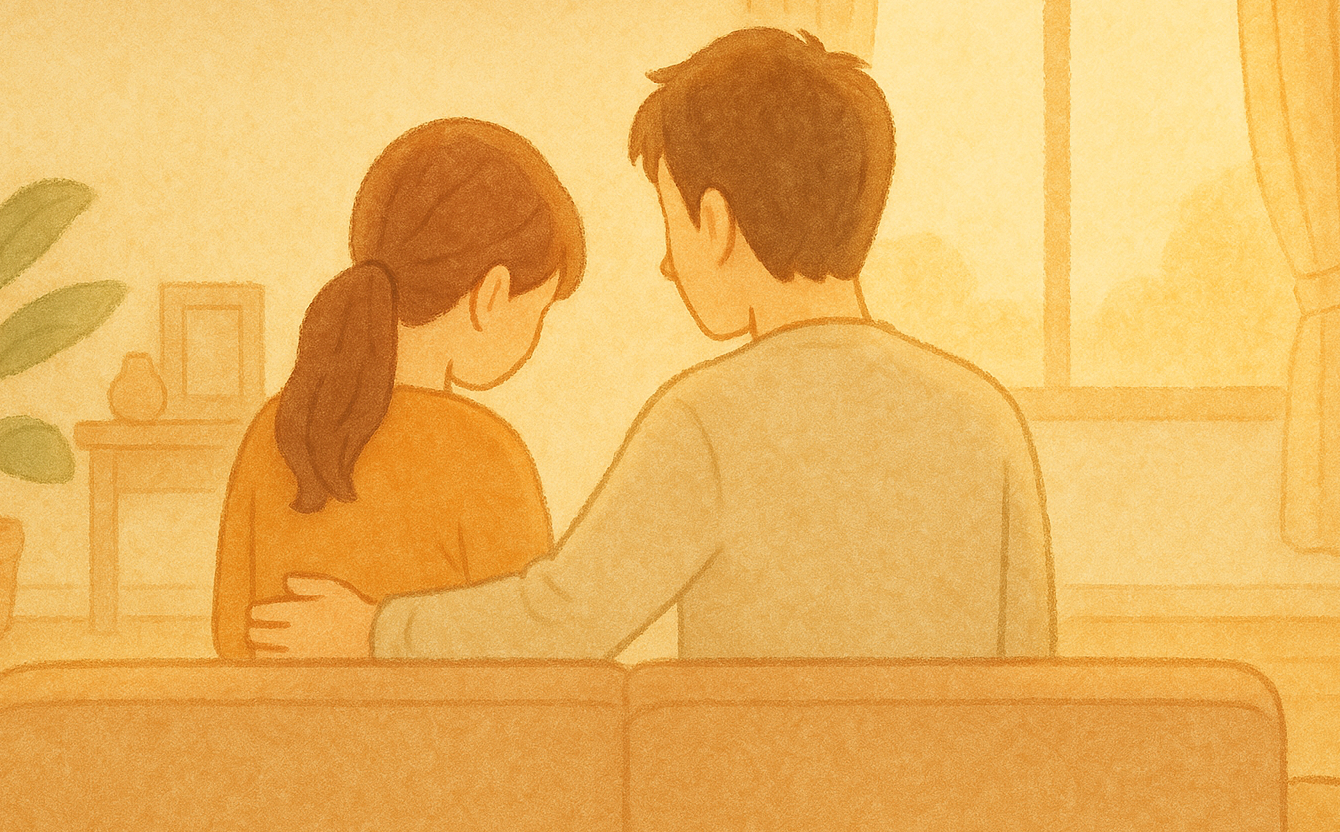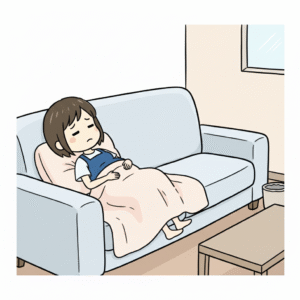こんにちは、Dr.流星です。
つわりの時期は、妊婦さんご本人だけでなく、その周囲で支えるパートナーや家族にとっても大きな試練です。実際、身近な方のちょっとした気遣いや具体的なサポートがあるだけで、妊婦さんの精神的な負担は大きく軽減されます。しかし、どう接したらいいのか分からず悩んだり、無意識のうちに妊婦さんを傷つけてしまう支援者も少なくありません。
私自身、日々の診療で「支援者の一言や行動が、妊婦さんの心に想像以上の影響を与えている」と実感する場面にたびたび遭遇します。時には「それは辛くて当然ですね……」と思わず同情してしまうケースも。けれど、サポートを頑張ろうと努力している方々も本当に多いのです。「何をしたらいいのか分からない」「どんな声掛けが良いのか迷う」という悩みは、ごく自然なものです。
この記事を読んでくださっている方は、「妊婦さんの力になりたい」「少しでも良いサポートをしたい」と思っているはず。そんな前向きな気持ちを後押しできるよう、支援者が避けるべきNG行動や、実際に役立つサポート方法、声掛けのポイントなどを、精神科医の視点からわかりやすく解説します。つわりの時期は家族みんなにとって“特別な非常事態”。みんなでチームになって、この大切な時期を乗り越えていく意識が重要です。
それでは、詳しく見ていきましょう。
「つわり時期」のパートナー・支援者の対応
家事・育児の肩代わり
つわり中の妊婦さんにとって一番大切なのは身体を休めることです。特に妊娠初期は仕事を続けている方も多く、家に帰るとクタクタという場合もあります。パートナーは積極的に家事を引き受けて、妊婦さんが遠慮なく休める環境を整えることが大切です。食事の用意(テイクアウトや宅配の利用も検討)、部屋の掃除・片付け、洗濯など、できることは率先して行いましょう。上の子がいる場合は一時的に実家の力を借りたり、ファミリーサポートを利用するのも有効です。パートナーさんも「自分一人で全部やらなきゃ」と思い込まず、外部の家事代行サービス等に頼ることも検討してください。とにかく妊婦さんが安心して横になれる時間を増やすことが、家族として最優先のサポートです。そのためにも日頃から家事を一緒にしておいて、何をどこに片付けるのか、この家事で気を付けるべきポイントは何なのかを共有しておくことが大切ですね。
思いやりの言葉かけ
パートナーの何気ない一言が、つわりで弱っている妊婦さんの心を大いに救います。「大丈夫?無理しないでね」「全然こっちでやっておくから休んでいていいよ」など、ねぎらいと労わりの言葉をぜひ積極的に伝えてください。心の中で心配していても意味がないです。言葉に出さなければ伝わりません。「つらいね、頑張ってるね」と共感する一言や、「少し横になったら?」「何か飲めそう?用意するよ」と優しく促す言葉だけでも妊婦さんは「わかってくれている」と感じ、安心できます。考え方を替えれば、「この人がパートナーでよかった」と思ってもらう絶好の機会でもあります。ここが頑張りどころです。反対に「俺には何もしてやれないし…」と黙っている、「声かけてもイライラしてるみたいだし…」と自己防衛に走るのはNGです。どんな言葉でも気遣いが感じられれば十分支えになることを覚えておいてください。また、たとえイライラした口調で返されたとしても「今はホルモン的にも不安定な時期だもんな」と広い心で受け入れる余裕と知識が肝要です。
現在の気持ちや要望を聞く
つわり症状や妊婦さんの欲しいサポートは日によって刻々と変化します(超重要!)。昨日平気だった匂いが今日はダメになったり、求める助けや欲しいものも変わるでしょう。そこでパートナーは「今、何をしてほしい?」「今日はどうかな?」とその都度尋ねる習慣をつけるようにしましょう。「何か手伝おうか?」ではなく、「今一番つらいことは何かな?」「何か食べられそうなものある?飲めそうなものでも」など具体的に問いかけてみましょう。妊婦さんには、「遠慮せずにその時々の希望をしっかり言ってほしい」ことも伝えてください。例えば、「背中をさすってほしい」「コンビニの氷やアイスを買ってきてほしい」「静かに横にいてほしい」等、細かなリクエストに応えることで妊婦さんの負担はぐっと減ります。コミュニケーションを密にすることで、「自分は一人じゃない」という安心感も生まれます。日々の変化に柔軟に対応することで、その後の夫婦生活にも活きるサポート力が身に付いていくはずです。
匂いへの配慮(NG行動の回避)
パートナーが気をつけたいNG行動の筆頭は、強い匂いで妊婦さんを刺激しないことです。具体的には、妊婦さんの前で匂いのきつい物を食べない、調理の際はニンニクや香辛料たっぷりの料理を作らない、魚を焼かない、といった配慮が必要です。場合によってはしばらく白米を控える必要もあるでしょう。どうしても食べたい場合は外で済ませるか、妊婦さんがいない部屋で窓を開ける、換気扇を回すなどして食べるようにしましょう。良かれと思って「スタミナをつけてあげよう」とニンニク料理を作ったら臭いに妊婦さんが耐えられなかった、といった失敗談もあります。また、昨日は平気だった食品でも今日はダメになっている場合があります。何の匂いが辛いのか、その都度妊婦さんに確認することも大切です。匂い関連でもう一つ、パートナー自身のタバコやお酒の匂いにも注意してください。妊娠中は受動喫煙などあり得ないのはもちろんですが、衣服や息に染み付いたタバコ臭や、飲酒後のアルコール臭も妊婦さんにはきつく感じられます。妊娠を機に禁煙・禁酒を心がけ、少なくとも匂いをプンプンさせて妊婦さんのそばに行くことは控えましょう。匂い(臭い)をきっかけに関係性が悪くなるというのは普段からあるリスクですが、つわり時期には特に気を付けなければいけないことを肝に銘じておきましょう。
自分のことは自分で
妊婦さんに余計な負担をかけないため、パートナー自身の身の回りのことは自分で行う習慣をつけましょう。脱いだ服を脱ぎっぱなしにしない、部屋を散らかさない、食器は流しに運ぶ等、当たり前のことですが妊娠中はちょっとしたことで妊婦さんはイライラしてストレスが溜まっていくため、一層徹底します。「君が休んでいる間くらい自分のことは自分でするよ」「いつもありがとう」という姿勢を見せるだけでも、妊婦さんは安心して休めますし、産後の共同育児の予行演習にもなります。
一人にしない・寄り添う
つわり中、特に週末などパートナーが家にいるときはできるだけ妊婦さんと時間を共に過ごすよう心がけましょう。妊婦さんが家で苦しんでいるのに、自分だけ頻繁に飲み会に出かけたり趣味に没頭したりするのは避けるべきです。もし自分が高熱で苦しんでいるときにパートナーが遊びに出かけてしまったら…と想像すれば、その寂しさや不満は理解できるでしょう。もちろんパートナー自身も適度にリフレッシュは必要ですが、会社の上司や同僚にも「今、妻がつわり中で…」と事情を話しておき、1分でも早く帰宅して、帰宅したら妊婦さんに「大丈夫だった?」「今日はどんな感じ?」と声をかけ、できる範囲で側にいてあげてください。つわり時期の妊婦さんにとっては一緒にテレビを見るだけでも心強いものです。「辛いときに優しくしてくれた」という記憶は、きっと夫婦の絆を深めることにつながります。逆にこの期間のサポート不足は一生言われ続けることになりますよ……
共感と称賛・感謝の言葉を忘れずに
『思いやりの言葉かけ』と重なる部分はありますが、苦しそうな妊婦さんを見て「つわりなんだから仕方ない」と放置・楽観視するのではなく、積極的に共感を示す態度が大切です。妊婦さんが吐いて苦しんでいるとき、「見ていられなくて…」「苦しいところを見られるのは嫌なんじゃ…」と逃げたり目を背けたりするのでなく、背中をさすってあげたり、「辛いよね」「一緒に乗り越えようね」と共感して励ましの言葉もかけましょう。どんなに些細なことでも「ありがとう」「助かるよ」と伝え、妊婦さんの努力を認める言葉かけをしてください。つわりを夫婦で乗り越えた経験は、出産・育児という次の試練に向かう上で大きな自信と信頼感につながります。
おわりに
以上、パートナーや家族ができるサポートについて述べました。要は「妊婦さんの立場に立って考える」ことが何よりも大切です。つわりの辛さは本人しかわからない部分もありますが、想像力を働かせて最大限の気遣いをしましょう。妊婦さんも遠慮せず「こうしてくれると助かる」と伝えてください。お互いの理解と協力があれば、つわりの時期を乗り越えることができるはずです。
つわりは決して楽なものではありませんが、適切な対処法と周囲のサポートで乗り切ることができます。医学的に裏付けられた対策を試しつつ、心のケアも怠らず、妊婦さんを甘やかすくらいの気持ちで過ごしてください。つわりを経験した多くの先輩ママ・パパ達も、同じような不安や苦労を乗り越えてきました。つらいときは周囲に頼り、少しでも笑顔になれる瞬間を大切にしてください。いつか振り返ったとき、「あの時は大変だったけど頑張って良かったな」と思える日がきっと来ます。
今はどうか妊婦さんにはご自愛いただき、あなたと赤ちゃんの健やかな毎日を第一にお過ごしください。パートナーや支援者の方々も、一緒にこの試練を乗り越え、素晴らしい新しい命の誕生を迎えられることを願っています。

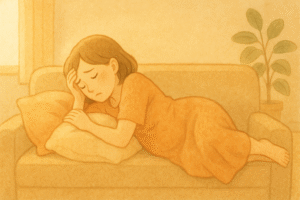
参考文献・情報源
- 日本産科婦人科学会「産科診療ガイドライン-産科編2020」
- 日本産婦人科医会「つわり(妊娠悪阻)に関するQ&A」
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「妊娠悪阻」
- ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists): Morning Sickness: Nausea and Vomiting of Pregnancy. FAQ126. 2021.
- NIH (National Institutes of Health): Nausea and vomiting of pregnancy – MedlinePlus
- NICE guideline [CG62]: Antenatal care for uncomplicated pregnancies (National Institute for Health and Care Excellence)
- Maternal Mental Health Alliance: Hyperemesis Gravidarum and mental health (2023)
- PR TIMES「妊婦の約9割がつわりを経験、約半数が精神的に不安定に。『つわり』に関する意識調査」2023年
- 兵庫県立大学 地域ケア開発研究所「つわり症状の軽減法と支援」2022年
- 産婦人科オンラインジャーナル「妊娠中の不安な気持ちの対処法」2022年
- Better Health Channel (Australia): Pregnancy – morning sickness
- Smith, C.A., Crowther, C.A., Willson, K., et al. “Aromatherapy for nausea and vomiting in pregnancy.” Cochrane Database Syst Rev. 2020.
- Duke, A. et al. “Management of Nausea and Vomiting in Pregnancy.” Am Fam Physician. 2021; 103(5): 277-284.
- Dean, C., Shemar, M., & Gill, P. “Hyperemesis gravidarum and risk of psychological distress, depression and anxiety: A systematic review.” Pregnancy Hypertens. 2021; 25: 179-186.
- 厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」
- 公益社団法人 認知行動療法学会
- オーストラリア産科新生児学会「Morning sickness in pregnancy」
- Seabergh, B. et al. “Ginger for nausea and vomiting in pregnancy.” Obstet Gynecol. 2020; 135(5): 1108-1115.