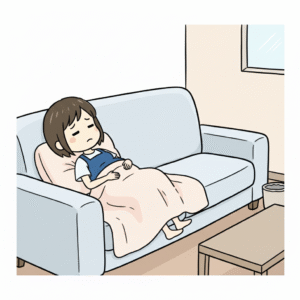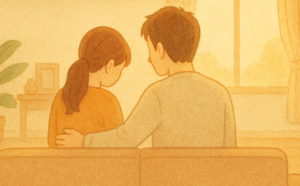こんにちは、Dr.流星です。
「つわり」(妊娠悪阻を含む)は、多くの妊婦さんやそのご家族にとって身近でありながら、不安や悩みの種にもなりやすいものです。実際、私の妻も重いつわり――特に妊娠悪阻に苦しみ、入院を検討するほど大変な経験をしました(その時に私たちが試したことや感じたことは、別の記事で改めて紹介できればと思っています。妻にも体験談を書いてもらう予定です)。
つわりは、日常生活や気持ちにも大きな影響を与えるため、悩まれている方も多いと思います。今回から数回に分けて、「つわり」について分かりやすくまとめていきます。第1回は「つわりを正しく知り、どう向き合うか」についてです。
「対処法だけ知りたい!」という方は、ぜひ目次から気になる項目にジャンプしてご活用ください。
それでは、本題に入っていきましょう。
はじめに
妊娠初期の「つわり」は、多くの妊婦さんにとって避けられない試練です。実際、ある調査では妊婦の9割以上が何らかのつわり症状を経験したと報告されています。吐き気や嘔吐といった身体症状だけでなく、精神的にも不安定になることがあり、妊婦本人も周囲の家族も戸惑うことが少なくありません。本シリーズでは、精神科医の視点からつわりの代表的な症状と症状別の科学的に裏付けられた軽減方法を解説し、さらにつわり時期の心理的影響や不安を軽減する考え方・心理的アプローチ、リフレッシュに役立つセルフケア、そしてパートナーや家族ができる具体的な支援と共感的対応について、最新の医学的エビデンスに基づきながらわかりやすく紹介します。つわりと上手に付き合い、心と体の負担を減らすためのヒントになれば幸いです。
つわりの代表的な症状
そもそも「つわり」とは主に妊娠初期(概ね妊娠5〜16週)にみられる症状の総称で、個人差は大きいものの、多くの妊婦さんが経験します。一般的に妊娠8〜10週頃に症状がピークとなり、12〜16週頃には落ち着いていく場合が多いと報告されています。代表的な症状には以下のようなものがあります。
吐き気(悪心)・嘔吐
胃のむかつきや吐き気、実際に嘔吐してしまう症状です。朝起きた直後や空腹時に強く出ることが多く、重い場合は一日中続くこともあります。程度は様々で、軽い吐き気のみの人もいれば、1日に何度も嘔吐して日常生活に支障を来す人もいます。特に重症の場合は「妊娠悪阻(にんしんおそ、Hyperemesis Gravidarum)」と呼ばれ、全妊娠の約1〜3%にみられます。妊娠悪阻では体重減少や脱水を伴い、入院治療が必要になることもあります。
匂いに敏感になる
普段は気にならない食べ物や匂いに強く反応し、吐き気が誘発されることがあります。例えば、ご飯の炊ける匂いや肉・魚の匂い、タバコや香水の匂いなどに極端に敏感になります。つわりの時期は嗅覚が鋭敏になり、特定の匂いが突然ダメになる妊婦さんも多いです。中には、どんな食べ物の匂いでも気分が悪くなるという方も。ある調査では「匂いに敏感になる」症状を経験した妊婦さんは全体の67.2%であったとの報告もあります。
食欲不振・嗜好の変化
食べ物の好みが変わり、特定の食品を受け付けなくなったり、逆に特定の物ばかり食べたくなることがあります。例えば、今まで好きだった料理やお菓子が急にダメになったり、炭酸飲料(それこそ炭酸水だけなど)や酸味のある果物だけが口にできる、といったケースです。約半数の妊婦さんが何らかの食欲減退や嗜好変化を経験し、「昨日は食べられたものが今日はダメ」など日によって変化するということも珍しくありません。一方で、中には「食べつわり」といって、「空腹になると気持ち悪くなる」ため、常に何か食べていないと落ち着かず、食欲が増進するタイプの方もいます。
唾液過多
妊娠中に唾液の分泌が増えてしまい、常に唾を吐き出したくなる症状です。これはよだれづわりとも呼ばれ、唾液を飲み込むと吐き気が悪化するため、常にティッシュや容器で唾を吐き出している妊婦さんもいます。そのため、外出を渋ってしまう場合や支援者に「汚いと思われてないかな」と心配になってしまう場合もあり、生活や人間関係にも支障をきたしうる症状です。また、就寝中も唾液があふれて、唾液に溺れて眠れないほど悩まされるケースもあります(夜間のむせ込みや不快感)。
強い眠気・倦怠感
異常なほどの眠気やだるさに襲われることがあります。妊娠初期は黄体ホルモン(プロゲステロン)の急増により、日中でも眠気が強くなり、体がだるく感じられます。これは、仕事や家事の最中でも集中力が続かず、常に疲労感がある状態で、決して怠けているわけではないのに何もできず、悩む方も多い症状です。ある調査では「眠気」を訴える妊婦さんが6割近くに達していたとの報告もあります。
胸やけ・消化不良
胃酸過多や消化機能の変化により、胃もたれや胸やけを感じる人もいます。食後に胃のあたりがムカムカしたり、げっぷや胃酸の逆流による喉の灼熱感が出ることがあります。妊娠中は消化管の動きがゆっくりになるため、こうした症状が現れやすくなります。
情緒不安定(心理的症状)
ホルモンバランスや体調の変化から、イライラしやすくなったり、不安感や落ち込みといった心理的不安定さを感じる場合があります。妊娠初期の急激なホルモン変化(特にプロゲステロン増加)は、ちょっとしたことでイライラしたり憂うつになる原因となり得ます。そのため、「嬉しいはずの妊娠なのに気分が晴れない」「自分だけ取り残されているようで孤独」といった感情が湧くことも珍しくありません。この心理的な揺らぎも広い意味で“つわり”の一部と考えられており、実際に約4割の妊婦さんがつわり中に精神面の不調を経験したとされています。
以上のように、つわりの症状は多岐にわたり、個人差は大きく、人それぞれ異なります。一部の幸運な妊婦さんはほとんど症状が出ないこともありますが、大半は何らかの不快症状に悩まされます。
では、それぞれの症状にどのように対処したら緩和できるのか。次章でそれぞれの症状を少しでも和らげるための具体的な対処法を、科学的根拠に基づいて見ていきましょう。
症状別の科学的に裏付けられた軽減方法
さて、つわりの辛さを軽減するために、近年では様々な対策が研究されています。ここでは代表的な症状ごとに、医学的・科学的根拠に基づいた緩和策を紹介します。民間療法とは異なり、現在の正しい症状に応じた薬物療法と非薬物療法の双方を上手に活用することで、つわりと付き合いやすくなると思います。
吐き気・嘔吐への対処法
食事療法(少量頻回食)
妊娠初期の吐き気には、まず食事の摂り方を工夫することが効果的です。一度にたくさん食べようとせず、1日4〜5回程度の少量頻回食にすると胃の負担が軽減され、空腹による吐き気悪化を防げます。特に夜から朝まで長時間何も食べないと朝一番に強い吐き気が出やすいため、就寝前や夜中に軽い夜食(例えば、小さなおにぎりやビスケット、チーズやヨーグルトなどの乳製品など)を口にするのも有効です。朝は布団の中で乾いたクラッカーやビスケットを少し食べてから起き上がると、急な吐き気を予防できます。
避けた方が良い食品
食事内容にも注意しましょう。脂っこい揚げ物や香辛料の強い刺激物は吐き気を誘発しやすいため、つわり中はできるだけ避けることが望ましいです。比較的食べやすいのは消化によい炭水化物やタンパク質で、例えば、バナナ、お粥、トーストなど消化しやすい物がおすすめです。うどんなどは消化がいいように思われるかもしれませんが、よく噛まなければ逆に消化が悪い、というものも多数あるため注意が必要です。胃に長く留まらない高炭水化物の軽食(クラッカー、果物、シリアルなど)は比較的よく受け付けられますので、好みに合わせて用意しておくことをお勧めします。一方、いろいろと試す中で「これなら食べられる」というものが見つかったら、栄養や消化がいいかなどは気にせず、それを少量ずつ摂るのも良いでしょう(たとえ栄養バランスが偏っても、「食べられる」「飲める」ものを優先します)。
水分摂取と嘔吐後のケア
脱水は吐き気を悪化させるため、こまめな水分補給が大切です。一度に大量に飲むと吐いてしまう場合は、氷を舐めたりスポーツドリンクを少しずつ飲むなど工夫が必要かもしれません。嘔吐が頻回にある方は、胃酸で歯のエナメル質が傷つかないよう吐いた後に重曹水で口をゆすぐのも有効です。コップ一杯の水に重曹小さじ1を溶かした液で口をすすぐと胃酸を中和でき、不快感も軽減できます。また、嘔吐が続くと体内の電解質バランスが崩れ、不調の要因にもなります。理想では経口補水液(OS-1など)を嘔吐後に胃が落ち着いてから(15~30分程度休んでから)摂取できればよいのですが、飲水すらもままならない場合は医療機関を受診して点滴をしてもらうことも考える必要があるます。
ショウガ(生姜)の活用
ショウガは古くから吐き気止めに効くとされ、近年の研究でもショウガ自体や生姜サプリメントの摂取が妊娠に伴う軽度の吐き気・嘔吐を和らげる可能性が示唆されています。これは、生姜に含まれる成分(ジンゲロールやショウガオールなど)が胃腸の働きを調整すると考えられていることによります。実際、生姜粉末のカプセルや生姜入りキャンディー、ジンジャーティーなどは試す価値があるでしょう。ある文献では「1日1〜1.5g程度のショウガ」が安全量とされていますが、ショウガを多めに食べようと考えている場合やサプリメントを使う場合は必ず事前に医師に相談してください。なお、ジンジャーエールを飲む場合は本物の生姜を使ったものにしましょう(人工的な香料のみを使用しているものも多く、それらでは効果が期待できません)。
ビタミンB6と薬物療法
食事や生活改善でも吐き気がつらい場合は、遠慮なく産婦人科医に相談しましょう。安全に使えるお薬もあります。まずビタミンB6(ピリドキシン)は比較的安全な妊娠悪阻治療の第一選択肢で、つわり症状の緩和に効果があるとされています。さらに抗ヒスタミン薬であるドキシラミン(睡眠改善薬の成分)を併用すると効果が高まることが示されています。海外ではビタミンB6+ドキシラミン配合薬が処方されていますが、日本でも医師の判断でビタミンB6製剤や抗ヒスタミン薬が用いられることがあります。これらは胎児への有害影響もないと報告されています。
抗吐剤(制吐剤)の使用
ビタミンB6や抗ヒスタミン薬でも症状が治まらない重症例では、医師が制吐薬を処方することもあります。代表的な制吐剤には、妊娠悪阻でよく使われるメトクロプラミド(プリンペラン)やプロクロルペラジン、場合によってはオンダンセトロンなどがあります。ただし一部の薬(特にオンダンセトロン)は胎児への安全性について議論があり、心電図への影響も報告されているため医師と利益およびリスクをよく相談して使用する必要があります。総じて、多くの制吐剤は妊娠中でも安全に使用できるとされますが、薬の選択は主治医(産婦人科)の指示に従いましょう。
匂い過敏(においつわり)への対処法
換気と空気環境の工夫
強い匂いで吐き気が誘発される「においつわり」には、こまめな換気が基本です。自宅では窓を開けて新鮮な空気を取り入れ、台所や部屋に匂いがこもらないようにしましょう。しかし、住んでいる環境によっては外部からのにおいが強かったり、道路が近くて新鮮な空気とは言えないご家庭もあるかもしれません。そういった環境には機能性の高いエアコン(フィルター清掃なども重要)や空気清浄機の活用も効果的です。また、外出先でもマスクを着用すると匂い刺激が和らぎます。唾液が多くなっている方はマスクの替えも持って外出することをお勧めします。
匂いの原因を減らす
ご家族やパートナーには、香水・整髪料・柔軟剤など強い香りの製品を控えてもらうようお願いしましょう。特に柔軟剤が使えなくなる方は多いかもしれません。石鹸や洗剤も無香料タイプに切り替えると安心です。調理中の匂いが辛い場合は、できれば調理そのものを避けて他の人に料理を代わってもらうか、調理時に換気扇を強めに回す・扇風機や卓上ファンで匂いを吹き飛ばすなどしてみてください。どうしても難しい場合は、料理は電子レンジ調理や出来合いの物を利用し、火を使う時間を短縮するのも一策です。次の「冷たい食事」も検討してみましょう。
冷たい食事の活用
温かい料理は湯気とともに香りが立ちやすいですが、冷たい食品や常温の食品は匂いが弱く感じられます。例えば、温かいスープより冷製スープ、ホットミールより冷やし麺やサンドイッチなど、匂いの少ない状態で食べられるものを選びましょう。どうしても温かい食事を摂りたいときは、香辛料を活用したり、少し冷ましてからゆっくり食べたりすると匂いが和らぎます。
口の中の匂い対策
食後に口の中に残る味や匂いが気持ち悪い時は、すぐ歯みがきをするかマウスウォッシュでうがいするとスッキリします。実際、うがいや歯磨きの頻度は自然と増えているかもしれません。レモン水で口をすすぐのもサッパリしておすすめです。また、口の中が常にさっぱりするよう、ミント系ガムやタブレットを試す妊婦さんもいます(ただしメントールの強い刺激がダメな方もいるので、自分に合うものを探してみましょう)。メントール系のリップクリームや鼻の下に塗るクリームを使用する人もいるようです。
強い眠気・倦怠感への対処法
睡眠リズムを整える
妊娠初期はホルモンの影響で眠気が出やすいですが、生活リズムを規則的にすることで多少緩和できます。具体的には「朝起きたら太陽の光を浴びる」「夜は就寝前に強い光(スマホやPC画面)を見ない」など、昼夜のメリハリをつけることを意識しましょう。これらの習慣は当たり前と言えば当たり前なのですが、意外とできていない人は多いです。日中に可能であれば軽い運動(散歩やストレッチ)を取り入れると体内時計が整いやすくなります。どうしても午後に眠い時は、20〜30分程度の昼寝など夜間の睡眠に影響がない程度の昼寝を取り入れます。可能なら16時以降の昼寝は避けるようにしましょう。
休息を最優先に
強い眠気や疲労感を覚えるときは、無理に動かず思い切って休むことが大切です。家事や仕事の途中でも、「少し横になる」「椅子に座って目を閉じる」など短時間でも休憩を挟みましょう。眠れずとも脳への刺激を減らすことで休息につながります。特に眠気が強いまま無理に車の運転をしたり高所の作業をしたり精密機械の操作をしたりすると、思わぬ事故につながる危険があります。妊娠中の自分と赤ちゃんを守るためにも、「怠けているのではなく必要な休息なんだ」と割り切って休みを確保するようにしてください。
栄養と水分補給
極度の倦怠感を感じるときは、もしかすると貧血や脱水が隠れている可能性もあります。つわりで食事が十分摂れていない場合、鉄分やミネラル不足で余計にだるくなることがあります。鉄分豊富な食品(レバー、ほうれん草、赤身の肉など)やサプリの活用について、産科で相談しても良いでしょう。また少量でも水分とカロリーを摂っておくと最低限の体力が保てます。スポーツドリンクやゼリー飲料の他、それぞれの食べられる・飲み込めるもので補給しましょう。
心理的な不安・イライラへの対処法
心療内科的アプローチ
つわりによる不安や抑うつ感が強い場合に取り入れられる専門的な心理療法をご紹介しておきます。まず、認知行動療法(CBT)的なセルフケアとして、自分の思考パターンを見つめ直す方法があります。不安や自己嫌悪につながる考えが浮かんだとき、「それは本当に自分に当てはまるのか?」「元々の自分はそうじゃないだろう」と立ち止まり、より前向きで現実的な捉え方に置き換えてみます。例えば、「何もできない自分はダメな母親だ」と落ち込んだ際には、「いい母親になろうって決めたばかりじゃないか」「今は赤ちゃんのために自分を大切にして休むことが一番大事」「つわりは一時的なもの、いずれ終わる」「つわりが終わったら子育てグッズを買いに行く!楽しみ!」と考え直してみましょう。実際、妊娠悪阻の当事者支援団体は「つわり(特に重度のもの)はあなたの責任ではなく、妊娠に伴う医学的状態である」と強調しています。決して自分を責めず、「今は治療と休養が必要な時期だ」と割り切ることが大切です。また、つわりの時期が終わったあとに自分なりのご褒美(報酬)を用意しておくことも辛い時期を乗り越える支えになります。
情報との適度な距離
インターネットや書籍でつわりに関する情報収集をするのは有益ですが、他人の体験談と自分を過度に比べないようにしましょう。「○週で終わるはずなのに自分はまだつらい」「○○さんは仕事を続けているのに自分は休んでいる」などと考えると余計にプレッシャーになります。つわりの経過は人それぞれで個人差が非常に大きいです。「自分は自分」と割り切り、心配なことは主治医に直接相談する方が確実です。また、周囲に理解が得られず孤独に感じる場合は、産科の助産師さんや妊婦向けの電話相談(自治体や専門機関が実施)を利用し、気持ちを話してみてください。周囲や専門家に気持ちを打ち明けるだけでも安心感が得られることがあります。
アロマセラピー(芳香療法)
精神的な不安やイライラの軽減には、アロマセラピー(アロマオイルの芳香浴)が効果的であるとの研究報告があります。明治国際医療大学の研究では、妊娠期のセルフケアにアロマを取り入れることで不安感が有意に軽減したとされています。特に効果が実証されたのはラベンダー、プチグレン、ベルガモットの3種類の精油で、これらの香りにはリラックス効果が高いことで知られます。好きな香りのアロマオイルをティッシュに1滴垂らしてそばに置いたり、ディフューザーで焚いたりしてみましょう。ただし、つわり中は匂いに敏感になっているため、アロマの香り自体がダメな場合もあります。気分が悪くならない香りを選び、様子を見ながら少しずつ試すことがポイントです。
おわりに
今回は、「つわり」について、まずは正しく知ることに焦点を当ててお話ししました。
つわりは個人差が大きく、多くの妊婦さんにとって本当に辛いものです。喜ばしいはずの妊娠がこの時期には思いがけずネガティブな気持ちにつながってしまうかもしれませんが、つわりを乗り越えることで、きっとまた前向きな気持ちで子育てに向き合える時期がやってくるはずです。
つわりで悩む妊婦さんはもちろん、周囲で支えるご家族やパートナーの方にも、「つわり」について理解し、それぞれに合った対処法を一緒に考えていただければと思います。
次回は、精神的な側面から見た「つわり」や、メンタルケアのポイントについてお伝えする予定です。少しでも参考になれば幸いです。
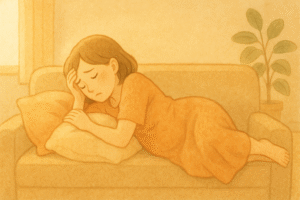
参考文献・情報源
- 日本産科婦人科学会「産科診療ガイドライン-産科編2020」
- 日本産婦人科医会「つわり(妊娠悪阻)に関するQ&A」
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「妊娠悪阻」
- 厚生労働省「母性健康管理指導事項連絡カード」
- ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists): Morning Sickness: Nausea and Vomiting of Pregnancy. FAQ126. 2021.
- NIH (National Institutes of Health): Nausea and vomiting of pregnancy – MedlinePlus
- NICE guideline [CG62]: Antenatal care for uncomplicated pregnancies (National Institute for Health and Care Excellence)
- Maternal Mental Health Alliance: Hyperemesis Gravidarum and mental health (2023)
- PR TIMES「妊婦の約9割がつわりを経験、約半数が精神的に不安定に。『つわり』に関する意識調査」2023年
- 兵庫県立大学 地域ケア開発研究所「つわり症状の軽減法と支援」2022年
- 明治国際医療大学 看護学部「妊婦へのアロマセラピーの有効性」看護研究学会雑誌 2021年
- 産婦人科オンラインジャーナル「妊娠中の不安な気持ちの対処法」2022年
- Better Health Channel (Australia): Pregnancy – morning sickness
- Smith, C.A., Crowther, C.A., Willson, K., et al. “Aromatherapy for nausea and vomiting in pregnancy.” Cochrane Database Syst Rev. 2020.
- Duke, A. et al. “Management of Nausea and Vomiting in Pregnancy.” Am Fam Physician. 2021; 103(5): 277-284.
- Dean, C., Shemar, M., & Gill, P. “Hyperemesis gravidarum and risk of psychological distress, depression and anxiety: A systematic review.” Pregnancy Hypertens. 2021; 25: 179-186.
- 厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」
- 公益社団法人 認知行動療法学会
- オーストラリア産科新生児学会「Morning sickness in pregnancy」
- Seabergh, B. et al. “Ginger for nausea and vomiting in pregnancy.” Obstet Gynecol. 2020; 135(5): 1108-1115.