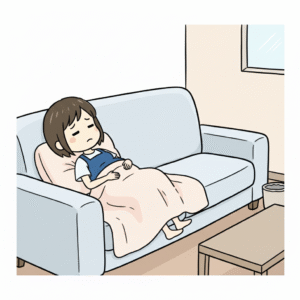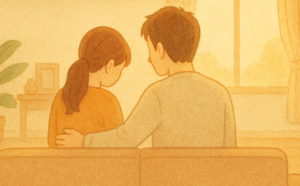こんにちは、Dr.流星です。
前回は「つわり」そのものについてお伝えしましたが、今回はそのつわりが心にもたらす影響――つまり「つわりとメンタルヘルス」について考えていきます。
つわりは身体的につらいだけでなく、妊婦さんのメンタルヘルスにもさまざまな影響を及ぼします。ホルモンバランスの急激な変化や体調不良によって、情緒が不安定になったり、不安や孤独感、無力感を抱いたりすることは珍しくありません。「この苦しみはいつまで続くのか」「赤ちゃんに影響がないか」といった不安が高まり、社会的な孤立感や自己評価の低下につながることもあります。
また、つわりのために仕事や家事が思うようにできない自分を責めてしまったり、些細なことでパートナーに苛立ちを感じてしまうことも自然な反応です。こうした心の揺れや感情の変化は決して特別なことではなく、誰にでも起こりうるものです。
この記事では、つわりがもたらす心の変化や感情の動きを整理し、妊婦さん自身と支援者の双方が理解を深められるようにまとめました。

つわりが心に与える影響
身体的に辛いつわりの時期、妊婦さんのメンタルヘルスにも様々な影響が及びます。ホルモン変化や体調不良により情緒が不安定になることは前の記事で述べた通りですが、それに加えて心理社会的な要因も大きく関与します。ここでは、つわり期間中によく見られる心の変化や感情について整理してみましょう。
不安感の高まり
つわりの時期には「この苦しみはいつまで続くのだろう」「まともに栄養も摂れずに赤ちゃんに影響はないのかな」といった不安が募りやすくなります。特に初めての妊娠でつわりが重い場合、「本当に妊娠を継続できるのかわからなくなってきた……」という心配に襲われるかもしれません。実際、つわりに苦しむ妊婦さんは通常時に比べて不安障害や抑うつ症状が高まりやすいとの報告があります。ただし、つわり自体は身体的なホルモン変化が主体であり、「不安があるからつわりになる」という因果関係は証明されていません。つわりの症状として不安になりやすいのであって、「元々不安になりやすいから」「本人が精神的に弱いから」というわけでは全くないので自分を責めないでくださいね。「つわりの時に不安になるのは当たり前」と妊婦さんも周囲の人も理解しておくことが大切です。
孤独感・孤立感
つわりの症状がひどいと職場を休んだり自宅で寝込んだりすることが増え、外出や社会交流が減ります。その結果、自分だけ取り残されているような孤独感を抱くことがあります。特に周囲につわりの辛さを理解してもらえないと、「誰にもわかってもらえない」という思いから孤立感が深まります。責任感の強い方は「妊娠したせいで周囲に迷惑をかけてしまった」と感じているかもしれません。重度の妊娠悪阻を経験した女性の声として、「ずっと家やベッドにこもらざるを得ず、社会から切り離された気がした」というものがあります。パートナーが仕事で日中いなかったり、両親が遠方に住んでいたりする場合はなおさら孤独を感じやすいでしょう。不安なときはこの孤独感や孤立感がより気分を落ち込ませるものです(次の「抑うつ気分」につながりやすくなります)。
無力感・抑うつ気分
長期間体調不良が続くと、誰しも気持ちが滅入ってきます。周囲には気丈に振る舞っても、思うように動けないもどかしさから無力感を抱いたり、「何もできない自分が嫌」「妊娠前の自分に戻りたい」と涙する妊婦さんもいます。食事が満足にできず体重が減っていくと、「お腹の赤ちゃんに申し訳ない」という罪悪感を感じることもあります。妊娠悪阻のケースでは、あまりの辛さに「こんなに辛いなら妊娠しなければよかった」「もう妊娠を終わらせたい」といったネガティブな考えが浮かぶことさえあり、こうした思考に「お腹の赤ちゃんは頑張っているのに何を言っているんだろう。自分は最低だ」と自己嫌悪を重ねてしまう悪循環も報告されています。また、つわりのために仕事や家事が思うようにできないことから自己評価が下がり、不安や孤独感、無力感も相まって抑うつ状態になるケースもあります。海外の研究では、重度のつわり経験者は出産後も一定割合でPTSD(心的外傷後ストレス障害)に似た症状を示すことが指摘されています。それほどまでに、つわりが心に与える衝撃は大きいのです。この心の変化に妊婦さん自身でも、周囲の支援者も気づいてほしいのです。
苛立ち・パートナーへの怒り
つわりの時期には心の余裕がなくなるため、些細なことでイライラしやすくなります。自分ばかりつらい思いをしていると、「なんで私だけがこんな目に遭うの!」「どうして夫は分かってくれないの!」とパートナーに対して苛立ち、怒りが湧くこともあります。悪気のない一言にもカチンときたり、手伝ってくれない態度に不満をぶつけてしまったりするかもしれません。元々気になることがあった場合はなおさらです。実際、妊娠悪阻の女性たちからは「『妊娠したらつわりは当たり前』と軽く言われて腹が立った」「夫が平気な顔で食事しているのが許せなかった」といった声も聞かれます。まあ、配慮が足りない夫にも悪い点はあると思いますが、これは決して異常な反応ではなく、身体的・精神的に極限状態にあるということの裏返しなのです。この点は妊婦さん自身は「イライラして仕方ない」状態なので、周囲の支援者(特に同居家族)が特に配慮して、適切な対応を心掛けておく必要があるところです。
以上のように、つわりは妊婦さんのメンタルにも様々な影を落とします。しかし大切なのは、「こう感じてしまう自分はおかしいのでは?」と思わないことです。妊娠中は誰でも多かれ少なかれ情緒不安定になりやすく、ホルモンの作用でイライラや落ち込みが起こるのは自然なことです。つわりの辛さゆえのネガティブな感情は、一時的な反応に過ぎません。「喉元過ぎれば熱さを忘れる」とも言いますが、この時期を乗り越えてしまえば、自然と回復するものでもあります。
次章からは、妊婦さん本人がこうした不安や落ち込みに対処し、少しでも心を楽にするための考え方やセルフケアについて具体的に紹介します。支援者の対処や心がけについては別の記事でまとめたいと思います。
妊婦さん本人の不安を軽減する考え方・心理的アプローチ
つわりの時期を穏やかに乗り越えるためには、妊婦さん自身の「心の持ち方」も大きな助けになります。不安やストレスをゼロにすることは難しいですが、ものの見方を少し変えるだけで気持ちが軽くなることがあります。ここでは認知行動療法的な視点も取り入れながら、具体的な心理的アプローチをまとめます。
「これは一時的なもの」とはっきり理解する
つわりの苦しさは永遠に続くわけではありません。多くの場合、妊娠4ヶ月頃(16週頃)までにはほとんど症状が和らぎます。多くの方は10週~12週頃から症状が軽くなっていることを実感できるでしょう。今は長い暗いトンネルの中にいるように感じても、いずれ出口が見えてトンネルを抜ける時が来ると考えましょう。「赤ちゃんが成長している証拠」と前向きに捉える考え方もあります。実際、中等度のつわりがある妊婦は流産率が低いという研究もあり、辛い症状がある分お腹の赤ちゃんは順調なのだと考えると少し救われるかもしれません。もちろん、症状が重すぎる場合は妊婦さんにも危険が及ぶ可能性があるので、無理せず医療機関で点滴などの適切な治療を受けてください。
胎児への影響を正しく知る
嘔吐が続くと「栄養が取れず赤ちゃんが心配…」と不安になりますが、軽度〜中等度のつわりであれば胎児への直接的な悪影響はないとされています。嘔吐で腹圧がかかっても赤ちゃんは羊水に守られており大丈夫です。食事が思うように取れなくても、妊娠初期は胎児の必要栄養量がまだ少ない時期ですし、母体の栄養蓄えからも供給されますので、元々の栄養失調がなければ必要量を賄うことはできます。医師から栄養補給や点滴の指示がない限り、「吐いても、食事がまともに食べられなくても、水分さえ摂れていれば赤ちゃんは大丈夫」と考えておきましょう。それでもやはり心配になることはあると思います。そんなときは遠慮なく産科で相談し、必要な検査やケトン体(飢餓状態の指標)のチェックをしてもらうと安心です。
周囲に遠慮しすぎない
つわりで会社を休んだり家事ができなかったりすると、「迷惑をかけて申し訳ない」と周囲に遠慮してしまう妊婦さんも多いでしょう。しかし、妊娠中の体調不良は誰のせいでもなく自然現象です。仕事であれば母性健康管理制度を利用するなど、正当に休む権利がありますし、家族も職場も本来あなたをサポートすべき立場です。罪悪感を覚える必要は全くありません。家事ができなければパートナーや家族に任せ、仕事も無理せず休職や時短勤務の措置をとりましょう(産科医の意見書を書いてもらうこともできます)。あなたがしっかり休んで心身ともに健康に過ごすことが、結果的に赤ちゃんと家族の幸せにつながるのです。
情報共有と相談
自分の不安やつらさを一人で抱え込まないようにしましょう。意外にもできている方が少ない印象を受けますが、誰かと自分の体調や精神状態を共有することはメンタルヘルス維持にとても重要です。パートナーや信頼できる家族・友人に正直な気持ちを話すだけでも、心の負担は軽くなります。「自分の情けない姿なんか話せない」「こんな弱音を吐いてはいけない」と思う必要はありません。日本人は我慢強いなどと考えている人がいるのであればそんな古い考え方は捨ててしまいましょう。現代では同じ妊婦さん同士のコミュニティ(オンラインのママ向け掲示板や妊婦さん向け講習会で出会ったママ友など)で話を聞いてもらうのは非常に有効です。ただし、掲示板などはモラルのない投稿や過激な発言・コメントなどもあるので影響を受けすぎないようにしましょう。情報共有をすることで、きっと「自分だけじゃない」と実感でき、孤独感の解消につながります。また、症状が重い場合や気分の落ち込みが続く場合は専門家に相談しましょう。産婦人科で事情を話せば、必要に応じて精神科や心療内科と連携して診察やカウンセリングを受けることもできます。必要があれば治療が開始になるかもしれませんが、妊娠中でも使える安全な抗不安薬・抗うつ薬などの向精神薬もありますので、説明を受けてくださいね。精神疾患ではなく、一連の自然な経過での一時的なものであると説明を受けるだけでもすごく安心できると思います。
ネガティブ思考への対処
つわりが長引くと、どうしても否定的な考えにとらわれがちです。「自分はなんて弱いんだ」「母親失格なんじゃないか」といったネガティブな自己評価が浮かんできたら、その都度きっぱり打ち消す練習をしましょう。例えば、「今日は何もできなかった…ダメな一日だ」と落ち込んだら、「赤ちゃんのために必要な休息がとれた、明日は何かできるかもしれない」と言い換えてみます。家事ができなくても「余裕ができた分、寝ることができてよかった」、仕事を休んでも「無理して職場で倒れるより賢明な判断だった」と、自分を肯定する言葉に置き換えます。これらは簡単なようでなかなかできないことでもありますが、習慣化できると非常に効果的です。心の中で思うだけでなく、できれば声に出して言ってみると自己暗示的に気持ちが楽になります。「大丈夫、夫も手伝ってくれているし、なんとかなる」「ママも頑張ってるからね」と毎日自分に、あるいはお腹の赤ちゃんに言い聞かせてください。そして、妊娠・出産後もその考え方が習慣になっていると子育てにもいい影響があるはずです。
リフレッシュとストレス軽減に役立つセルフケア
つわり期間中はストレスフルな日々が続きますが、意識的にリフレッシュする時間を設けることも心身の健康維持に大切です。ここでは、妊娠中でも無理なくできるストレス軽減法やセルフケアのアイデアを紹介します。
マインドフルネスを取り入れた瞑想・呼吸法
最近注目されているマインドフルネスとは、呼吸や体の感覚に意識を向け「今、この瞬間」に集中する瞑想法です。妊婦さんがマインドフルネスを実践するとストレスホルモンのバランスが改善し、不安感が和らぐという研究結果も報告されています。やり方は簡単で、楽な姿勢で目を閉じ、ゆっくり鼻から息を吸って吐くことに意識を集中します。考え事が浮かんできても評価せず受け流し(考えない)、呼吸に意識を戻す—これを5〜10分繰り返すだけでもリラックス効果があります。毎日続けると妊娠中のストレス低減に有効とされ、夜も眠りに入りやすくなるでしょう。妊娠中期以降はマタニティヨガのクラスやオンライン動画を利用し、呼吸法と軽いストレッチを組み合わせてみるのもおすすめです。マインドフルネスは日常生活でも活用できますので、是非トライしてみてくださいね。
軽い運動・散歩
体調の良い時間帯に無理のない範囲で体を動かすことは、気分転換に効果的です。天気の良い日に近所をゆっくり散歩したり、公園のベンチで深呼吸するだけでもリフレッシュになります。適度な運動は血行を促し消化も助けるため、つわり症状の改善にもつながります。妊娠中に安全な運動については主治医に確認しつつ、できる範囲で体をほぐしてあげましょう。ただし吐き気が強い日は無理せず休むことが第一です。妊娠後期になるとより運動や散歩を意識して行うことになるため、散歩ルートの開拓やお気に入りのお店やカフェを見つけておくことも楽しめるかもしれません。
好きなことに没頭する
家で安静にしている間も、ネガティブな考えに囚われすぎないよう意識的に気分転換を図りましょう。特に好きなことや趣味があると心強いです。例えば、好きな映画やコメディ番組を観て笑う、本を読んだり音楽を聴いたりしてリラックスする、編み物や大人の塗り絵をして集中するなど、楽しいと感じられることに時間を使ってください。特に笑いはストレスホルモンを減らす効果があります。スマホでSNSばかり見ていると楽しんでいる他人と比較したり、ネガティブな内容が目に留まったりして落ち込むこともあるので、できれば趣味的なアナログ活動がおすすめです。出産後の子育てについてブログや本から情報収集しておくことで将来を考えて楽しみを増やしてもいいでしょう。
十分な睡眠・休養
「休みたいときに休む」のがつわり克服の鉄則です。夜は早めに床に就き、昼間も眠ければ躊躇なく昼寝をしましょう。妊娠中は普段より多く睡眠が必要です。不眠や寝付きの悪さがある場合は、寝室の環境を見直してみます。室温や湿度、枕の高さを調整し、リラックスできる音楽(小さい音量で)を流すのもよいでしょう。就寝前のスマホ・PC使用は控え、お風呂やホットドリンクで体を温めておくとスムーズに眠りに入れます(体温が下がると眠くなります)。「寝ても寝ても眠い…」という時期は、赤ちゃんのためにエネルギーを蓄えていると思って「寝すぎ」という罪悪感を捨て、とにかく眠ることに専念してください。
リラクゼーション効果のある飲み物
食事が思うように取れない時でも、ハーブティーやホットミルクなど温かい飲み物でホッと一息つく時間を持ちましょう。例えば、科学的にはカモミールティーやペパーミントティーにはリラックス効果があり、吐き気を和らげる助けにもなるようです。蜂蜜やシロップを少し入れてゆっくり飲めば、カロリー補給とリラックスが同時にできます。ただし、ハーブによっては妊娠中避けた方が良い種類もあるので、カフェインを含まない安全なハーブを選んでください(市販の「マタニティブレンド」ハーブティーなどが安心です)。
セルフマッサージやツボ押し
気分が落ち込んでいるときほど、自分で自分をいたわる行動が大切です。温かいオイルやお気に入りのクリームで手足をマッサージしたり、肩や首をゆっくり揉みほぐすと筋肉の緊張がほぐれ、リフレッシュできます。吐き気に効果がある有名なツボとして内関(ないかん)があります。手首の内側のシワから指3本分肘寄りにあるツボで、ここをゆっくり押すと吐き気が和らぐと言われています。実際、手首に巻くつぼ押しバンド(シーバンド)がつわり軽減に役立ったとの報告もあります。個人差はあるかと思いますが、ご自身で優しくツボを刺激したり、パートナーに頼んで軽く押してもらうのも良いでしょう。
自分に優しく、完璧を求めない
最後に、日頃の心がけで大切なのは、「今の自分は普段とは違う特別な状態にある」ことを認めたうえで、自分に優しく接することです。甘々でいいんです。家の中が多少散らかっていても気にしない、毎日お昼もパジャマで過ごしてもOK、とにかく自分とお腹の赤ちゃんが心地よくいられることを最優先に考えましょう。真面目で責任感の強い人ほど「私がちゃんとしなきゃ」「お腹に赤ちゃんがいるんだから」と思いがちですが、つわり期間中くらいは肩の力を抜いて「まあ、いいか」「今だけは仕方ないよね」で乗り切ってください。世の中の妊婦さんの多くが程度の差こそあれ同じ経験をしています。「みんな大変なんだ、一人じゃない」と思えば少し楽になれますし、頑張りすぎないことがつわり悪化予防にもつながります。
おわりに
いかがでしたか。
つわりの時期は、身体的な苦しさだけでなく、心にも大きな負担がかかる特別な時期です。不安や孤独感、無力感、苛立ちなど、妊婦さんが感じるさまざまな感情はすべて自然な反応であり、決して「自分が弱いから」「精神的に未熟だから」ではありません。この時期は誰もが情緒不安定になりやすく、ネガティブな気持ちになることも珍しくありません。だからこそ、まずは「自分を責めないこと」、そして「一人で抱え込まないこと」が大切です。
妊婦さん自身には、必要なときには遠慮せずに助けを求め、セルフケアや気分転換を取り入れながら、心身をいたわってほしいと思います。つわりは必ず終わりが来る一時的なものです。どうか焦らず、完璧を求めすぎず、自分のペースでこの時期を乗り越えてください。あなた自身やお腹の赤ちゃんのために、少しでも穏やかに過ごせる時間が増えることを願っています。
パートナーや家族など、周囲の支援者も、妊婦さんの気持ちの揺れやつらさを理解し、温かく寄り添ってサポートすることが大切です。次回の記事では支援者目線での対応方法をまとめられたらと考えています。ぜひ、参考にしていただけたらと思います。
それでは、幸せな子育てライフを!

参考文献・情報源
- 日本産科婦人科学会「産科診療ガイドライン-産科編2020」
- 日本産婦人科医会「つわり(妊娠悪阻)に関するQ&A」
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「妊娠悪阻」
- 厚生労働省「母性健康管理指導事項連絡カード」
- ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists): Morning Sickness: Nausea and Vomiting of Pregnancy. FAQ126. 2021.
- NIH (National Institutes of Health): Nausea and vomiting of pregnancy – MedlinePlus
- NICE guideline [CG62]: Antenatal care for uncomplicated pregnancies (National Institute for Health and Care Excellence)
- Maternal Mental Health Alliance: Hyperemesis Gravidarum and mental health (2023)
- PR TIMES「妊婦の約9割がつわりを経験、約半数が精神的に不安定に。『つわり』に関する意識調査」2023年
- 兵庫県立大学 地域ケア開発研究所「つわり症状の軽減法と支援」2022年
- 明治国際医療大学 看護学部「妊婦へのアロマセラピーの有効性」看護研究学会雑誌 2021年
- 産婦人科オンラインジャーナル「妊娠中の不安な気持ちの対処法」2022年
- Better Health Channel (Australia): Pregnancy – morning sickness
- Smith, C.A., Crowther, C.A., Willson, K., et al. “Aromatherapy for nausea and vomiting in pregnancy.” Cochrane Database Syst Rev. 2020.
- Duke, A. et al. “Management of Nausea and Vomiting in Pregnancy.” Am Fam Physician. 2021; 103(5): 277-284.
- Dean, C., Shemar, M., & Gill, P. “Hyperemesis gravidarum and risk of psychological distress, depression and anxiety: A systematic review.” Pregnancy Hypertens. 2021; 25: 179-186.
- 厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」
- 公益社団法人 認知行動療法学会
- オーストラリア産科新生児学会「Morning sickness in pregnancy」
- Seabergh, B. et al. “Ginger for nausea and vomiting in pregnancy.” Obstet Gynecol. 2020; 135(5): 1108-1115.