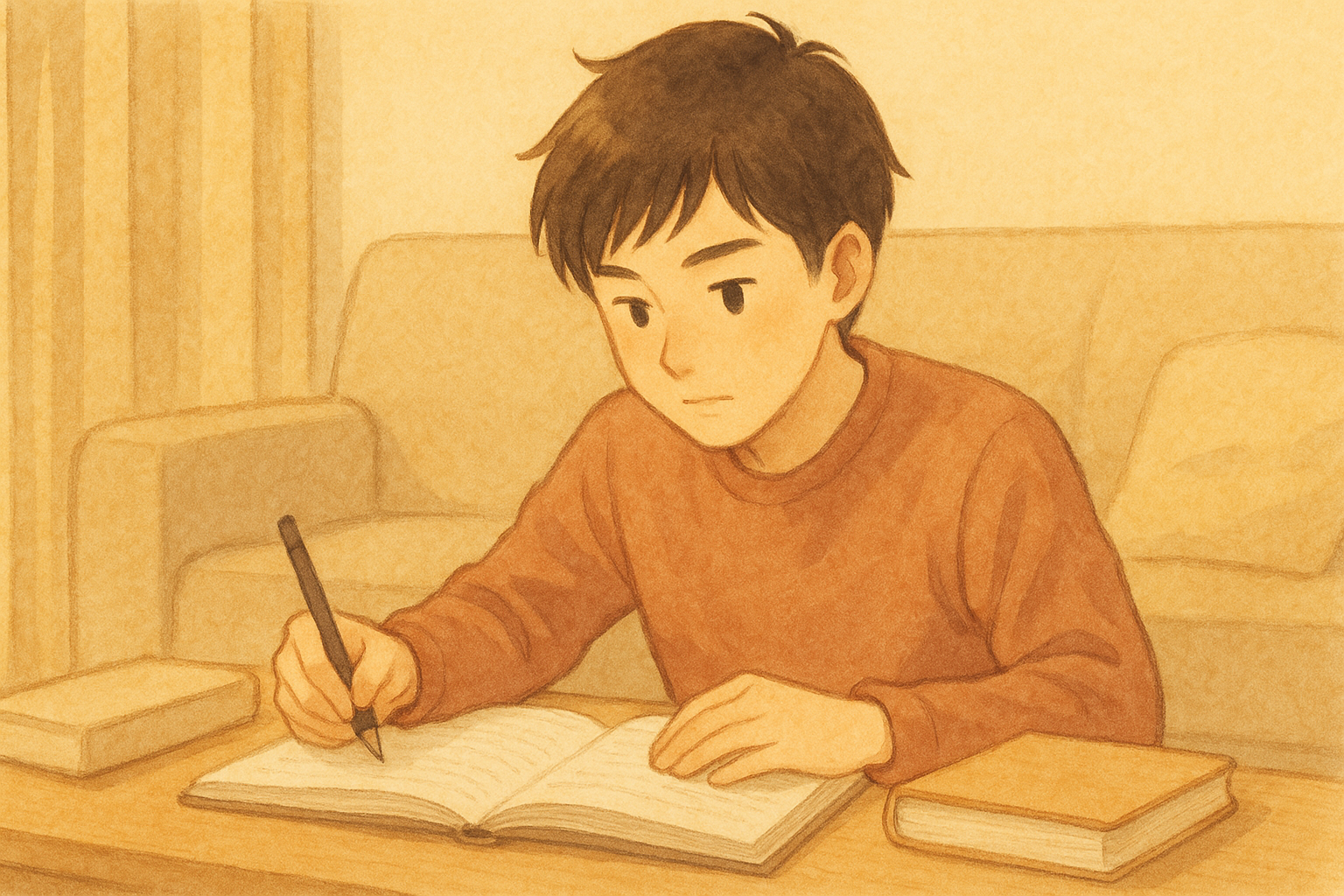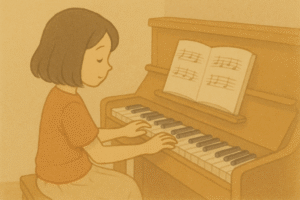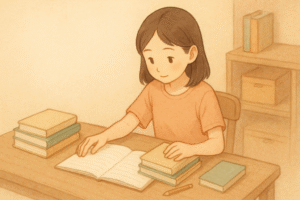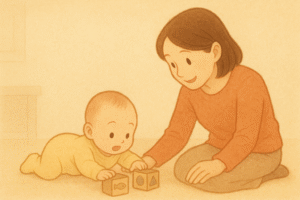こんにちは、Dr.流星です。
高校生ともなると、認知能力や論理的思考力がさらに発達し、学習内容も高度化していきます。自分の将来を見据えた計画力や自己管理能力が求められ、学ぶ目的や意義を見出すことが、長期的な学習意欲に直結します。
今回は、高校生が主体的に学ぶ力を伸ばすための脳の発達特性、内発的動機づけの方法、親のサポートのあり方、そして自律的な学習環境の整え方について詳しく解説します。将来に向けた力強い一歩を踏み出せるよう、ぜひ参考にしてください。
高校生(16~18歳)
脳の発達と高次機能の成熟
高校生ともなると、認知能力は大人にかなり近づきます。論理的思考力や判断力、計画性など前頭前野の機能が中学生時代より発達し、自己コントロールも多少効くようになります。ただ、脳の発達はまだ完了ではありません。神経科学によれば脳が大人と同程度に成熟するのは20代半ばであり、高校生の脳もなお成長途上です。具体的には、注意力やマルチタスク能力、将来を見据えた意思決定などは向上しますが、強いストレス下や誘惑の多い環境では衝動に負けることもあります。この時期は大学受験や将来への不安などで慢性的なストレスを抱えやすいですが、繰り返すストレス反応は脳の学習に関わる部位に悪影響を与える可能性があるので、上手なストレスマネジメントが必要です。脳の可塑性という点では、高校生はすでに基礎的な回路は出来上がっていますが、興味のある専門分野については集中的に能力を伸ばせる柔軟性があります。例えば、高校から始めた第二外国語を熱心に勉強した場合、大人よりも早く習得できたり、数学オリンピックに向けて鍛錬すれば高度な抽象思考力が育つといった具合です。脳は使う領域を選択的に発達させることができるので、高校時代に何に力を注ぐかで脳の発達も個性が現れるでしょう。また、高校生になると思春期のピークが過ぎて情緒も安定してきます。親離れ・子離れの過程でもあり、精神的に自立し始めるので、学習においても自分の意志で取り組む割合が増えます。高校の3年間は人生の中でも人格や価値観が大きく形成される時期であり、「学ぶこと」への姿勢もここで固まると言っても過言ではありません。すなわち、高校時代に自主的に学ぶ習慣を確立した人はその後も生涯にわたり学び続ける傾向があり、逆に受動的・消極的になってしまうと大学でも伸び悩む場合が多いです。脳の発達的には、高校生は「大人の脳へのラストスパート」です。基礎力を完成させつつ、自分なりの興味や強みを伸ばし、ストレスや誘惑に打ち勝つレジリエンス(適応力、復元力、耐久力)も身につけられるよう、総合的な支援が求められます。
モチベーション:自律性と目的意識を育む
高校生の学習動機は、人によって大きく分かれてきます。大学受験や将来のために頑張る子もいれば、燃え尽きやスランプで意欲を失う子もいます。共通して言えるのは、中学生までよりも自分の意志で勉強するか否かを選べる環境になっていることです。先生や親の管理は減り、宿題も自己責任、予習復習も自分次第です。このため、内発的動機づけが弱い子は成績が大きく下がることも珍しくありません。一方で、興味あることには驚異的な集中力を発揮する場合もあります。例えば、好きな科目の勉強や、資格試験の勉強に没頭するなどです。もちろん、スポーツや趣味への没頭もあるでしょう。この「興味への集中力」を活かして高校生のモチベーションを高めるには、まず明確な目標設定が有効です。大学進学が目標なら志望校を具体的に決め、その学校のオープンキャンパスに行ったりカリキュラムを調べたりすると、「ここに行きたい」という気持ちが強まり日々の勉強の原動力になります。進学以外でも、「将来エンジニアになりたいから数学を極める」「留学したいから英語を頑張る」など、将来像と現在の学習をリンクさせることが重要です。親や教師はその目標設定を手伝い、現実的かつやる気の出る目標を一緒に見つけましょう。
モチベーション維持には成功体験も欠かせません。高校の勉強は難しくなるため、挫折を経験しやすいですが、小さな成功を積み重ねる工夫をします。例えば、模試で苦手科目の偏差値が5上がったら思い切り褒めて自信をつけさせる、定期テストで一つでも順位が上がったら一緒に喜ぶ、といった具合です。親の立場からすると志望校に届く点数でなければ不安かもしれませんが、過程での進歩を承認することがさらなる努力を促す点を忘れないでください。「結果だけを見ずに、過程を褒める」のは子育ての基本です。ご褒美の使い方も高校生では変わってきます。物質的な報酬より、精神的な報酬や将来への投資が動機づけになります。例えば、希望の大学に合格したら一人暮らしを許可する、結果が出たときには多少高価でも将来に役立つパソコンを買ってあげるなどです。声かけでも「○○が頑張ってる姿をみて誇らしいと思ったよ。応援してるからね」「自分のやり方でやってみていいからね。困ったことがあればいつでも言ってね」と徐々に対等な立場で話しかけていくといいでしょう。親からの信頼や称賛そのものが大きな報酬になる年齢でもあり、精神的な成長を実感できる機会となります。
また、この頃になると友人や恋人など周囲からの影響もモチベーションに影響します。仲の良い友達同士で切磋琢磨して勉強している場合は問題ありませんが、そうでない場合は本人が孤軍奮闘でやる気を出さねばなりません。そこで、塾や勉強会など同じ目標を持つ仲間との出会いを促すのも手です。互いに刺激し合えると継続しやすくなります。部活引退後は特に時間ができるので、図書館で毎日自習する習慣を友達と始める、塾主催の勉強合宿に参加するなど、環境を変えてモチベーション維持を図ります。
内発的動機づけについては、高校生にもなると「学ぶこと自体が楽しい」と思える場面が増えているかもしれません。好きな科目で深い知識を得たり、難問が解けた時の爽快感などは、純粋な知的快感として味わえるでしょう。この快感を大事にし、それを得られる瞬間を増やすよう仕向けます。学習そのものの喜びに気づくことができた場合、「学ぶことが楽しい」と学習への意欲が維持でき、みるみるうちに成績も上がります。事実、学業優秀な高校生の多くは「勉強が楽しい」と感じており、それが強力な内発的動機になっています。もちろん、全科目でそれを感じるのは難しくとも、一部の科目やテーマだけでもそう思えるなら、勉強全体への態度が前向きになります。しかし、この「学ぶ楽しさ」を得るまでには苦労も多く、努力が必要であることは事実です。そのために、幼少期から「学びへの欲」を育てておくことが大切なのです。
最後に、日頃からモチベーションを自己管理する方法を知っておく必要があります。高校生には自分で習慣化し、自分でやる気を鼓舞する力が求められます。「やる気が出ないから今日はいいや」では済まなくなるので、そんな時はどうするかを一緒に考えます。例えば、「5分だけやってみて、それでもダメなら休もう」といったスモールステップや、「過去にやる気が出た方法(音楽を聴く、目標を紙に書く・声に出すなど)を試してみる」などです。自分で試行錯誤してモチベーションをコントロールする経験は、将来大学や社会に出てからも役立つスキルとなります。
以上、高校生のモチベーション支援は、本人の目的意識を高め、自主性を尊重し、成功体験で支え、自分でやる気を維持する術を身につけさせることに集約されます。親はそれを陰から見守り、必要に応じて声をかけたり環境を調整したりしてサポートしましょう。
親の関わり方
高校生ともなると、親の関与は以前より限定的になります。学校生活や勉強の細かい部分に親が介入することは減り、子どももそれを望まないでしょう。親は基本的に「後方支援」に徹するスタンスが望ましいです。ただし全く無関心では子どもも不安になります。前述した通り、親からの信頼や称賛が活力になる時期であり、子どもは子どもなりに「親に応援してほしい」「認めてほしい」という気持ちを強く持っています。そこで、適度な関心とサポートを示しましょう。例えば、定期テスト前に「調子どう?何か手伝えることある?」と声をかける、模試の結果について「数学が苦手って言ってたけど、着実に伸びてるね」「英語は次回までの伸びしろが大きいね」とポジティブなフィードバックをする、といった具合です。結果が悪かった時も頭ごなしに叱らず、「どこが難しかった?作戦練り直そうか。何が必要かな」と共に問題解決に向かう姿勢を見せます。高校生は大人扱いされることを好みますから、「あなたの努力を尊重しているし、信頼もしている」というメッセージを常に伝えるようにします。親の信頼は高校生の自信とやる気を支える大きな力です。
具体的な勉強の内容については、親が教えることは難しくなってくる場合が多いでしょう。無理に口出しせず、必要なら塾や学校の先生に任せます。その代わり、学習リソースの確保や環境調整に注力します。例えば、「参考書買いたいんだけど…」と言われたらすぐ購入に協力する、勉強合宿に参加したいと言えば費用や準備をサポートする、静かな環境で勉強できるよう他の家族にも協力を求めるなどです。また、生活面での支えも親の重要な役目です。食事の栄養バランスを考え、脳に必要なブドウ糖やタンパク質、オメガ3脂肪酸(DHAやEPAなど)などをしっかり摂らせます。試験前は消化に良いものやビタミン豊富な果物を出すなど、陰ながら力を発揮できるようケアします。睡眠も不足しがちなので、睡眠時間が確保できるよう親がサポート(学校の準備を手伝うなど)し、寝具や照明などの睡眠環境も整え、良質な休息を促します。親が健康管理を気遣ってくれると、子どもも「支えられている」安心感から頑張れるものです。
高校生は進路に直結する時期ですので、進学・就職の情報提供や相談相手としても関わります。大学選びではオープンキャンパスに同行したり、一緒に(もしくは親が中心となって)大学の資料を取り寄せたりすると良いでしょう。ただし、最終的な決定は子どもに委ねます。親の意向を押し付けると後々子どもが後悔したり反発したりしかねません。親はファシリテーター(引き出し役)として、多くの選択肢や判断材料を提示しつつ、「あなたの人生だから自分で決めていいんだよ」と伝えます。アドバイスを求められた時は、自分の意見を述べても構いませんが、「○○だからこの大学に行くべき」と断定せず、「○○大学は△△が、◇◇大学は☆☆が魅力的だよね。私ならこっちかな。でも一番大事なのはあなたが何をもって納得できるかだよ」とフォローします。どんな進路を選んでも親はあなたを応援するという姿勢を示しておくと、子どもは安心して自分の道を選べ、その選択肢に向けて勉強を頑張れます。
さらに、親子の会話は学業以外のことも大切にします。高校生になると親に全てを話さなくなりますが、それでも雑談や共通の趣味の話などは貴重なコミュニケーション機会です。親子の信頼関係が維持されていれば、子どもは必要な時に必ず相談してきます。そうした土壌を培うためにも、音楽や時事問題、友人関係など色々な話題で普段から話しやすい雰囲気を作っておきましょう。勉強の悩みも、そうした何気ない対話の中でポロッと出てくることがあります。その際は真剣に耳を傾け、一緒に解決策を考えてあげます。(恋愛については、勉学にも大きな影響を与える要素ではありますが、介入しすぎないようにしましょう。)
最後に、親自身の接し方ですが、高校生には基本対等にリスペクト(尊重する気持ち)を持って接することが大切です。過干渉や詮索は避け、プライバシーも尊重します。しかし「大人扱い」と「無関心」は違います。要所では親として毅然と助言したり注意したりも必要です。例えば、明らかに勉強をサボっている日が続けば、「このままだと志望校厳しいけど大丈夫か?」と問いかけ、軌道修正を促すなどが必要になる場合もあるでしょう。完璧な声かけをする必要はありません。「あなたのことを気にかけてるからこそ注意するんだよ」といった姿勢は貫き、多少の衝突はあっても対等な関係を持ち続けることが肝要です。本人が「うるさいな」と思っても、後で振り返れば感謝されることもあります。結局、親の深い愛情と適度な距離感が、高校生には一番の支えです。「見守るけれど見放さない」バランスを保ちながら、子どもが自立した学習者になるのを後押ししましょう。
学習環境とセルフマネジメント
高校生ともなると、自分の学習環境はかなり自分でコントロールできるようになります。親が用意してあげる面は中学までに比べ減りますが、その代わり子ども自身が環境を整える力を発揮できるよう支援します。
まず、家での勉強環境は基本的に中学生までに整えたものを引き続き使います。静かな自室と明るい照明、整理された机、必要な資料が揃った本棚などがあれば十分でしょう。高校生になると参考書やノートの量が増えるので、収納スペースや整理システムを子どもと相談してアップデートします。例えば、新しく本棚を追加する、古い教材を処分してスペースを作る、科目別に色分けしたファイルを用意するなどです。親はそれを一緒に手伝い、環境のリフレッシュを図ります。模様替えをすると気分も変わり、新たな気持ちで勉強に臨めることがあります。
次に、デジタル環境との付き合いです。高校生は勉強にPCやインターネットを使う場面も多くなります。レポート作成やオンライン講座の受講などでPCが必需品となることもあります。親は必要に応じて性能の良いPCやタブレットを用意してあげましょう(これは一種の報酬にもなります)。ただし、SNSや動画視聴などの誘惑も大きいので、本人に自制を促します。すでに自律が期待できる年齢ですから、中学生までのような強制的な制限はせず、ルール作りと時間管理は本人に任せる方向で良いでしょう。どうしてもコントロールが難しければ再度話し合ってルールを見直しますが、基本は自立に委ねます。
場所の活用も高校生になると多様になります。学校の図書館、塾の自習室、スタバやファミレス、時には24時間営業の自習スペースなど、本人が集中できると思う場所で勉強することもあるでしょう。親はそれを許容し、必要なら送り迎えや利用料の支援をします。ただし、深夜の利用は避け、治安面の配慮は忘れずに行いましょう。家に友達を呼んで勉強することもあるかもしれません。その際は場所を提供し、飲み物や軽食を差し入れするなどサポートしつつも口出しはしません。お互い教え合う学習は理解を深める良い方法なので、歓迎しましょう。
静音環境については、高校生でも集中には静けさが一番です。小さい弟妹がいる場合、受験生の高校生の勉強時間には部屋を分けたり外出してもらったり、家庭全体で協力します。近所の騒音がひどい場合は、思い切って図書館メインで勉強しても良いかもしれません。逆に、多少の雑音なら音楽でマスキングするなど、本人なりに工夫している場合は見守ります。
視覚的環境では、高校生にもなると好きなポスターや写真を貼る子もいます。勉強に支障なければ問題ありません。むしろ志望大学のパンフレットや目標にしている先輩や有名人の名言などを壁に貼ってモチベーションにしている例もあります。そうしたセルフモチベートの工夫は尊重します。ただ、散らかった部屋で勉強しているようなら、時折「片付けた方が効率上がるんじゃない?」と整理整頓を促しましょう。自分で気づけば片付けるでしょうし、気づかないようなら一緒に片付けを手伝ってもよいでしょう。
高校生ともなると生活パターンも人それぞれです。朝型で早朝に勉強する子、夜型で深夜に集中する子。それぞれメリットデメリットがありますが、親はある程度子どものリズムを受け入れます。ただし、睡眠時間だけは確保させましょう。夜型でも6~7時間は寝るよう、朝起きれないようなら夜遅くまでは勉強しないよう働きかけます。やはり10代の学習には睡眠が欠かせず、寝る間を惜しむ勉強は、むしろ効率が落ちることを知っておきましょう。
最後に、環境以上に本人の意思が物をいう段階です。親は環境を整えてあげたら、あまり口うるさく言わず信じます。「準備は万端だから、あとは努力次第だね!頑張れ!」と背中を押しましょう。自分の部屋のドアに「勉強中・入るな」の札をかけるような子もいます。その場合は本当に必要なとき以外ノックもしないぐらいの配慮をします。一方で、リビングで勉強しているなら家族も静かに過ごすなど環境作りに協力します。このように高校生の学習環境は本人の自己管理に任せ、親はサポート役に徹する形になります。もちろん、試験の日程管理や願書の提出など細かいところで手助けが必要な場面もありますが、それも「手伝ってくれてありがとう」の一言で済むくらい、子どもが主体でいるのが望ましいです。
高校生の学習環境づくりで親が心がけるべきは、「困った時は助けるが、基本は子ども自身に任せる」スタンスです。そうすることで子どもは自らベストな環境を整え、勉強を自己管理する力を養えます。この力こそが大学での自主的な学びや将来の自己研鑽につながり、生涯にわたって勉強好きでいられる礎となるのです。
高校生(16~18歳)
- 脳の発達
- 前頭前野の機能がさらに発達し、自己コントロール力が向上する。
- 高次機能の成熟に伴い、計画力や抽象的思考が向上。
- モチベーション
- 興味を持っていることへの集中力を活用。明確な目標設定が鍵。
- 学ぶ楽しみを知り、モチベーションの自己管理ができることが理想。
- 親の関わり方
- 基本は後方支援に徹し、助力を求められたときだけ意見を伝える。
- 信頼をもって対等な関係で接しつつ、必要時には心理的なサポートを。
- 学習環境
- 自主的に整えられる力を伸ばし、ルール作りと時間管理は任せる。
- 本人の意思を尊重しつつ、環境の整備、睡眠の確保には助力する。
参考文献・情報源
参考文献・情報源
- 乳児期の脳発達
- Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (Eds.). (2000). From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. National Academy Press.
- Johnson, M. H. (2005). Developmental Cognitive Neuroscience. Wiley-Blackwell.
- 内発的動機づけと報酬系
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.
- Galván, A. (2013). The Teenage Brain: Sensitivity to Rewards. Current Directions in Psychological Science, 22(2), 88-93.
- Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627-668.
- 学習環境と家庭の影響
- Evans, G. W., & Wachs, T. D. (Eds.). (2010). Chaos and Its Influence on Children’s Development: An Ecological Perspective. American Psychological Association.
- Sanders, M. R., & Mazzucchelli, T. G. (2013). The Power of Positive Parenting: Transforming the Lives of Children, Parents, and Communities Using the Triple P System. Oxford University Press.
- 学習習慣と学力
- Dweck, C. S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. Random House.
- Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. P. (2005). Self-Discipline Outdoes IQ in Predicting Academic Performance of Adolescents. Psychological Science, 16(12), 939-944.
- Heckman, J. J., & Kautz, T. (2013). Fostering and Measuring Skills: Interventions That Improve Character and Cognition. NBER Working Paper No. 19656.
- 睡眠と学習の関係
- Walker, M. P. (2017). Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams. Scribner.
- Carskadon, M. A., & Tarokh, L. (2014). Developmental changes in circadian biology and sleep regulation. In G. G. National Research Council (Ed.), Sleep Disorders and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem. National Academies Press.
- 思春期の脳の発達
- Blakemore, S. J., & Mills, K. L. (2014). Is Adolescence a Sensitive Period for Sociocultural Processing? Annual Review of Psychology, 65, 187-207.
- Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The Adolescent Brain. Annals of the New York Academy of Sciences, 1124(1), 111-126.
- 家庭の学習支援と親の関わり
- Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1989). Parent Styles Associated with Children’s Self-Regulation and Competence in School. Journal of Educational Psychology, 81(2), 143-154.
- Pomerantz, E. M., Moorman, E. A., & Litwack, S. D. (2007). The How, Whom, and Why of Parents’ Involvement in Children’s Academic Lives: More Is Not Always Better. Review of Educational Research, 77(3), 373-410.