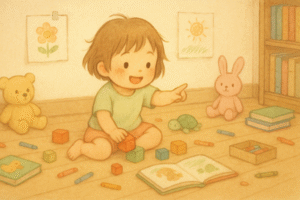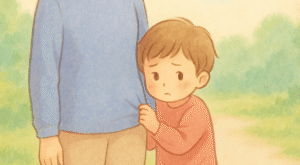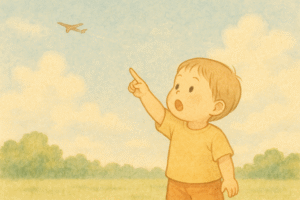こんにちは、Dr.流星です。
子どもにどう声をかけたらよいか、特に、叱る場面ではどう伝えるべきか悩む親御さんは少なくありません。
今回の記事では、「子どもへの声かけと叱り方」について、医学的・科学的な根拠に基づき、年齢ごとに分かりやすく解説していきます。
ちょっと長めの記事なので、「うちの子に関係ありそうなところだけ知りたい!」という方は、ぜひ目次から読みたいところへ飛んでくださいね。
はじめに
子どもに望ましい行動を教えるためには、年齢や発達段階に応じた適切なしつけとコミュニケーションが欠かせません。研究によれば、体罰(叩く、平手打ちなど)は子どもの問題行動の改善に効果がなく、怒鳴ったり子どもを辱めるような叱り方も同様に逆効果だと分かっています。むしろ、過度に厳しい身体的・言葉による罰は子どもの心身の発達に長期的な悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、子どもの発達(心理面、脳の成熟、社会性、自我の形成など)に合わせて、適切な声かけや叱り方を選ぶことが重要です。
では、乳幼児期から大学生までの年代別に、科学的エビデンスに基づいた効果的な声かけ・叱り方と、避けるべき言動について解説していきます。
乳幼児期(0〜2歳)
効果的なアプローチ
この時期の子どもは論理的な理解や自制がまだできず、親が長々と説教しても意味を理解できません。危ない行動をした場合は頭ごなしに叱るのではなく、物理的にその場から遠ざけたり、危険な物を取り上げて安全なおもちゃに持ち替えさせるなど注意をそらす対応が有効です。例えば赤ちゃんが割れ物を掴んだら、「それは触らないよ。こっちで遊ぼうね」と優しく声をかけながら取り上げ、代わりに安全な物を渡すと良いでしょう。普段から肯定的な言葉で簡単に伝えるよう心がけ、「立っちゃダメ!」より「お座りしようね」というように言い換え、“ダメ!”など否定的な言葉は本当に危険な場面に限定して使うのがおすすめです。例えば、刃物に触ろうとした時には、「あぁ、ダメダメ!」と言いながら安全な場所に移動させたうえで、「痛い痛いしちゃうからダメなんだよ。大きい声出してごめんね。びっくりしたね」と優しく声を掛けます。また、親が赤ちゃんの声やしぐさに反応してあげる(要求に応じたり話しかけたりする)ことは、脳の発達を促しコミュニケーション能力の基盤を築くのに役立ちます。例えば、赤ちゃんが喃語(「あーうー」「まんま」など)を発したら笑顔で応じたり、泣いたときには抱きしめて落ち着かせることで、安心感と信頼関係が育まれます。声色で赤ちゃんもママ(パパ)が楽しいのか怒っているのかが分かるとされており、脳への刺激が違うため、脳への影響も異なってきます。
避けるべき言動
当然のことではありますが、大声で怒鳴ったり、威圧的な口調で叱ることは避けましょう。先述しましたが、生後数ヶ月の赤ちゃんでも親の表情や声のトーンから感情を感じ取っており、家庭内で怒鳴り声が聞こえると、眠っている赤ちゃんでさえストレスホルモン値が上がるとの研究もあります。このように強い怒りの声は赤ちゃんに不安とストレスを与え、安心感を損ねます。もちろん体罰は厳禁です。特に乳児期の子どもへの身体的な罰は重大なけがの危険がある上(揺さぶられっこ症候群など)、脳の発達にも悪影響を及ぼしかねません。この年代では「叱って教える」ことは難しいため、怒りや罰ではなく、安全を確保しつつ穏やかに見守る姿勢が基本となります。「なんで泣き止まないの!」「静かにしてよ!」と言っても赤ちゃんが分かるはずもなく、状況は好転しません。もし、そのことがどうしても理解できなければ、親御さん自身に精神科的要因(知的障害や発達障害、産後うつなど)がある可能性があります。対処できない場合は、一人で抱え込まず、家族、医療機関、行政機関を頼ってください。
乳幼児期(0〜2歳)
効果的な声かけ・叱り方:
- 危険行動には注意をそらす方法で対応する
- 否定的な言葉より、肯定的で簡単な言い換えを使う
- 喃語やしぐさに反応してあげることで安心感と脳の発達を促す
避けるべき対応:
- 怒鳴る、威圧的な言い方や体罰は厳禁
- 理解できない言葉で叱ること(例:「静かにしなさい」など)
- 感情をぶつけるだけの否定的な叱責
幼稚園期(3〜5歳)
効果的なアプローチ
3〜5歳頃になると、子どもの認知能力と言語能力が発達し、自我(自己主張)も芽生えてきます。いわゆる「イヤイヤ期」で、自分の思いどおりにならないと癇癪を起こすこともあります。しかし、子どもが「イヤ!」と反抗するのは、自分の興味や意思を模索している表れでもあります。効果的な声かけとしては、子どもの気持ちを尊重しつつ、親の期待やルールを簡潔に伝えることです。例えば、子どもが汚れた靴を履きたがった場合、「それは汚いからダメ!」と頭ごなしに否定するのではなく、「ママはこっちのきれいな靴を履いてほしいな。汚れている靴だと靴下も汚れちゃうもんね」のように理由を添えて諭すと、子どもも受け入れやすくなります。擬人化も効果を示すことがあり「この靴のウサギさんも一緒にお出かけしようって言ってるよ」など、子どもが楽しく選択できるような工夫もしてみましょう。また、子どもは徐々に善悪の概念やルールを理解し始めるため、簡単なルールは説明して教えましょう。ただし、長い説教(説諭)はまだ難しいので、短く具体的に伝えることが肝心です。できたことを「できたね!」と積極的に褒めてあげるのも効果的です。例えば、公園で友達と遊んでいて順番が守れたときには「順番守れたね!すごいね!ママ(パパ)は嬉しいよ」と褒めておくと、「ママ(パパ)が喜んでくれるから遊ぶ時には順番を守る」と子どもも考えるようになります。4〜5歳頃には「自分だけできないのは恥ずかしい」という感情や、うまくできたときの誇らしい気持ちが育ってくるため、どんな小さな成長も認めて一緒に喜び、子どもの「誇らしい」気持ちを育ててあげることで、「自分はできる、がんばれる」という自信がついてきます(自己肯定感を育てる)。この自己肯定感がその後の勉強やスポーツの上達、リーダーシップなどに繋がっていきます。
避けるべき言動
自己肯定感を育てるためにも、この年代の子どもを叱る際には、人格を否定するような言葉や他の子と比較する発言は厳禁です。例えば、「まじで悪いことしかしないよね。意味がわからない」「○○ちゃんはできているのに、どうしてあなたはできないの?」といった言い方をすると、子どもは「自分はダメな子なんだ」と思い込んで自己肯定感を傷つけてしまいます。特に幼稚園期の子どもは他人からの評価に敏感になり始めるため、恥をかかせるような叱り方は逆効果です。叱る際には人前で叱ることは避けましょう。また、感情的に怒鳴ったり叩いたりすると、子どもは恐怖心から一時的には従うかもしれませんが、本質的な理解にはつながりません。強い怒りや罰は子どもの心に不安や恐怖を残し、かえって癇癪や問題行動をエスカレートさせる可能性があります。したがって、頭ごなしに叱りつけるのではなく、落ち着いて毅然と対応し、子どもの気持ちにも寄り添う姿勢が大切です。自分自身ではなかなか気付いていない親御さんもいらっしゃいます。そういった方は周囲からの支援がなかなか受けられない状況にあったり、親御さんに精神科的要因(知的障害や発達障害、うつ病など)があったりする可能性があります。一人で抱え込まず、周囲の助言を聞きながら子育てを見直してみてください。
幼稚園期(3〜5歳)
効果的な声かけ・叱り方:
- 子どもの気持ちを尊重しつつ、親の意図を簡潔に伝える
- 理由を添えて諭すことで納得感を持たせる
- 小さな成功も「できたね!」と喜び、自己肯定感を育てる
避けるべき対応:
- 「なんでできないの?」などの人格否定や比較
- 感情的な怒鳴り声や体罰、人前で恥をかかせる叱り方
- 子どもを傷つける言葉で支配しようとする関わり
小学生(6〜12歳)
効果的なアプローチ
小学生になると、概念の理解力や論理的思考が発達し、社会のルールや善悪の判断もだんだん身についてきます。この時期の子どもには、なぜそれがいけないのか理由を説明し、自分で考えさせる関わり方が有効です。「ダメなことを注意するだけでなく、なぜダメなのかという理由をセットで説明すること」が重要だと指摘している専門家もいます。例えば、友達との約束の時間を破ったときは、「○○君が時間を守れなかったからお友達は困ってたよ。待っている間、お友達は悲しかったんじゃないかな。○○君も約束したのにお友達が来なかったら悲しいんじゃないかな」とその行動が原因で起きた結果や他者の気持ちを伝えます。その上で「次からどうしたらいいと思う?」と本人に考えさせると、子どもは自分の行動と結果を結びつけて学びやすくなります。子ども自身が選択や反省をする機会を与えることで、自己判断力や責任感が育ちます。また、家庭のルールや期待事項を子どもと話し合って明確にしておくことも大切です。ルールを一定期間守ったときにはお小遣いや遊び時間などの年齢に応じた特典を与えるなど、規律と自由のバランスをとると良いでしょう。さらに、子どもの努力や良い行いを見逃さずに褒める(「宿題なんてして当たり前」とスルーするのではなく、「今日も宿題終わったんだね!頑張ったね」など)ことで、望ましい行動を強化できます。叱った後で改善が見られたらしっかり褒めてあげる(「お!この前言った○○ができてるね!お母さん嬉しいよ!」など)のも忘れないようにしましょう。
避けるべき言動
小学生の子どもへの叱り方で注意したいのは、頭ごなしに押さえつけたり人格を否定する言葉を使うことです。「あなたはダメな子ね」「全然できていない」などの言葉は自己評価を下げてしまい、子どものやる気を失わせます。また、兄弟や他の子と比較して叱るのも避けるべきです(「お兄ちゃんはできるのに、なぜあなたはできないの?」など)。比較されると子どもは劣等感を抱き、親への反発心や嫉妬心が生まれやすくなります。ドラマなどでよく見るこの兄弟間や他者との比較ですが、いざ自分の家庭となると意外としてしまっていることがあります。この年代では叱る際に長時間説教したり感情的に怒鳴り続けるのも逆効果です。長すぎる説教は子どもを萎縮させ、集中力も続かず、内容が頭に入らなくなります。むしろ短く要点を伝えた後は、子どもに「なぜ叱られたのか」「何がいけなかったのか」を自分の言葉で説明させる方が理解と納得が深まります。さらに、叩くなどの体罰は絶対に避けましょう。体罰は一時的に言うことを聞かせても、子どもは「親も暴力を使うものだ」と学習してしまい、攻撃的な行動や問題行動が減るどころか増えてしまう傾向があります。実際、体罰を受けた子どもは他者に対しても乱暴になりがちで、暴力によるコミュニケーションの悪循環に陥ることが報告されています。もし、別の家庭の体罰や繰り返す暴言などを発見した際には、児童相談所などの行政機関への連絡をお願いします。
小学生(6〜12歳)
効果的な声かけ・叱り方:
- なぜいけないのか、理由を添えて説明する
- 自分で考えさせる問いかけをし、反省を促す
- 約束を守れたときや努力したことを積極的に褒める
避けるべき対応:
- 頭ごなしの命令、長時間の説教
- 他の子や兄弟との比較
- 体罰による行動コントロール
中学生(13〜15歳)
効果的なアプローチ
中学生になると、思春期に入り心身ともに急激な変化が起こります。脳の前頭前野(判断や抑制を司る部分)はまだ発達途中で、完全に成熟するのは25歳前後と言われています。このため、13〜15歳頃の子どもは衝動的な行動や感情の起伏が大きく、大人から見ると未熟な判断をすることがあります。同時に、自我がよりはっきりし、親からの干渉に敏感になり始めます。そのため効果的な関わり方は、子どもを一人の人格として尊重しつつ、明確なルールと期待を伝えることです。基本的な家庭のルール(門限やスマートフォン利用など)は子どもと話し合って設定し、守れなかった場合の結果(ペナルティ)も事前に共有しておきます。叱る際も頭ごなしではなく、「なぜそれが問題なのか」「それによって誰が困るのか」を冷静に説明しましょう。例えば、無断外出をした場合、「連絡がないと事故に遭ったのかと思ってとても心配した」「お父さんとお母さんはあなたが無事に帰るまで不安なんだよ」と、具体的な影響と親の気持ちを伝えます。そうすることで、子どもは自分の行動が周囲に与える影響を理解しやすくなります。また、この年代では子どもの話を最後まで聞く姿勢が重要です。頭ごなしに叱る前に「どうしてそうしたのか」本人の話す理由や背景に耳を傾け、それを踏まえてから助言や注意をすれば、子どもは自分を理解してもらえたと感じて受け入れやすくなります。
避けるべき言動
思春期の子どもに対して、感情に任せた厳しい叱責や罵倒は厳に慎むべきです。研究でも、親からの激しい叱責(怒鳴る・罵るなど)を繰り返し受けた中高生は、抑うつ症状が増え、攻撃的・反社会的な問題行動が強まることが報告されています。怒鳴って従わせようとする方法は短期的にも問題行動の改善につながらず、むしろ悪化させる恐れがあります。特に、人格を否定するような言葉や、人前で叱りつけて恥をかかせるような行為は、子どもの自己評価を傷つけ反発心を招くだけなので避けましょう。さらに、この年代では過度に干渉しすぎること(例えば、日記やスマホを無断でチェックする、交友関係を全て制限するなど)も逆効果です。自立心が芽生えている時期に親から一人の人として尊重されない経験をすると、子どもは親への不信感を募らせ、かえって本音を隠したり反抗的な態度を強める可能性があります。叱る際には個人の尊厳に配慮し、プライバシーや意見を尊重する姿勢を持つことが大切です。「中学生なんて子どもなんだから親の言うことを聞いておけばいい」といった考え方は改め、「どうしたら自尊心を育てることができるか」に親が注目して考えなければなりません。そういった意味では、親も親として成長する必要がある時期とも言えるでしょう。
中学生(13〜15歳)
効果的な声かけ・叱り方:
- 一人の人格として尊重し、ルールは話し合って決める
- 叱る前に理由を聞き、背景を理解した上で伝える
- 行動が周囲に与える影響や親の気持ちを冷静に伝える
避けるべき対応:
- 怒鳴り声や罵倒、人格否定
- プライバシーの侵害(無断でスマホを見るなど)
- 一方的な管理や過干渉
高校生(16〜18歳)
効果的なアプローチ
高校生になると、見た目は大人に近づき多くの面で自立心が強まりますが、まだ精神的・社会的には過渡期にあります。この年代では、親は「管理者」というより「相談相手」「コーチ」のような役割を意識すると良いでしょう。基本的な生活習慣や安全面のルール(飲酒・喫煙しない、深夜に無断で出歩かない等)は引き続き明確に示しつつ、子ども自身の自己決定を尊重します。効果的な関わりとして、将来や進路、交友関係などについて日頃から対話をしておくことが挙げられます。毎日少しでも会話の時間を持ち、学校での出来事や悩み・考えを聞き出すように努めましょう。思春期の子どもに対して何と声をかけたらいいか分からないという親も多いですが、日頃の対話は継続していかなければなかなか生まれないものです。親から十分な愛情とサポートを感じて育った若者は、そうでない場合に比べてリスクの高い行動(ドラッグや飲酒、無謀運転など)に手を出しにくいことが知られています。叱る場面では、頭ごなしの命令よりも「自分で判断する力」に訴える方が効果的です。例えば、夜更かしが続いている子には、「睡眠不足だと体調を崩したり成績にも影響するけど、自分はどう管理していくつもりなのかな?」と問いかけ、「こうしなさい」と指示するよりも自己管理の必要性を考えさせます。自分で決めさせたルールについては本人も納得感が強く、違反したときにも本人の反省を促しやすいです。違反時には感情的に責め立てるのではなく「自分で決めて約束したよね?守れなかったことをどう思うかな?今後はどう改善できると思う?ルールの調整が必要かな?」と冷静に話し合う方が建設的です。
避けるべき言動
16〜18歳の若者に対して、子ども扱いするような叱り方や過干渉は逆効果です。例えば、小さい頃のように頭ごなしに「こうしなさい」と命令したり、「夜9時以降はスマホ禁止にするからね」と親から細かく行動をコントロールしようとすると、かえって反発心を招き親子関係が悪化します。高校生にもなると、叱責よりも対話による解決を試みるべき段階です。強い口調で非難したり説教を長々とするより、「なぜそれが問題なのか」を論理的に伝え、子ども自身に考えさせる方が効果があります。前述したように、怒鳴ったり侮辱的な言葉で叱ることは思春期以降の子どもには有害で、特に高校生くらいになると親への反発から本人が故意に問題行動をエスカレートさせるリスクもあります。過度な干渉も避けるべきです。例えば、友人関係や進路選択に親が口を出しすぎると、子どもは自分が信頼されていないと感じて自己決定力が育たず、親の目が届かない所でかえって危険な選択をしてしまう恐れもあります。逆に自己決定力が低く育ってしまった子どもは親に頼らないと物事を決めることができずに、学校や社会で孤立したり、「仕事ができないやつ」という評価を受けてしまうかもしれません。「必要なときには助言するが最終的には本人の判断に任せる」という姿勢で接し、重大な過ちに対して注意する場合でも人前で叱りつけることは避け、プライドを傷つけない配慮をしましょう。もし、この年代になっても約束が守れないことが続き、自己決定力も一向に育たないなどがあれば、精神科的要因(知的障害や発達障害)が影響していることが考えられます。その場合は、一度専門家に相談することもご検討ください。
高校生(16〜18歳)
効果的な声かけ・叱り方:
- 親は「相談役」「コーチ」として関わる意識を持つ
- 自己決定を尊重し、必要時は冷静に助言する
- 問題点は論理的に伝え、改善策を一緒に考える
避けるべき対応:
- 子ども扱いで命令する口調
- 細かすぎる管理や高圧的な態度
- 感情的な非難や恥をかかせる叱責
大学生(18歳以上)
効果的なアプローチ
18歳を超えると法律的には大人ですが、脳の発達はまだ完全ではなく20代半ばまで前頭前野の成熟が続きます。そのため、大学生や20歳前後の子どもも判断ミスや衝動的な行動をとる可能性があり、親の支えや指導が全く不要になるわけではありません。ただし関わり方は幼い子どものそれとは大きく変える必要があります。基本的には本人の自己責任・自己決定を尊重し、親はサポート役に徹します。効果的な声かけとしては、本人が相談してきたときに傾聴し、必要に応じて助言を与えることです。こちらから一方的に干渉するのではなく、「何か困っていることはない?」「応援しているよ」といったスタンスで、いつでも頼れる存在であることを伝えましょう。大学生活や将来のキャリアについて話し合う際は、できるだけ子どもの意見や計画を尊重し、親の価値観の押し付けにならないよう注意します。叱る場合も、頭ごなしの禁止ではなく、具体的な懸念や理由を伝え、本人の自主的な改善を促す形が望ましいです。例えば、生活リズムが乱れている子に対し、「昼夜逆転だと体を壊すし勉強にも支障が出るから心配だよ。どう改善できるか一緒に考えてみようか?」というように、あくまで本人の健康や成功を願っていることを伝えつつ提案します。社会的に大人扱いされる年代だからこそ、親からも対等に近い敬意を持って接することで、子どもは素直に耳を傾けやすくなります。加えて、できていることや頑張っていることにも積極的に目を向け、「さすがだね!」「自慢の息子(娘)だよ」と声をかけることも忘れないようにしましょう。子どもからの反応はあまりないかもしれませんが、必ず自信や幸福感に繋がっていることでしょう。
避けるべき言動
大学生以上の子どもには、子ども扱いする叱り方や過干渉な態度は強い反発や親子の溝を生みます。毎日の行動を細かく監視したり、ミスに対して逐一説教するような接し方は避けましょう。例えば、「お風呂に入りなさい」「早く寝なさい」といった命令ではなく、「お風呂沸いたけど、先に入る?お母さんが先に入ってもいい?」「お母さん(お父さん)は10時頃に寝るけど、今日は何時くらいに寝るの?」など、あくまで本人の決定を引き出すような声かけを心がけるといいでしょう。研究によれば、いわゆる「ヘリコプターペアレント」(子どもに張り付いて世話を焼きすぎる親)による過干渉は、大学生の不安や抑うつ症状の増加と有意に関連していることが示されています。親が常に先回りして指示・介入していると、子どもは自立心や問題解決能力を十分に育めず、ストレスを感じたり自己肯定感を損なったりしがちです。その結果、かえって友人関係や生活面のトラブルが増える可能性も指摘されています。また、18歳以上の子どもに対して感情的に怒鳴りつけたり侮辱的な言葉を投げかけるのは、親子関係の悪化を招くだけでなく、精神的な深い傷を残します。社会的には大人である彼らは、そのような扱いを受けると距離を置こうとしたり、反発して連絡を断つこともありえます。したがって、この年代では「叱る」というよりは必要に応じて助言するという姿勢に切り替え、深刻な場合でも人格を尊重した冷静な話し合いを心がけることが大切です。
大学生(18歳以上)
効果的な声かけ・叱り方:
- 本人の判断と責任を尊重し、困ったときに寄り添う姿勢を示す
- 一方的に干渉するのではなく、必要な時だけ助言する
- 努力や成長を認め、肯定的な言葉をかける
避けるべき対応:
- 命令や監視による行動管理
- 精神的に傷つける怒鳴りや侮辱的な言葉
- 過干渉や親の価値観の押し付け
最後に
いかがだったでしょうか。
もちろん、子どもの性格や特性は多種多様で、子どもへの声かけや叱り方に「正解」はありません。
大切なのは、完璧を目指すことではなく、子どもにとって安全で安心できる存在であり続けることです。
毎日余裕がなく、つい強く叱ってしまったり、どう接すればよいか分からなくなることもあるかもしれません。
そんなときは、今日ご紹介した「その子の発達に合った関わり方」を、思い出してみてください。
子どもの行動の裏には、必ずその子なりの「理由」や「気持ち」があります。
まずはその気持ちに寄り添い、落ち着いて伝えることで、少しずつでも信頼関係が育まれていきます。
子育てに悩んでいるのはあなただけではありません。
困ったときには、家族や身近な人、医療や行政のサポートを遠慮なく頼ってくださいね。
親だって、ひとりの人間です。無理せず、少しずつ、できることからで大丈夫です。
参考文献・情報源
参考文献・情報源
● アメリカ小児科学会(AAP)
“Effective Discipline to Raise Healthy Children”(2018)
→ https://pediatrics.aappublications.org/content/142/6/e20183112
● ZERO TO THREE(米国の0〜3歳育児支援団体)
“Coping with Defiance: Birth to Three Years”
→ https://www.zerotothree.org/resource/coping-with-defiance-birth-to-three-years
● 遠藤利彦 教授(東京大学大学院教育学研究科 発達心理学)
「“ほめ方”と“叱り方”のコツ」講談社コクリコ インタビュー記事
→ https://cocreco.kodansha.co.jp/general/psychology/childcare/YoOXM
● ベネッセ教育情報サイト
「小学生を伸ばす“叱り方”とは?」
→ https://benesse.jp/kosodate/202001/20200117-1.html
● ピッツバーグ大学研究
“Yelling Doesn’t Help, May Harm Adolescents”(2013)
→ https://www.pitt.edu/news/yelling-doesn-t-help-may-harm-adolescents
● 中国青年研究(2020)
“Helicopter Parenting and Mental Health in College Students”
→ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7343269/