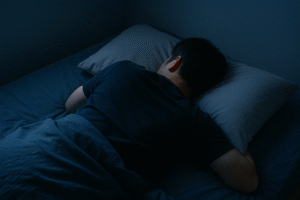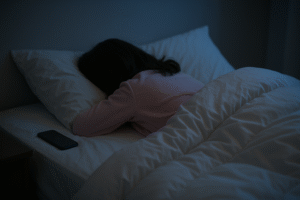こんにちは、Dr.流星です。
前回は、②1〜3歳の睡眠について取り上げましたが、今回は③3〜5歳、いわゆる就学前の子どもの睡眠についてまとめていきます。
幼稚園や保育園に通い始め、活動量が増えるこの時期は、生活リズムが家庭ごとに大きく異なり、「うちの子、昼寝はまだ必要?」「夜遅くなっても大丈夫?」といった悩みも増えてくる頃です。
睡眠時間の目安や昼寝の有無、遅寝が与える影響など、詳しく解説していきます。
それでは、早速みていきましょう。
就学前児(3〜5歳)
推奨睡眠時間
3〜5歳の就学前児童では、1日あたり10〜13時間の睡眠が推奨されます。AASMのガイドラインでは3〜5歳児は昼寝を含め10〜13時間の睡眠をとることが最適とされ、これにより心身の健康や発達が促進されるとしています。日本の指針でも同様に、幼稚園・保育園児にあたる3〜5歳児で10〜13時間程度の睡眠時間確保を推奨しています。この年代では個人差が出始め、一部の子どもは必要下限近くの10時間程度でも日中元気に過ごせますが、理想的には12〜13時間近く確保できることが望ましいでしょう。十分な睡眠時間は、子どもの記憶力や問題解決能力の発達、身体の成長に欠かせません。睡眠時間を削ってまで優先することはこの時期にはありません。小学校受験が控えている子であったとしても、睡眠時間を確保したうえで勉強や習い事をしましょう。
理想的な睡眠時間帯
就学前児の理想的な就寝時間帯は、概ね夜20〜21時頃までに就寝し、朝6〜7時台に起床するパターンです。厚労省の「早寝早起き」推進でも、幼児期から夜更かしせず朝型の生活を習慣づけるよう呼びかけています。3〜5歳頃になると保育園や幼稚園での集団生活が始まり、朝決まった時間に起きる必要がでてきます。そのため、休日でも平日と大きくずれない起床時刻にすることが望ましく、就寝時刻も毎日規則正しく保つとよいとされています。そのためには親も休日であっても平日と同じ生活リズムで活動することを心がけましょう。文部科学省の調査では、幼児期の子どもの平均的な就寝時刻は21〜22時台ですが、22時以降に就寝する子は年々増加傾向にあります。理想的には20時頃には床に就くようにし、朝は自然と目覚め、太陽の光を浴びることで体内時計をリセットする習慣作りを目指したいです。こうした習慣が小学校以降の生活リズムの基盤となります。
昼寝の必要性
3〜5歳では昼寝の必要性は個人差があります。3歳児の多くはまだ午後に1〜2時間程度の昼寝をとりますが、4〜5歳になると徐々に昼寝なしでも過ごせる子が増えてきます。米国のデータによれば、4歳児の約40%は引き続き昼寝をしており、5歳でも約30%が日中に眠る習慣があるとされています。日本でも、保育園では年少〜年中児まではお昼寝時間を設けていますが、年長児になると「お昼寝しない」子も出てきます。これは発達に伴い夜間にまとめて必要な睡眠をとれるようになるためです。昼寝をやめるタイミングは子どもによって異なりますが、おおむね3〜5歳の間に移行します。昼寝をしなくても夕方まで機嫌よく過ごせるようであれば無理に寝かせる必要はありません。一方、昼寝をしないことで夕方以降に極端に不機嫌になったり疲れすぎたりする場合は、短時間でも昼寝を続けたほうが良いでしょう。ポイントは夜の睡眠に響かない範囲で昼寝をとることであり、遅い時間まで昼寝を引きずらないようにします。
睡眠不足・過剰睡眠の影響
就学前児は知的好奇心が旺盛で情緒も発達する時期ですが、睡眠不足はその健全な発達を妨げかねません。慢性的な睡眠不足の幼児は、注意力や記憶力の低下、落ち着きのなさ(多動傾向)や情緒不安定といった問題が現れることがあります。大阪大学の研究グループは、幼児期早期に睡眠が不規則な子どもは認知機能やコミュニケーション能力、社会性の発達に負の影響が出る可能性を示しています。例えば、毎晩就寝時刻が遅く不規則な幼児は、年齢相応の社会的スキルの習得が遅れる傾向があるとの報告があります。さらに、幼児期の短い睡眠は将来の肥満リスクとも関連します。日本の疫学研究でも、3歳時点で睡眠時間の短かった子は小学生になったとき肥満になりやすいことが示されています。一方、推奨より極端に長い睡眠(過剰睡眠)は幼児ではあまり一般的ではありませんが、もし13時間を大幅に超えて眠る場合は何らかの睡眠障害や日中の活動不足が疑われます。過剰な睡眠はかえって夜間の睡眠の質を低下させ、昼夜逆転を招く可能性もあります。総じて、3〜5歳では適切な睡眠確保が情緒の安定と認知発達に直結しており、不足すれば問題行動や学習意欲の低下につながるため注意が必要です。
就学前児(3〜5歳)
- 必要な睡眠時間: 1日10〜13時間。夜間睡眠中心に。
- 睡眠時間帯: 21時までに就寝、朝6〜7時台に起床が理想。
- 昼寝: 必要性に個人差あり。徐々に不要になる。
- 影響: 睡眠不足は注意力や社会性の低下、肥満リスクを高める。
共通事項
各年齢段階で共通して言えることは、適切な睡眠習慣(十分な睡眠時間の確保と規則正しい就寝・起床リズム)が子どもの健全な発育・発達に不可欠だという点です。睡眠中には成長ホルモンの分泌や記憶の整理、細胞の修復が行われ、心身の成長を支えます。そのため、慢性的な睡眠不足は身体的成長の遅れ、認知機能の低下、情緒面の不安定、問題行動の増加、生活習慣病リスクの上昇など多岐にわたる悪影響を及ぼします。一方で過剰な睡眠も、子どもの場合は多くありませんが、極端な長時間睡眠は何らかの不調(倦怠感や無気力感など)を示す可能性があります。子どもの年齢に応じた適切な睡眠時間と生活リズムを家庭・学校で支援し、「寝る子は育つ」という言葉通り十分な睡眠をとることが、子どもの健康な発育・学習・生活の土台となります。
次回は、④6~12歳の小学生頃についてまとめていきたいと思います。
参考文献・情報源
国際機関・学会ガイドライン
- American Academy of Sleep Medicine (AASM). (2016). Consensus Statement: Recommended Amount of Sleep for Pediatric Populations. [Journal of Clinical Sleep Medicine, 12(6):785–786].
https://jcsm.aasm.org/doi/10.5664/jcsm.5866 - American Academy of Pediatrics (AAP). (2014). School Start Times for Adolescents. Pediatrics, 134(3):642–649.
https://doi.org/10.1542/peds.2014-1697 - World Health Organization (WHO). (2019). Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children under 5 years of age.
https://www.who.int/publications/i/item/9789241550536
日本の行政・学会資料
- 厚生労働省. (2023). 「健康づくりのための睡眠指針 2023(子ども編)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32777.html - 文部科学省. (2022). 「子供の生活習慣と学習意欲に関する調査結果」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155_00001.htm - 日本小児保健協会. (2016). 「子どもの睡眠と健康~小児科医がすすめる睡眠の知恵~」
https://www.jschild.or.jp/modules/publication/index.php?content_id=14
医学論文・研究報告(PubMed収載)
- Mindell, J. A., et al. (2015). Developmental aspects of sleep hygiene: Findings from the 2014 National Sleep Foundation Sleep in America Poll. Sleep Health, 1(1), 40–47.
https://doi.org/10.1016/j.sleh.2014.12.002 - Touchette, E., et al. (2007). Short night-time sleep-duration and hyperactivity trajectories in early childhood. Pediatrics, 120(4), 850–857.
https://doi.org/10.1542/peds.2006-1874 - Sadeh, A., et al. (2011). Sleep and the transition to kindergarten: A longitudinal study. Developmental Psychology, 47(2), 378–391.
https://doi.org/10.1037/a0021804 - Lo, J. C., et al. (2016). Effects of Partial and Acute Total Sleep Deprivation on Performance across Cognitive Domains, Individuals and Circadian Phases. Sleep, 39(3), 687–698.
https://doi.org/10.5665/sleep.5552
補足的資料
- National Sleep Foundation (NSF). (2015). Sleep Duration Recommendations: Methodology and Results Summary.
https://www.sleepfoundation.org/professionals/sleep-duration - National Institutes of Health (NIH). (2011). Your Guide to Healthy Sleep.
https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/public/sleep/healthy_sleep.pdf