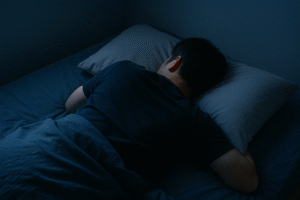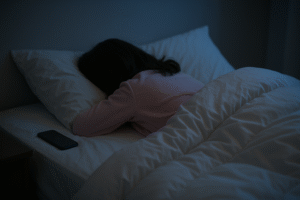こんにちは、Dr.流星です。
赤ちゃん期を過ぎ、少しずつ「自我」が芽生えてくる1〜3歳。
この時期は、「イヤ!」という言葉が増え、いわゆる“イヤイヤ期”に入り始める頃でもあります。
睡眠においても、「寝かしつけてもなかなか寝てくれない」「昼寝をすると夜に寝ない」など、今までとは違った難しさが出てきたと感じているご家庭も多いのではないでしょうか。
この年代は、身体も心も急速に発達する時期であり、十分な睡眠が成長・情緒・学習能力の土台を築く重要な役割を果たします。
今回は、1〜3歳の子どもにとって必要な睡眠時間や理想的なリズム、昼寝との付き合い方、睡眠不足がもたらす影響について、医学的な視点からわかりやすくまとめていきます。
幼児(1〜2歳)
推奨睡眠時間
1〜2歳の幼児には、1日あたり合計11〜14時間の睡眠が推奨されています。米国睡眠医学会(AASM)のコンセンサスによれば、1〜2歳児は昼寝を含めて11〜14時間の睡眠を確保することが最適な健康状態を促すとされており、日本の厚生労働省の「睡眠指針」でもこの国際基準を踏まえ、1〜2歳児で11〜14時間程度の睡眠時間を目安にするよう推奨しています。2歳前後になると身体活動量が増えますが、そのぶん睡眠でしっかり疲労を回復させ、成長ホルモン(疲労を回復させる作用もある)の分泌を促す必要があります。
理想的な睡眠時間帯
幼児期前半では早寝早起きの習慣が重要になります。理想的には夜19〜21時頃までに就寝し、朝6〜7時台に起床するリズムが望ましいです。この年代の子どもはまだ夜遅くまで起きているだけの体力や成熟度がないため、夜は早めに寝かせ日が昇る頃に起きる生活が適しています。厚労省の指針でも、「幼児期から早寝早起きを習慣づけ、朝決まった時間に起きて日光を浴び、夜更かしを避ける」ことが推奨されています。具体的には、朝の起床時刻を一定に保った上で、必要な睡眠時間から逆算して就寝時刻を決める方法が勧められています。例えば、朝7時に起こすなら、1〜2歳児の場合は夜9時までに寝付けば約10時間の夜間睡眠がとれる計算です。理想を言えば、朝は自然と6~7時に目が覚めるようにしたいです。朝6時半に子どもが「ママ(パパ)起きて!」と起こしてきたとしても、「いい時間に自然と起きてる!いいこと!」と思えたら、眠くても褒めてあげたいとさえ思えるかもしれませんね。日中たくさん遊んで身体を動かすほど夜は自然と眠くなるため、日中の適度な運動も規則正しい就寝につながります。
昼寝の必要性
1〜2歳児は引き続き昼寝が必要です。ただし、新生児や乳児期に比べて昼寝の回数は減り、多くの幼児は1日1回の昼寝に移行します。一般的に1歳代では午前と午後に2回昼寝をしていた子どもも、18〜24か月頃までにお昼頃1回の昼寝にまとまっていきます。米国睡眠財団のデータによれば、94%の幼児は5歳までに昼寝をやめるものの、2〜3歳では大半の子がまだ1日1回は昼寝をしていると報告されています。このため1〜2歳ではお昼過ぎに1〜2時間程度の昼寝時間を確保するとよいでしょう。昼寝は夜の就寝時間とのバランスが大切で、遅い時間帯の長い昼寝は夜更かしの原因になるため避けます。一方で昼寝を早々にやめてしまうと、夜まで起きている間に疲れすぎてしまい夕飯やお風呂などの活動中に寝てしまったり、かえって機嫌が悪くなると癇癪を起こして入眠が難しくなったりすることもあるため注意が必要です。適切な時間帯(午後の早い時間)に短めの昼寝をとらせることで、夜まで機嫌良く活動でき、かつ夜もスムーズに眠れるリズムをつくります。
睡眠不足・過剰睡眠の影響
幼児期の子どもは睡眠不足になると顕著に行動や気分に影響が現れます。十分に眠れていない1〜2歳児は、日中機嫌が悪くなったり癇癪(かんしゃく)を起こしやすくなったりします。また注意力が散漫になり、遊びや学びに集中できなくなります。睡眠不足が続く幼児は、事故やけがのリスクも高まることが指摘されています。実際、睡眠不足の子どもは昼間の転倒や事故が増えるとの報告もあります。また、この時期は言葉や基本的生活習慣を身につける重要な時期ですが、慢性的な睡眠不足はそうした発達課題の達成を遅らせる可能性があります。一方、過剰な睡眠については、夜間に必要以上に長く眠りすぎる幼児は稀ですが、例えば昼寝が長すぎて夜眠れないという場合には生活リズムが逆転し発達によくありません。過度の昼寝で夜の睡眠が削られると、成長ホルモン分泌のリズムが乱れ身体の発育に影響する可能性があります。総じて、1〜2歳では睡眠不足は情緒不安定や問題行動(かんしゃく・多動傾向)の一因となり得ること、そして睡眠時間が推奨範囲より極端に長い場合は潜在的な睡眠障害や生活リズムの乱れを示唆することが知られています。
幼児(1〜2歳)
- 必要な睡眠時間: 1日11〜14時間(夜+昼寝)。
- 睡眠時間帯: 夜は19〜21時に就寝、朝6〜7時に起床が理想。
- 昼寝: 基本1回。午後の1〜2時間が一般的。
- 影響: 睡眠不足は癇癪・情緒不安定・多動傾向に。昼寝が遅いと夜間の入眠困難に。
共通事項
各年齢段階で共通して言えることは、適切な睡眠習慣(十分な睡眠時間の確保と規則正しい就寝・起床リズム)が子どもの健全な発育・発達に不可欠だという点です。睡眠中には成長ホルモンの分泌や記憶の整理、細胞の修復が行われ、心身の成長を支えます。そのため、慢性的な睡眠不足は身体的成長の遅れ、認知機能の低下、情緒面の不安定、問題行動の増加、生活習慣病リスクの上昇など多岐にわたる悪影響を及ぼします。一方で過剰な睡眠も、子どもの場合は多くありませんが、極端な長時間睡眠は何らかの不調(倦怠感や無気力感など)を示す可能性があります。子どもの年齢に応じた適切な睡眠時間と生活リズムを家庭・学校で支援し、「寝る子は育つ」という言葉通り十分な睡眠をとることが、子どもの健康な発育・学習・生活の土台となります。
次回は、幼稚園に通う頃の③3~5歳頃についてまとめていきたいと思います。
参考文献・情報源
国際機関・学会ガイドライン
- American Academy of Sleep Medicine (AASM). (2016). Consensus Statement: Recommended Amount of Sleep for Pediatric Populations. [Journal of Clinical Sleep Medicine, 12(6):785–786].
https://jcsm.aasm.org/doi/10.5664/jcsm.5866 - American Academy of Pediatrics (AAP). (2014). School Start Times for Adolescents. Pediatrics, 134(3):642–649.
https://doi.org/10.1542/peds.2014-1697 - World Health Organization (WHO). (2019). Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children under 5 years of age.
https://www.who.int/publications/i/item/9789241550536
日本の行政・学会資料
- 厚生労働省. (2023). 「健康づくりのための睡眠指針 2023(子ども編)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32777.html - 文部科学省. (2022). 「子供の生活習慣と学習意欲に関する調査結果」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155_00001.htm - 日本小児保健協会. (2016). 「子どもの睡眠と健康~小児科医がすすめる睡眠の知恵~」
https://www.jschild.or.jp/modules/publication/index.php?content_id=14
医学論文・研究報告(PubMed収載)
- Mindell, J. A., et al. (2015). Developmental aspects of sleep hygiene: Findings from the 2014 National Sleep Foundation Sleep in America Poll. Sleep Health, 1(1), 40–47.
https://doi.org/10.1016/j.sleh.2014.12.002 - Touchette, E., et al. (2007). Short night-time sleep-duration and hyperactivity trajectories in early childhood. Pediatrics, 120(4), 850–857.
https://doi.org/10.1542/peds.2006-1874 - Sadeh, A., et al. (2011). Sleep and the transition to kindergarten: A longitudinal study. Developmental Psychology, 47(2), 378–391.
https://doi.org/10.1037/a0021804 - Lo, J. C., et al. (2016). Effects of Partial and Acute Total Sleep Deprivation on Performance across Cognitive Domains, Individuals and Circadian Phases. Sleep, 39(3), 687–698.
https://doi.org/10.5665/sleep.5552
補足的資料
- National Sleep Foundation (NSF). (2015). Sleep Duration Recommendations: Methodology and Results Summary.
https://www.sleepfoundation.org/professionals/sleep-duration - National Institutes of Health (NIH). (2011). Your Guide to Healthy Sleep.
https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/public/sleep/healthy_sleep.pdf