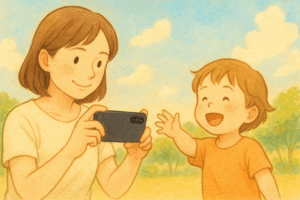こんにちは、流星パパです。
今回は、子育て世代の方にも参考になる「睡眠時の室温」について、私自身が家庭で実践していることを、科学的根拠と精神科医としての見解も交えてご紹介します。
自宅では家族全員で同じベッドに寝ています(ベッドの紹介もそのうちしますね)。家族みんなが快適に眠れるように、睡眠に関するエビデンスを意識して、環境を整えることを心がけています。
記事の後半では根拠となる文献も紹介しますので、ご自身やご家族の睡眠改善に少しでも役立てていただければ幸いです。
室温は「夏は23度以下」
「え、寒くない?」と思う方もいるかもしれませんが、それには理由があります。
我が家では温湿度計を寝室に設置し、空気清浄機・サーキュレーター・加湿器(主に冬)を活用しつつ、エアコンもフル活用しています。湿度は50%前後に調整しています。
23℃以下に室温を保つ理由は、「深部体温、特に脳の温度を下げるため」です。そして、睡眠の質を高めるために意識しているのは「手足は布団から出して熱を逃がす」「体幹や腕・脚は冷やさない」というポイントです。
具体的には、夏場でも室温は23℃以下を維持し、長袖・長ズボン(冬よりは薄手)で寝ています。体幹は薄い羽毛布団(うちはニトリ製)で覆い、手足は布団の外へ。マスクは基本つけませんが、必要な時も鼻は覆わないようにしています。子どもは布団をかけていてもすぐに離脱するので、「着る」タイプのものにしています(これもそのうち紹介しますね)。
この効果は私自身実感しているところで、寝つき・目覚めともにスムーズで、睡眠時間が予定外に短くなってしまってもある程度休めている感覚はあります。目覚めに関しては、朝はカーテンを開けて日光を浴びることも心がけています(自動カーテン開閉ガジェットの導入もおすすめです)。
夏場の寝苦しさや睡眠環境に悩んでいる方の参考になればうれしいです。
脳を冷やすとは
「脳を冷やす」とは、睡眠中に脳がしっかり休息できるようにすることです。実際に「脳が休息するために適した室温は23℃以下」と言われており、寝室の温度もやや低めに保つことが推奨されています。ただし「脳は冷やしたいが体は冷やしたくない」ため、長袖・長ズボン+布団で体幹を守りつつ、深部体温を下げるために熱を逃がしやすい手足は外に出しておきます。
暑い環境(28度以上では特に顕著)だと、脳も「寝苦しさ」を感じ、寝返りや体動が増え、睡眠の質が低下することが報告されています。
さらに、脳は頭の外側から直接冷やせるわけではなく(頭蓋骨などがありますからね)、鼻腔(特に鼻の奥)が脳に最も近い冷却経路だと考えられています。冷たい空気が鼻から入ることで、間接的に脳を冷やすことができるため、マスクをする場合も鼻はできるだけ覆わないようにします。そういう意味では、「鼻詰まり」も睡眠の質を損なう原因となり得るので注意が必要ですね。
脳が休まると自然と睡眠は質のいいものになります。逆に暑い環境では「脳も寝苦しい」ようで、寝返りなどの体動が顕著に増えることが報告されています。
おわりに
少し長くなりましたが、私が日々実践している睡眠環境の工夫についてご紹介しました。これから夏本番ですが、ご家族皆さんが快適に眠れるよう、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
この後には、公的機関や論文などの参考文献を掲載しますので、根拠となる情報もぜひご覧ください。
日本睡眠科学研究所の推奨
- 同研究所は、冬場の睡眠時の理想的な室温を22~23℃、湿度を50~60%としています。
- これは、深部体温の適切な低下を促し、スムーズな入眠と深い睡眠を実現するためです。
- 室温が高すぎると体温の放散が妨げられ、低すぎると末梢血管の収縮により深部体温の低下が阻害され、いずれも睡眠の質に悪影響を及ぼします。
厚生労働省のガイドライン
- 「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」では、夏季において寝室の室温上昇が睡眠時間の短縮や睡眠効率の低下を招くと報告されています。
- これにより、エアコンを活用して寝室を涼しく保つことが推奨されています。
その他
- Sleep Foundation: https://www.sleepfoundation.org/bedroom-environment/best-temperature-for-sleep
- Healthline: https://www.healthline.com/health/sleep/best-temperature-to-sleep
- PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37474050/
- Neuroscience News: https://neurosciencenews.com/optimal-sleep-temperature-23840/
- Verywell Health: https://www.verywellhealth.com/best-temperature-for-sleep-8601415
- WIRED: https://www.wired.com/story/sleep-disruption-heat-wave
- 小澤健史ほか「睡眠時の室温が睡眠と体動に与える影響」東京都市大学
https://www.comm.tcu.ac.jp/rijal_lab/articles2011/ozawa02.pdf