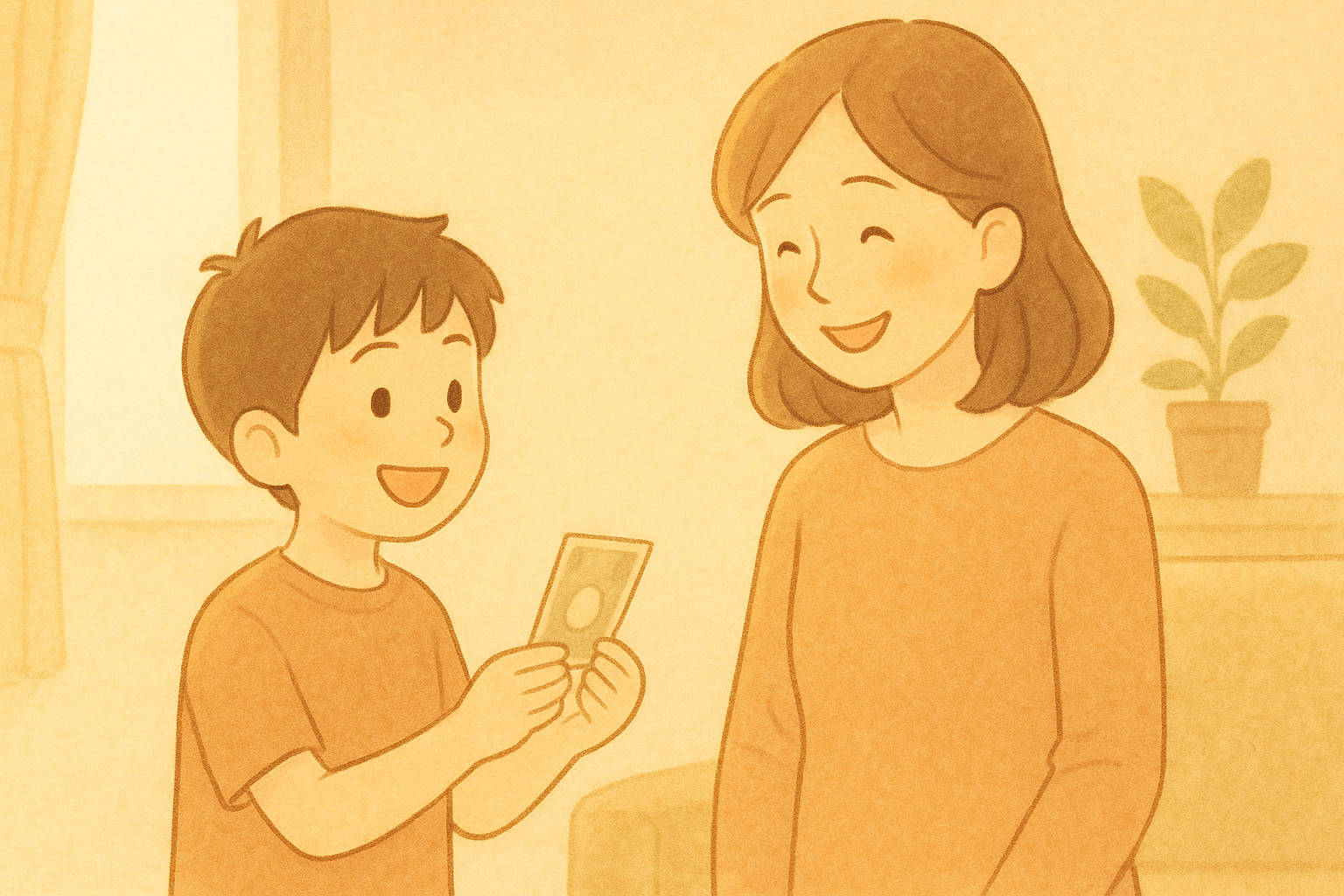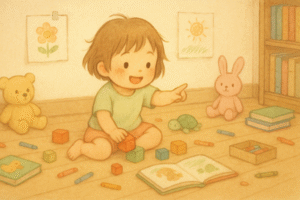こんにちは、Dr.流星です。
子どもにお小遣いを渡すべきか、いつからどれくらい渡すべきか──これは多くの保護者が直面する悩みです。お小遣いは単なる「お金のやり取り」ではなく、子どもに金銭感覚を教える絶好の機会です。
本記事(全2記事)では、日本の未就学児から大学生まで各年代におけるお小遣いの実態をデータで紹介し、子育ての視点から金銭に関する教育のポイントを解説します。
健全な金銭感覚や自己管理能力、自尊心を育むお小遣いの与え方について具体例を交えながら一緒に考えてみましょう。
年齢別:日本の子どものお小遣い事情(平均額・頻度)
まず、各年代の子どもがどれくらいお小遣いをもらっているのか、信頼できる調査結果を見てみましょう。金融広報中央委員会の2023年調査によれば、日本の家庭で子どもに渡している月々のお小遣いの平均額は以下の通りです:
- 未就学児(小学校入学前):月約3,052円
- 小学校低学年(1~2年生):月約2,213円
- 小学校中学年(3~4年生):月約1,751円
- 小学校高学年(5~6年生):月約2,054円
- 中学生:月約3,860円
- 高校生:月約6,629円
- 大学生(短大・専門学校含む):月約22,208円
これらは1人当たりの平均値であり、実際には各家庭の経済状況や方針によって差があります。また、お小遣いを「定期的にもらっている」子どもは年齢が上がるほど増える傾向があります。例えば、高校生では、約75%が定期的または必要なときにお小遣いを受け取っており、定期的にもらう生徒だけでも約53%にのぼります。高校生のお小遣い額は平均で5,333円(中央値5,000円)程度という調査結果もあります。一方、小学生では低学年のうちは「必要なときに都度渡す」家庭も多く、学年が上がるにつれて「月に1回決まった額を渡す」定額制へ移行する家庭が増えていきます。実際、小学生低学年では月1回お小遣いを渡す家庭はわずか13.4%ですが、中学年で32.1%、高学年では45.0%と約半数近くに増加します。
お小遣いの典型的な金額も成長とともに上がります。小学生の具体例を挙げると、ある調査では小学1~2年生で月500円程度が一般的で(最頻値500円)、小学5~6年生になると月1,000円程度が中央値になるとの報告があります。低学年では決まった日に100円玉を数枚渡す程度だった子が、高学年になるころには500円玉や1,000円札を渡され、自分でやりくりを考える機会が増えるわけです。このように、「いくら渡すか」「どの頻度で渡すか」は子どもの年齢と発達段階によって変わっていくものです。
金銭感覚の発達とお小遣いが与える影響
子どもの金銭感覚(お金に対する理解)は徐々に発達していきます。幼児期(未就学児)の子どもは、お金そのものの価値をまだ十分に理解できません。例えば、2~3歳児では「お金を払うと物が買える」という概念すら曖昧ですが、発達の早い子では2歳代後半から金銭の役割に気づき始めることが報告されています。ここで、年代別の金銭感覚の発達についてみていきましょう。
幼児期(2~5歳)
幼児期には数の概念も未熟なため、硬貨や紙幣の大きさ・見た目で価値を判断してしまうこともあります(例:10円玉の方が100円玉より大きいので価値があると思う 等)。したがって、この時期に高額なお小遣いを与えても正しく扱えず、目の前のお菓子やオモチャにすぐ使ってしまうでしょう。幼児には、お小遣いという形よりも、買い物ごっこや実際の買い物体験を通じて「お金を渡すと物と交換できる」ことを教える程度でも十分です。例えば、スーパーで親と一緒にお菓子を選び、レジで100円玉を店員さんに手渡してみる、といった経験がとても大切です。消費者庁の調査でも、日常的に買い物や家計管理を経験している子どもほど金銭の価値理解度が高いことが示されています。遊び感覚であってもお金に触れる機会を持つことが、金銭感覚発達の第一歩となるのです。
小学校低学年(6~7歳)
小学生になると、算数教育も始まり数の理解が深まるため金額の比較や計算ができるようになります。低学年ではまだ衝動的に使ってしまいがちですが、「○○円あれば△△が買える」という目的志向も芽生えてきます。例えば、7歳の子が200円のお菓子を買うために、毎日20円ずつ10日貯める、といった計画が立てられるようになる頃が、お小遣い教育の始めどきです。実際、「おこづかいをあげ始めるタイミングは子どもが『買う』『貯める』といったお金の役割を理解し、欲しいものが出てきた頃」とされ、小学校入学前後が一つの目安と言われます。
小学校中~高学年(8~11歳)
小学校中~高学年にもなると、自制心や計画性も徐々に伸びてきます。発達心理学の観点から、欲求を我慢したり先を見通したりする力(セルフコントロール)はお金の使い方と深く関わります。この時期に定額のお小遣いを渡し、自分でやりくりさせる経験は、「限られたお金をどう使うか」を考えさせ、計画性と自制心を鍛える訓練になります。逆に「欲しいときに親に言えば買ってもらえる」という状況だと、お金の有限性を学べず計画性が育ちにくいとの指摘もあります。実際、ある教育セミナーでは「必要な時に都度買ってあげている」家庭が増えている一方で、その環境では「自分で考えてやりくりする力」が身につかないのではと専門家が懸念を示しています。
中学生・高校生(12~18歳)
中学生以上になると、友達付き合いや娯楽の幅も広がり、お金の使い道が複雑になります。塾代や部活動費は親が負担しても、スマホの課金や友人との遊びに使うお金は本人のお小遣いから、という家庭も多いでしょう。思春期の子どもは自己主張や独立心が強まる一方、衝動的な行動も出やすい時期です。お小遣いの範囲内で欲しいものを買う経験は、衝動と折り合いをつける練習になります。例えば、月末にお金が足りなくなって困れば、「来月から計画的に使おう」という学びにつながりますし、どうしても欲しい高額な物があるときに「お年玉を貯金して補おう」と工夫するのも立派な計画性です。それでも足りない場合は親と「じゃあ、半分は自分で出して、半分は誕生日プレゼントとして援助しよう」「今度のテストで数学が平均点以上なら特別な援助をしよう」など話し合う機会にもなります。このように、お小遣いは失敗しても大事にならない範囲で金銭管理を練習できる場と言えます。それを経験しないまま高校卒業後に突然クレジットカードやローンを手にできるようになったら、トラブルに陥るリスクが高まるでしょう。事実、2022年に成年年齢が18歳に引き下げられ、高校生でも契約やクレジットカードを親の同意なしで持てる時代になったことで、若者の消費者トラブル増加が指摘されています。特にスマホゲームや詐欺に膨大なお金を使ってしまったケースはよく目にします。こうした背景からも、高校生までにお金との付き合い方を身につけさせることの重要性が増しています。
次回予告
いかがでしたでしょうか。
ご家庭ごとにお小遣いや金銭感覚の考え方はさまざまですが、どのご家庭にも共通しているのは、「お小遣い」が子どもの金銭感覚を育てる大切な機会であるという点です。親子で話し合うきっかけになったり、時には意見がぶつかることもあるかもしれませんが、それもまた成長のプロセスの一部です。現代は現金だけでなく、電子マネーやスマホ決済など多様な支払い方法が普及しています。だからこそ、小さいうちからお金のやりくりを経験し、ときには失敗も通じて「正しい金銭感覚」を身につけることがより重要になっています。
次回は、精神科医の視点から金銭感覚やお小遣いが子どもの心にどのような影響を与えるのか、さらに詳しく解説していきます。ぜひご覧ください。
参考文献・資料(出典)
金融広報中央委員会. 「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」
https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/yoron/futari/2023/
公益財団法人 消費者教育支援センター・生命保険文化センター. 「高校生の消費生活と生活設計に関するアンケート調査(第3回)」報告書(2022年)
https://www.jili.or.jp/files/press/2022/20230227.pdf
博報堂教育財団こども研究所. 「令和5年のおこづかい事情」トピックス調査(2023年)
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/kodomo/childresearch/report/2023/20230310.html
りそなグループ. 「小学生にお小遣いはいつから渡す?平均額や管理方法もあわせて解説」(2024年更新)
https://www.resonabank.co.jp/kojin/kids_mama/column/okodukai/
日本家政学会監修. 「幼児期における金銭教育 – 子どもの経済的社会化に向けて」
https://www.jshe.jp/contents/column/education/kodomo.html
消費者庁 消費者教育ポータルサイト. 「子どもの金銭価値理解度」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/portal/
SHINGA FARM(伸芽会). 「定額制VS報酬制!? 子どものおこづかい、どうしていますか?」
https://www.shinga-farm.jp/column/okozukai-2step/
ファイナンシャルフィールド. 「子どもへの金銭教育も忘れずに」
https://financial-field.com/living/entry-20230303-153429.html
文部科学省. 「消費者教育の推進」
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/shouhi/
消費者庁. 「若年者向け消費者教育教材・金融トラブル防止の取り組み」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/young/