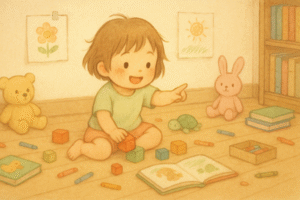こんにちは、Dr.流星です。
前回は、お小遣いをきっかけにした金銭感覚の育て方や、ご家庭でできる金銭教育についてお伝えしました。
今回は、精神科医としての視点から、金銭教育が子どもの心や発達にどのような影響を与えるのか、その大切さについて掘り下げてお話ししていきます。
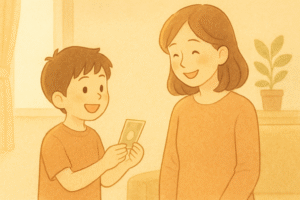
精神科医の視点から見た望ましい金銭教育とは
精神科医として子どもの発達やメンタルヘルスの側面から金銭教育を考えると、お小遣いは「脳の報酬系」(=うれしいことや達成感を得たときに脳が快感を感じる仕組み)を健全に発達させるチャンスだと言えます。人間の脳は、欲しい物を手に入れたり達成感を得たりしたときに喜びを感じ、それが行動の動機づけになります。しかし、報酬が大きすぎたり頻度が極端だと、いわゆる依存症的な報酬追求に陥る危険があります。例えば、幼少期に際限なくお金や物を与えられた子は、快感への耐性ができにくく、将来買い物依存やギャンブルなど「もっともっと」「足りない、満足できない!」と更なる快楽を求める傾向(欲求コントロールの困難さ)を助長しかねません。一方で、何のご褒美もなく我慢ばかりさせるのも良くありません。お小遣いという適度な枠の中で、我慢と報酬のバランスを学ばせることが精神的健全さにつながります。子どもが自分で計画しお金を貯めて欲しいものを買えたとき、脳内には達成の快感が生じます。その小さな成功体験の積み重ねが自己肯定感や自信を育むのです。逆に計画通りにいかず失敗したときも、大きなリスクを伴わない子どものお金だからこそ、「どうすればよかったかな?」「次はこうしてみたらどう?」と振り返り、衝動をコントロールする力を養う教材にできます。
さらに、お小遣いを通じた親子の対話は家庭内コミュニケーションを深め、メンタルヘルスの安定にも寄与します。お金の使い道という具体的な話題は、親子で向き合って話し合う練習に最適です。「この子は今こんなことに興味・関心があるんだ」「上手に計画を立てて、意外としっかり考えているんだな」と親が新たな一面に気づいたり、子どもも「ちゃんと話を聞いてくれるんだ」「お父さん(お母さん)のアドバイスがあれば上手くいく」と感じれば、信頼関係が強まります。それは思春期の非行防止や、悩みを相談しやすい親子関係作りにもつながるでしょう。金銭トラブルや依存症の予防という点でも、家庭でオープンに金銭教育が行われていることは重要です。消費者庁の研究では、金融教育を受けた若者は受けていない若者に比べて詐欺被害や金銭トラブルに遭うリスクが低いという結果も出ています。早いうちから健全なお金の価値観を身につけさせることは、心の安全ネットを張ることでもあるのです。
お金と愛情のバランスは非常にシビアで難しい
最後に、精神科医の立場から強調したいのは「お金=愛情」にならないようにすることです。つい子どもが可愛くて「あれもこれも買ってあげる」「お小遣いをどんどん与える」というのは、確かに子どもの幸福そうな姿を見ることができるでしょう。また、仕事が忙しくて子どもの相手ができないため、お金で解決しようとすることもあるかもしれません。それは子どもの捉え方にもよりますが、やはり金銭感覚の育成や愛着の形成という観点からは危険を含んでいると言えます。つまり、お金を渡す、買ってあげることが親の愛情表現の中心になってしまうと、子どもは「物質的な満足=愛情」と誤解してしまう恐れがあります。こうなると、「お金をくれない」「物を買ってくれない」=「自分は愛されていない、大切にされていない」「満足できない。幸せを感じない」となってしまう可能性があり、世間的にも周囲との感覚のズレが発生し得ることになります。つまり、子ども自身にとって将来人間関係や自己評価に歪みが出るリスクになると考えられるでしょう。一方で、罰としてお小遣いを取り上げたり、金額で子どもをコントロールしようとするのも避けるべきです。お小遣いはあくまで教育と自立のための手段であり、愛情やしつけの代替ではない、とういうことです。例えば、子どもがルールを破って無駄遣いしてしまった場合、「もう次からお小遣いなし!」と感情的に罰するのではなく、どう使ったのか、何に使ったことがもったいなかったのかを一緒に振り返り、必要なら一時的に追加を控える、お金を使うときは親と一緒に支払いをするなど冷静に対応しましょう。お金の話を通じてでも、子どもに向き合う姿勢そのものが愛情であることを忘れないでください。お小遣いはあくまで教育と自立のためのツールであり、愛情やしつけの代わりではありません。
おわりに:金銭教育は将来への投資
子どものお小遣いと金銭教育について、全2回でデータと専門知見をもとに解説しました。各年齢でお小遣いの額や渡し方は様々ですが、共通して言えるのは「金銭教育の目的」を意識することです。お小遣いは、子どもにお金の大切さや使い方、我慢と計画性を教える家庭でできる最良の教材です。そして何より、お金の話を通じて子どもの成長を見守り、一緒に喜んだり考えたりすること自体が、将来への大きな財産になるでしょう。文部科学省や消費者庁も学校教育や教材を通じて金融・消費者教育を推進していますが、家庭での日々の積み重ねに勝るものはありません。ぜひ今日から、年齢に合った形でお小遣い教育を取り入れてみてください。それは子どもの経済的自立への第一歩であると同時に、健全な心を育む一助にもなるのです。子どもがお金との上手な付き合い方を身につけ、将来社会に出たときに自信をもって自立できるよう、親として長い目でサポートしていきましょう。
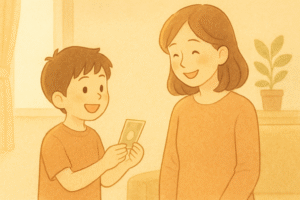
参考文献・情報源
- 金融広報中央委員会. 「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」
https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/yoron/futari/2023/ - 公益財団法人 消費者教育支援センター・生命保険文化センター. 「高校生の消費生活と生活設計に関するアンケート調査(第3回)」報告書(2022年)
https://www.jili.or.jp/files/press/2022/20230227.pdf - 博報堂教育財団こども研究所. 「令和5年のおこづかい事情」トピックス調査(2023年)
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/kodomo/childresearch/report/2023/20230310.html - りそなグループ. 「小学生にお小遣いはいつから渡す?平均額や管理方法もあわせて解説」(2024年更新)
https://www.resonabank.co.jp/kojin/kids_mama/column/okodukai/ - 日本家政学会監修. 「幼児期における金銭教育 – 子どもの経済的社会化に向けて」
https://www.jshe.jp/contents/column/education/kodomo.html - 消費者庁 消費者教育ポータルサイト. 「子どもの金銭価値理解度」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/portal/ - SHINGA FARM(伸芽会). 「定額制VS報酬制!? 子どものおこづかい、どうしていますか?」
https://www.shinga-farm.jp/column/okozukai-2step/ - 名古屋テレビ ニュース. 「“お金教育”で無駄づかい回避 “定額制”と“報酬制”の2ステップが大事」
https://www.nagoyatv.com/news/?id=015687 - ファイナンシャルフィールド. 「子どもへの金銭教育も忘れずに」
https://financial-field.com/living/entry-20230303-153429.html - 文部科学省. 「消費者教育の推進」
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/shouhi/ - 消費者庁. 「若年者向け消費者教育教材・金融トラブル防止の取り組み」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/young/
※記事内で使用した全てのデータ・引用は、各公的機関や教育関連団体の公式サイト・公式報告書に基づいています。URLは2025年6月時点のものです。